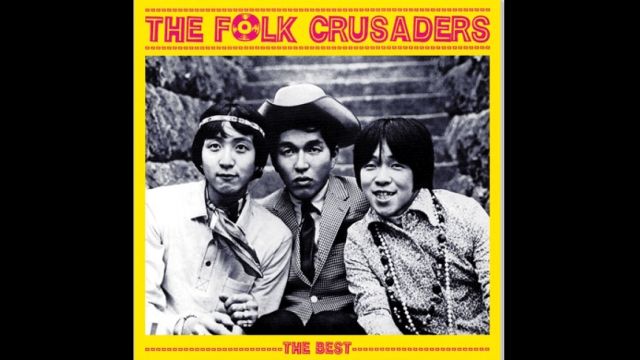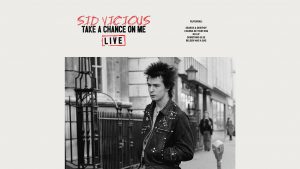2009年10月16日に加藤和彦が亡くなったニュースを知ってしばらくして、朋友の北山修が書いた追悼の文章を読んだとき、無念の思いとともに静かな怒りのようなものがこみあげてきたのを覚えている。
なぜ自殺したのか、自殺しなければならなかったのか。
どうして「ヘルプ!」と叫ばなかったのだろう?
前だけを向いて生きる加藤がジョン・レノンにも通じるのではないか‥‥。
そう気づいたのは10月13日に公開された本コラムで、石浦由高の文章を読んだときのことだ。
ジョンが「ヘルプ!」と叫んだことについて、石浦は「消えてしまいそうな魂の叫び声~ジョンの素顔その2」というコラムでこう述べていた。
「ヘルプ!」悲痛な叫び声から始まるの歌詞は次のように続く。
♪
僕がまだ若かった頃
今日よりずっとずっと若かった頃
どんな時だって
僕は誰かの助けを求めたことはなかった
♪
状況は突然、変わるわけではない。
だが、主人公は自らが絶望的な孤独の中にいることに、ある日、突然、気づくのである。
石浦はジョンが「ヘルプ!」を歌ったアルバム『4人はアイドル』の中で、ポールが「イエスタデイ」を歌っていることに注目する。
♪
イエスタデイ
悩みなどはるか彼方と思えたが
今や苦はここにいついたのか
ああ、まだ昨日という日を信じている
♪
ポールが歌った孤独は、彼女が去っていってしまったことによる寂しさである。
インディペンデンス=自立することとは、ひとりで立つことであり、何物にも頼らないことだが、それはそう簡単なことではない。
普通、大人になるということは、新たに「会社」やその他に帰属することで、新たなる安定を求めることに過ぎない。
今日という孤独を「ヘルプ!」と歌ったジョンが、15年後には人生を駆け抜けていってしまう。
昨日を偲んだポールは、まだ現役を続けている。
そんな対照的な人生があるのだと、石浦は指摘していたのだった。
いつかは昔話に花を咲かせたいと思っていたという北山は、ポールに通じるところがある。
ひたすら前に前にと進んで倒れた加藤の生き方は、ジョンに近いと思える。
2009年10月19日日に朝日新聞に掲載された北山の追悼文、「加藤和彦さんを悼む すべて一流のプレーヤー」はこんなふうに始まっていた。
彼は「振り返る」のが大嫌いだったが、大した戦績だったので、嫌われるのを承知で書こう。私は、一時期同じバンドのメンバーにして、楽曲を作る仲間、そして人生の良きライバルだった。それで故人を呼び捨てにするが、お許し頂きたい。今から数十年前のこと、その加藤がこう言ったことがある。
「お前は目の前のものを適当に食べるけど、僕は世界で一番おいしいケーキがあるなら、全財産はたいてもどこへだって飛んでいく」
趣味は一流、生き方も一流だった。ギタープレーヤーとしても一流で、プレーヤーすなわち「遊び事」としても一流。グルメであり、ワインに詳しく、ソムリエの資格をとるほどで、何をやらしても天才の名に個するレベルだった。
それがゆえに、凡百とのおつきあいの世界は、実に生きにくいものだっただろう。しかし私たちには、そんな背の高い天才の肩の上に乗ったら、見たことない景色が遥か遠くまで見えた。
加藤和彦が日本の音楽にもたらしたもの、それは「革命」だった。作品だけではなく、彼の生き方ややり方が新しかった。、六〇年代、若者の革命が幾つも夢想される中ほとんど何も持たない若いプレーヤーたちが芸能界のエスタブリッシュメントに挑んだのだ。はっきり言って、私たちは、アマチュアで、関西にいて、大した機会に恵まれなかった。そして振り返るなら、多くの「若者の戦い」の中で、あの音楽の戦いだけは一瞬成功したかに見えたし、クリエーター加藤和彦は、このプレーヤーたちの戦いの旗手となった。
わずかに300枚だけ作られ自主制作のアルバムのなかに入っていたザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」が、メジャーのレコード会社から発売されて半年で280万枚も売れた。
そんな1967年から68年にかけて、日本の音楽シーンの様相は大きく様変わりし始めていた。
レコード会社やプロダクションのあり方が、根底から揺らいで変革を余儀なくさせられた。
興行システムと音楽制作の流れも大きく変わって、学生たちがアマチュアのままそこに参加してきたのだ。
それまでのレコード会社が専属作家として抱える先生が作る楽曲を、歌手が歌わせてもらうという「上から下」の流れに対して、アマチュアの自作自演による「下から上」という、いわば下克上の波が音を立てて流れ込んだのである。
若くて新しい作家やプロモーターが活躍することによって、シンガー・ソングライターがブームになった。
そこに颯爽と登場してきた加藤は1970年代になると、サディスティック・ミカ・バンドを結成し、世界の音楽シーンとシンクロしながら時代の牽引者となっていく。
また吉田拓郎や泉谷しげるのプロデュースを手がけて、日本におけるプロデューサーの仕事を開拓しながらパイオニアとして活躍した。
「へルプ!」という声を叫ばなかった生き方、加藤の戦いぶりについて北山はこう書いていた。
後ろは振り返らない、そして同じことは絶対にやらないというモットーを貫き通した彼は、おいしいケーキを食べるために全財産をはたいて、また手の届かぬところに飛んで行った。戦友としては、その前だけを見る戦いぶりに拍手を贈りたい。しかし、昔話に花を咲かせ共に老後を過ごすことを楽しみにしていた仲間として、そしてこれを食い止めねばならなかった医師として、友人としては、実に無念である。
そして今、北山はミュージシャンもしくはアーティストが現代人を映す鏡だとして、精神科医の立場からこう警鐘を鳴らしている。
ミュージシャンにときどき起こっている悲劇は、現代人の悲劇なのでね。だから、手応えをくれる他人、返信をくれる他人、目の届くところにいる人たちのことを大事にして生きるっていうのを、私も心掛けていきたいなと思う。(注)
ポール・マッカートニーの「イエスタデイ」のように、”昨日という日を信じ”ることで悲劇を乗り越えていく。
そのときは加藤と北山が作った「あの素晴しい愛をもう一度」が、BGMとしてやさしく響きわたってくるのかもしれない。
(注)この発言は、平山 雄一(著)「なぜ日本の音楽はマーケティングを誤ったのか 弱虫のロック論2」(KADOKAWA)からの引用です。
<加藤和彦に関するコラムはこちらお読みいただけます>
・ザ・フォーク・クルセダーズの「イムジン河」は国境を越え、時間を超えて日本人の歌になった
・「イムジン河」のかわりに加藤和彦が作った「悲しくてやりきれない」の奥深さ
・吉田拓郎が”音楽の師匠”と呼ぶ加藤和彦との出会いから生まれたヒット曲
・1970年に北米を回った加藤和彦から生まれた「あの素晴しい愛をもう一度」
・イギリスでも注目されていた日本のロック、サディスティック・ミカ・バンドの全英ツアーが始まった
・加藤和彦との結婚、そしてサディスティック・ミカ・バンドの誕生
・フォークルに発見されて新たな生命を吹き込まれた寺山修司の「戦争は知らない」
・フランスに生まれた反戦歌をフォークル時代から歌い継いできた加藤和彦