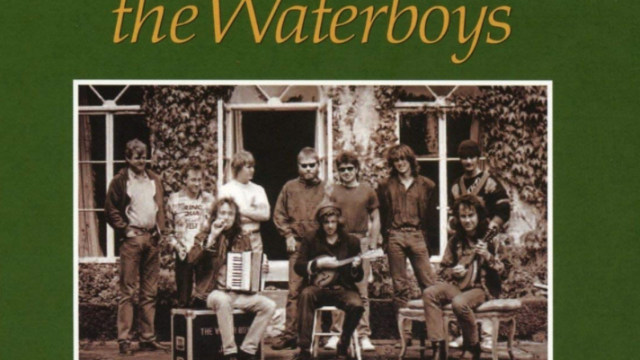2014年のフジ・ロック・フェスティバルでザ・ウォーターボーイズとして初来日を果たし、翌年4月に単独来日公演も実現。続いて2016年にはご存知の通り、アーティストのろくでなし子こと五十嵐恵と結婚し、デビューから30年以上を経て日本との距離を急激に縮めているマイク・スコット。その最新作は、昨年9月に登場したキャリア初のダブル・アルバム『アウト・オブ・オール・ディス・ブルー』だ。
長年の相棒であるスティーヴ・ウィッカム(フィドル)やマッスル・ショールズのベテランであるデヴィッド・フッド(ベース)、或いは、サザンロックに根差したミュージシャン集団スペイスボムのトレイ・ポラード(ブラス及びストリングスのアレンジ)といった技巧派プレイヤーの参加を得て、活動拠点のダブリンと東京でレコーディングされた同作には、計23曲を収録。
アナログの2枚組を想定したそうで、テーマに沿ってラフに4つのセクションに分けられている。サイド1にはラヴソング、サイド2とサイド3には場所や人物に因んだ曲を収め、中でもサイド3で目を向けているのはミュージシャンたち。そしてサイド4は妻との関係にフォーカスしており、日本を舞台にした曲が並んでいるのは、当然の成り行きと言うべきか?
以上の多彩なストーリーの数々をマイクは、非常にメロディックで馴染みやすい曲に仕立て上げた。しかも、ループされたビートやサンプルといったヒップホップ的なテクニックを用いて実験を行ない、グルーヴ感のあるソウル・ポップ・サウンドで新境地を開拓。ひたすら音楽に手を引かれるままに歩むノマド的な生き方がまたもや、大きな収穫をもたらした形だ。そんな彼を、休暇で訪れていた東京で取材する機会を得た。

──あなたのキャリアを振り返ってみると、いわゆる”ビッグ・ミュージック”期に始まり、ケルト期、スピリチャル期……といった具合に大まかに区分けできるような気がするのですが、ここにきて新たに、アメリカに目を向けているようですね。
確かに前作『モダン・ブルース』(2015年)には間違いなくアメリカンな趣があった。ナッシュヴィルでレコーディングした作品だし、あの時の僕は、サザン・ソウル/ロックぽいフィーリングを求めていたからね。その点、最新作はそこまでアメリカンじゃないが、ソウルやファンクに根差したアルバムではあるよ。
──その出発点は、2012年にニューヨークで耳にした、カーティス・メイフィールドのアルバム『Roots』(1971年)だったとか。
うん、つまり前作に着手する前の話だよ。ファンクのリズムとストリングスの絶妙なコンビネーション、そしてアルバムを貫く理想主義みたいなものにすごく惹かれて、あの作品が言わば、種を蒔いたわけだ。中でも特に『We Got To Have Peace』という曲の雰囲気が心から離れなくて、ずっと片隅にしまってあったんだよ。
──しかも最終的にはダブル・アルバムが完成。ここ数年は創作欲が漲っていたと考えて良さそうですね。
ああ。アメリカをツアーすると、いつもたくさんのインスピレーションをもらえるんだけど、今回も例外じゃなかった。英国からやってきた一介のミュージシャンとして、ナッシュヴィルやデトロイトやシカゴやニューヨークは、偉大な音楽を生んだ憧れの町であり、訪れるたびに刺激が得られる。そこに身を置いているだけで、自分の中にインスピレーションが湧き出るのを実感できるし、「この分だと曲が迸り出るように生まれるだろうな」と予感がした。それで「ダブル・アルバムを作ってやろう」と決めたのさ。
本格的にソングライティングを始めたのが、2015年の夏だったかな、一旦書き始めると1日に1曲のペースで書き上がった。10代の頃以来のハイペースで、自分でも驚いたよ。しかもティーンエイジャーの僕が書いた曲より、当然ながら、遥かに出来のいい曲ばかりだ(笑)。
そして今回は、書きながらどんどんレコーディングしていったんだ。自宅でもコンピューターさえあれば作業はできるからね。そもそも僕はデモを作るのが好きじゃなくて、閃いたらすぐに一発で録音したい。実は今作は、ほとんど独りで仕上げたアルバムなんだよ。ピアノを弾いたりドラムループを使って形作り、あとでバンドのメンバーや他のミュージシャンの参加を得て肉付けをした。ヴォーカルは最初に自宅で録音したものを使っている場合が多いよ。
──今ドラムループの話が出ましたが、プロダクション面でループやサンプルなどヒップホップ的手法を多用するに至った経緯を教えて下さい。
僕のバンドのギタリストであるザック・アーンストの影響で、ヒップホップに開眼したんだよ。彼はテキサス出身のアメリカ人で、ヒップホップ・マニアなんだ。で、ケンドリック・ラマーからJ・ディラまで様々なヒップホップ・アーティストの作品を聴かせてくれて、すっかりハマってしまったのさ。そういった作品の中に、最近のロックに欠けていると思う、旺盛な冒険欲を感じ取った。
というのも僕は、ザ・ブラック・キーズやアークティック・モンキーズなんかもちゃんと聴いているし、作品の質は総じて高い。でもザ・ブラック・キーズの場合はブルースをアップデートしたものだし、昔のロックの影響をみんな強く受けているよね。だから「これは新しい!」と飛びつくようなものがない。そんな時にケンドリックを聴いたんだ。
彼の曲は人間のイマジネーションを刺激する短編映画のようで、同時に、パンクや初代のインディロックのDIY精神を思い起こさせた。或いは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、サイケデリック期のザ・ビートルズにも通ずる部分があるのかな。バリアと呼べるものが見当たらなくて、何をやってもいいというフリーダムがある。ああいう精神が恋しかったんだ。それに彼は、様々なフィールド・レコーディング音源を挿入して、曲のシーンをさっと塗り替えたりするよね。あれも大好きで、早速『New York I Love You』で取り入れてみたよ。
──ほかにも、足掛け2年にわたる制作期間に多くの音楽関連の書籍を読んだことがインスピレーションを与えてくれたそうですが、例えばどんな本を読んだんですか?
僕は基本的に読書が好きで、今はふたり子供がいるから時間の確保が難しいんだが、週に3~4冊は読む。で、自分が音楽関連の本をやたら読んでいることに気付いて、だったら集中して読もうと思ったのさ。まずマーヴィン・ゲイを筆頭に伝記本をたくさん読んだよ。60~70年代に活躍した音楽ジャーナリストのリチャード・ゴールドスティーンの回顧録(注『Another Little Piece of My Heart』だと思われる)が特に面白かったし、ほかにも英国のパンクシーンに関する本、スタックス・レーベルに関する本があったな。
そうそう、モータウンのシングルを解説する本は素晴らしかった(注:『Tamla Motown:The Stories Behind the UK Singles』だと思われる)。各曲が生まれた経緯やレコーディングのプロセスが詳細に調べられていたよ。とにかくこういった書籍を読み続けることで、自分を常にインスパイアされた状態に置いて、アーティストたちの功績を思い知らされながら、高い理想を追うことができたよ。
──そういえば、中盤にはキース・リチャーズに捧げた『Mister Charisma』や、ザ・フーのジョン・エントウィッスルにまつわる逸話に根差しているという『The Hammerhead Bar』など、黄金期のロックの神話を題材にした曲もあります。
60~70年代のロックに僕はすごく興味があるんだ。というのも欧米ではあの時代に、カルチャーにおける様々な制約が消えたんだよ。確固としたブラック・カルチャーが誕生し、エルヴィス・プレスリーによって肉体にまつわるタブーが解かれ、ボブ・ディランによって心が解放され、ザ・ビートルズによって精神が解放された。
従って、あの大変革の時代を実際に生きたキースみたいな人たち……いや、正確には彼ら自身がその変革をもたらしたわけだけど、やっぱりインスパイアされずにいられないよ。彼らは抑圧的で体制順応型の社会で子供時代を過ごし、それを拒絶したんだ。もちろんパーフェクトな時代だったとは言わないし、みんな多くの過ちを犯した。でもあの時代に得た教訓は今の社会にも活かされている。”個人の自由”という考え方も、60年代に確立されたことだからね。
──一方の終盤は、奥さまに向けたこの上なく率直なラヴソングが並んでいます。哀しみや苦しみについて書くほうが簡単だというソングライターもいますが、あなたの場合はいかがですか?
悲しみだろうと喜びだろうと、あらゆるエモーションがインスピレーションになるし、僕は悲しみに特に強く反応するタイプじゃない。それに今回のアルバムも、序盤はどちらかというと悲しい曲が多いよね。『The Girl In The Window Chair』然り、『Morning Came Too Soon』然り。これらも僕の実体験に基づいていて、終盤は対照的に喜びで満たされ、ハッピーエンディングに至る。それは意図したんじゃなくて、ほかの曲を書いたあとで妻と出会ったから、時系列に沿っているというだけなんだけどね。
──ちなみに『アウト・オブ・オール・ディス・ブルー』というタイトルは、”ブルーな気分からの脱却”というニュアンスとも捉えられますが、完成までに苦難があったんでしょうか?
いいや、ちょっと誤解を招きやすいタイトルなんだよ(笑)。純粋にこのフレーズの響きがすごく気に入っていたし、僕にはタイトルとしてしっくり感じられたというだけだ。元々そういうタイトルの曲があったんだけど、アルバムには収めなかったのさ。今思うと、別のタイトルを選ぶべきだったかもしれないね。実は『Musk』という候補もあったんだ。ラヴソングが多いからからムスクの香りが似合うかなと思って。
──それにしても、今回のファンクやヒップホップの実験然りで、あなたは一貫してスタイルに捉われることなく、毎回音楽に主導権を委ねているところがありますよね。
ああ。自分でも次にどこに向かうのか分からないことがあるよ(笑)。だから次の方向性が見えてくるまで、しばし様子を見ているような時期もあったな。振り返ると、明らかに音楽的インスピレーションを欠いていて、とりあえず曲は書いているから発表するか――みたいなノリの作品がある。『Still Burning』(1997年)や『Book of Lightning』(2007年)がそうだね。
そういう時でもアルバムを作り続けるべきだと思うんだが、幸運にも僕の場合、たいてい何か新しい刺激と出会って、次のゴールを見つけることができる。そういう意味で00年代の作品、『An Appointment With Mr Yeats』(2011年)と『モダン・ブルース』と最新作は、いずれも非常に豊かなインスピレーションに後押しされて生まれたアルバムだね。
──同時に、そういうスタンスが息の長いキャリアをもたらした、とも言えますよね。
そう思うよ。これは僕個人の体験であり、ほかの人にも適用できるのか分からないけど、人にこう訊かれることがあるんだ、「よくダブル・アルバムなんか作れるね」とか「なぜいつも立ち止まらずに前に進むことができるんだい?」と。でもそれは僕にとって全く難しいことじゃない。音楽が指し示す通りに行動しているだけで、音楽に「ストップ」と言われたら立ち止まる。
今のところ音楽は、「立ち止まるな」と僕に呼びかけている。音楽とのコネクションが一度も断たれたことがないんだ。アーティストの中には、音楽ではなく名声やお金の声に耳を傾けたがために、音楽とのコネクションを失った人もいるよね。そして、それを取り戻すのに何年もかかったり、或いは二度と取り戻せなかったりもする。そういう意味では、僕はすごく恵まれたキャリアを歩んできたと思うよ。
(インタビュー協力/Hostess Entertainment)
The Waterboys/ウォーターボーイズ
1983年結成、英国エジンバラ出身のマイク・スコットを中心としたUKロック・バンド。ケルティック・フォーク、アイルランド伝統音楽、プログレ、カントリー、ゴスペルなどの影響を受けている。バンド名はルー・リードの曲の歌詞から名付けられる。初期はNYパンクの影響を受けたニューウェーブバンドとしてスタートし、U2フォロワー的な扱われ方もされていた。2014年にフジロックで初来日を果たし、2015年1月に約4年ぶりとなるニュー・アルバム『モダン・ブルース』をリリース。同年4月には渋谷クアトロにて来日公演を行なった。翌年、マイク・スコットは”ろくでなし子”こと日本の漫画家、五十嵐恵と結婚/出産を経験。そして2017年9月、2年半振りの新作『アウト・オブ・オール・ディス・ブルー』をリリースした。
詳しくはこちら