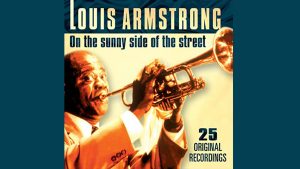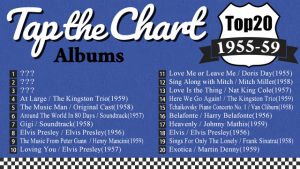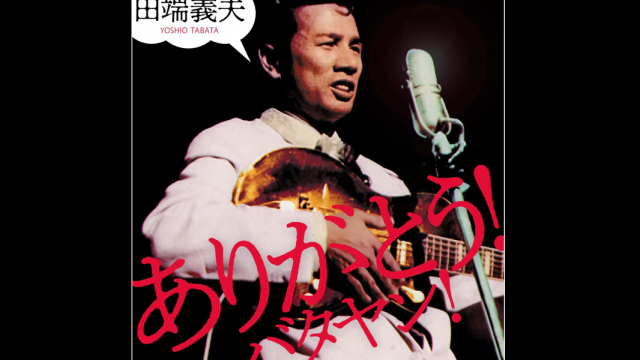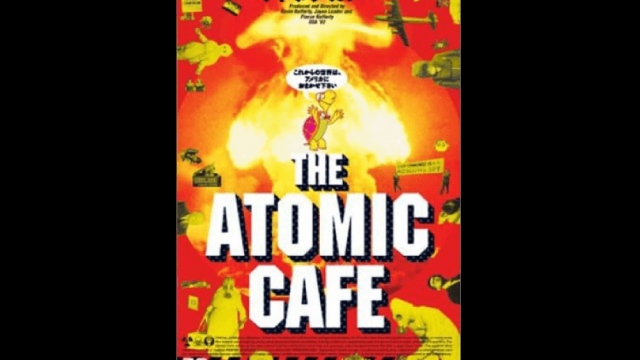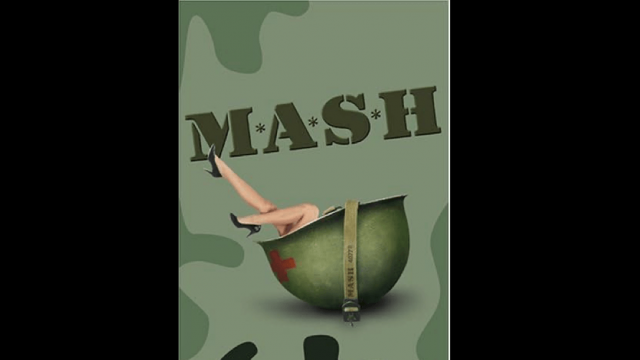ポップスといえば、スウイング・ジャズだった1940年代。「ダンス・ホール」全盛の時代で、女性ボーカリストとビッグ・バンドが組むスタイルが定番だった。
1940年、レス・ブラウン楽団のリード・ボーカルとなったのがドリス・デイ。少女歌手からキャリアをつみ、1940年、専属歌手となったとき、まだ18歳という若さだった。
1944年に、レス・ブラウンが自分で書いた曲を、ドリス・デイに歌わせてみたのが「センチメンタル・ジャーニー」。
“長い旅路の果て、わが家に帰る”という地味な歌詞だったが、ダンス・ホールで演奏してみると、思いがけぬことが起きた。
ドリス・デイがこの曲を歌い出すと、ダンスに興じていた男女の客たちのステップがピタリととまる。客たちはダンスを忘れて、ドリス・デイを囲んで曲に聞きいったのだ。
この曲は間違いなくあたる。その光景を見て、レス・ブラウンは、即座にレコーディングを決めたという。
この歌詞にはキーワードがひとつ隠されていた。
わくわくしている子供みたいな気持ちで
「出発進行」の声が聞こえるのを待ち望んで
「出発進行!」
列車の汽笛。言葉よりなにより、世界が最も望んでいたのはその合図だった。
1944年なかばという時代をひもとけば、事情がよくわかる。第二次世界大戦も開戦から6年。世界の戦地に送られた兵士たちの厭戦気分は頂点にたっしていた。今年のクリスマスまでには・・と帰還を願う兵隊たちと待ち続ける家族たちの忍耐力も限界にきていたのだ。
兵士たちが抱く望郷の一心をあつめ、1945年、「センチメンタル・ジャーニー」は発売とともに、たちまち爆発的ヒットとなる。そして、この曲は、「Hits of World WarⅡ」(第二次世界大戦の歌)とまで呼ばれるようになる。
一曲のダンス・ナンバーが、世界を揺り動かしたのだ。
進駐軍とともに日本にもやってきたこの曲は、東京の空の下、たえまなく流れ続けた。
リクエストを受け、日がな夜がな、この曲を流した放送局は、1945年に開局された進駐軍向けの放送局「WVTR」、「FEN」の前身で、日本人にも聴くことができた。
日本に進駐してきた米国の軍隊は、兵役を解かれ、「センチメンタル・ジャーニー」に送られて、日本からそれぞれの故郷に帰還していった。
だが、その兵士たちと入れ替わる形で、日本に第二陣のアメリカ軍が送りこまれていたことを知る人は少ない。
アメリカを代表するノンフィクション作家、デヴィット・ハルバースタムが、朝鮮戦争を描いた「コールデスト・ウインター」(1972年刊)であきらかにしたところによれば、第2陣の米軍とは、主に戦後日本の文民統治を目的とし、冷戦下、日本に軍事的空白をつくらないため、米軍のプレゼンスを保証するものとされ、兵士たちもそう聞かされてきた。
ところが、1950年6月25日、思いもよらないことが起きる。
朝鮮戦争の勃発である。
朝鮮半島に最も近い国にいたこと、また緊急を要することから、日本に駐留していた米軍兵士たちが、韓国軍支援のために、その戦場に投入されたのだ。
むろん兵士たちにとっては、寝耳に水の出来事だった。
こうして、実戦体験もとぼしい新参の兵隊たちは、予想もしなかった激戦地に投入され、おびただしい死者の数を重ねた。
「これまで日本は、韓国のようにベトナム戦争にひきずりこまれることなく、イラクやアフガニスタンでの戦闘にも直接かかわらずにすんだ。憲法の制約がなければ、アメリカが介入したこうした戦争に直接まきこまれていたことだろう」
日本の敗戦を描いた「敗北を抱きしめて」の著者である、ジョン・ダワー氏(マサチューセッツ工科大名誉教授。)は、「朝日新聞」のインタビューでこう語っている。
「集団的自衛権」をめぐる論議を見るにつけ、ふと思いをはせるのは、兵隊ひとりひとりの命のあまりの軽さである。
その姿は、直立不動のまま、運命の奔流になすがままにおしながされる「錫の兵隊」(アンデルセン)を思わせる。
もの言えぬ「錫の兵隊」たちを、危険な戦地に立たせてはならない。