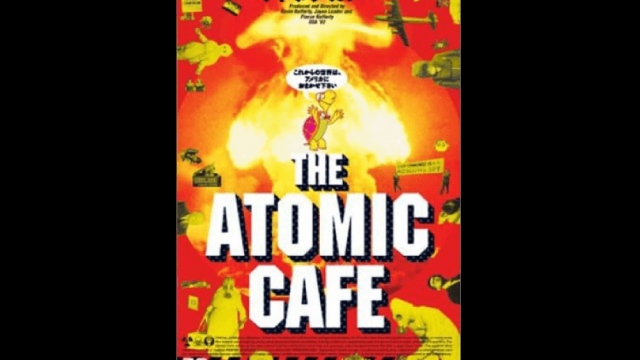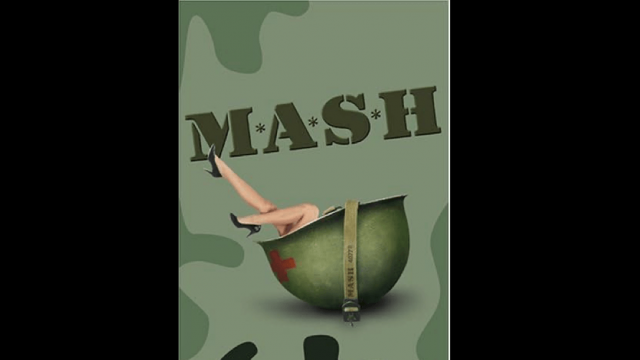実は「古事記」の中にもあったのである。「古事記」は、日本で最初に完成した文学作品といわれ、その時代を生きた人々が使っていた日本語で書かれていて、原典は解読することができない。それが池澤夏樹さんの個人編集、「日本文学全集」の第一巻として編まれることによって、誰にでも読めるようになった。
どこか読みすごしていた物語をたどるうち、ふと手がとまったのは、イザナキとイザナミのエピソード。
「古事記」の前半、イザナキは、妻に会おうと死者の国である黄泉国(よみの国)まで追いかけてゆくのだが、「私を見ないで」という妻との約束を破ってしまう。
このプロットにはどこか覚えがある。
それがなにゆえあって、はるか遠い東洋の島国である日本に・・と思ううち、記憶はたちまちワープして、昔に観た一本の映画へ。
見るな、ふりむくな。そう禁じられても破ってしまう普遍のタブー。
これはそっくり、映画「黒いオルフェ」(1959年フランス)のストーリーそのものではないか。
この映画の原案となっている「オルフェウスとエウリディーチェ」の古さは別格。ギリシャ神話だからである。
神話では、アポロンの息子である、見目美しい竪琴の名手オルフェウスが黄泉の国から妻、エウリディーチェを連れ戻す時、「決して後ろをふり返ってはいけない。」と言われていたのに、ふり返ってしまい、その瞬間、エウリディーチェは死者の国へ再び堕ちていくという悲劇。
まけずおとらず広く知られているのは、聖書に出てくる「ロトの妻の塩柱」だろうか。
悪の都市、ソドムとゴモラから夫妻で脱出をはかるとき、固く禁じられながらも、ふりかえってしまったロトの妻は、あっというまにその身を「塩の柱」に変えられてしまう。この出典は旧約聖書」で、創世記19章に出てくる。
映画「黒いオルフェ」に話を戻すなら、この作品の成功(1959年、カンヌ映画祭でグランプリ受賞)は翻案のダイナミクスにある。
監督、マルセル・カミユは、ギリシャ神話の荘重な舞台を、カーニバル前日の喧噪と熱狂のリオデジャネイロにとってかえてしまう。キャストは、褐色の若者たちで固め、強烈な原色画像と炸裂するサンバ。
なにしろ、主人公オルフェは、竪琴ならぬギターを、質屋に入れてしまう文無しの市電の運転手。底抜けに明るい青年には、演技体験ひとつない地元のサッカー選手、ブレノ・メロが起用された。
一方、恋人ユーリディスは、村から出てきたばかりの田舎娘。
ふたりは固く結ばれるが、ユーリディスが先に命をおとし、なきがらをかき抱く悲嘆のオルフェもろとも高い断崖をころげ落ちてゆく。
~悲しみは果てしなく、幸せははかない。
幸せは一枚の羽根。風にとって飛んでいってしまう~
そこに流れる「カーニバルの朝」、「フェリシダージ(悲しみよ、さようなら)」などの主題曲は世界的なロングセラーとなった。
そして、カーニバルの翌朝。オルフェのギターと歌は、子供たちに引き継がれ、その調べにのって、真っ赤な太陽が昇ってゆく。
音楽のすべてを仕切ったのは、ボサノヴァの生みの親として知られるアントニオ・カルロス・ジョビンとルイス・ボンファ。
ボサノヴァは、この映画によって世界的に火がついたといっても過言ではない。
ところで、「ふりむくな、見てはならない」のタブーはなぜこれほど広く語りつがれてきたのか?
神さまからみれば、人間とは自分との誓いすら守れないどうしようもないものであり、人間のサイドから見るなら、「妬む神」という形容(旧約聖書、出エジプト)があるように、神とはひたすら嫉妬深く、自分以外の教えに気を動かす者を決して許さないわがままな存在。
そのせめぎあいのなかに、答えは探すことができるのだろうか?
(このコラムは2015年2月27日に公開されたものに加筆訂正したものです)
フェリシダージ
黒いオルフェ