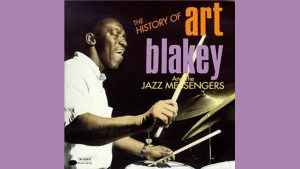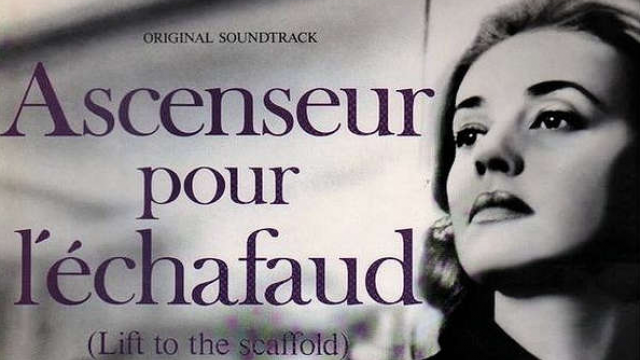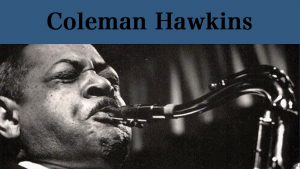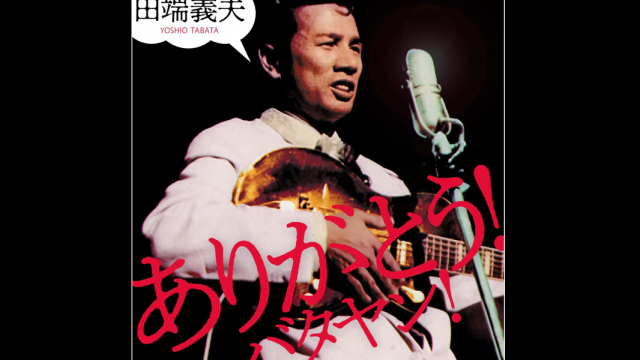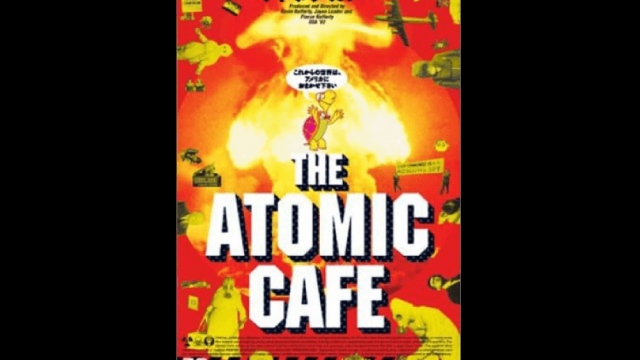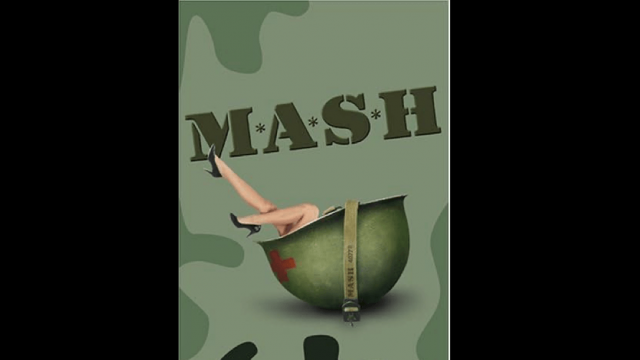ヌーベル・バーグとは、1950年代末から1960年代中盤にかけて、フランスで起きたムーブメントだが、その功績は、映画を志す若者たちに道を拓いたことにあった。
どんなに才能があっても、著名監督の下で修業を積まなければならなかった徒弟制度から解放され、思い通りの作品を撮れるようになった。
1959年、31歳で映画『危険な関係』を世に出したロジェ・バディムも、そんな時代の寵児のひとりだった。ビート・ジェネレーションとクロスする世代らしく、その感性は鋭角的なひらめきに満ちていた。
題材としたのは、閉塞の時代と呼ばれながらも、マルキド・サド、ブルトンヌなど多くのアンチ・モラルの作家を生んだ18世紀末。
その時代、サドとならび称されるコデルロス・ド・ラクロによって書かれた書簡小説を原作に、主役に、フランス映画界きっての演技派、ジェラール・フィリップとジャンヌ・モローという顔ぶれを配し、現代のパリに時代を移して、上流社会の退廃を辛辣に描き出すという作品。
斬新な映像美など多くの魅力があげられるが、この作品に強烈なドライブをかけたのは、まぎれもなくジャズだった。
アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズのリー・モーガンによる高らかにつんざくトランペットなくして、この作品の魅力を語ることはできない。
バディムは、この映画に「ビ・バップの高僧」という異名をとったジャズ・ピアノの最高峰、セロニアス・モンクを音楽担当に起用。さらに当時フランスで爆発的な人気を集めていたアート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズをサウンド・トラックに登場させる。
アート・ブレイキーは、1940年代から、マイルス・デイビス、セロニアス・モンクや、チャーリー・パーカーとのセッションで頭角をあらわした名ドラマーだが、1954年にジャズ・メッセンジャーズを結成。そのもとからはホレス・シルバー、クリフォード・ブラウンなど、有数のミュージシャンを巣立せている。
日本にも数多く訪れ、「危険な関係のブルース」は、日本におけるモダンジャズ・ブームのきっかけとなったといわれている。
バディムとジャズとの関係は、「大運河」(1957年)にさかのぼる。この映画はベネチアの運河を背景としたサスペンス・ドラマで、「街の灯」でジャン・ギャバンの相手役に抜擢された女優フランソワーズ・アルヌールの出世作となったことでも話題をよんだ。
「大運河」に、バディムが起用したのは、モダンジャズ・クワルテット、「MJQ」の名で親しまれてきたグループで、ジョン・ルイス、ミルト・ジャクソン、パーシー・ヒース、ケニー・クラークの四人組。モダン・ジャズとしてはめずらしく、演奏の時は必ずタキシード着用というスタイリッシュな姿勢を崩さず、クラシックと組んでも遜色のない洗練された演奏で知られていた。この映画のサントラからは、「ゴールデン・ストライカー」や「葬列」がヒット曲となっている。
映画とジャズ。今となってはあたりまえすぎるくらいだが、さきがけとなったのは、「大運河」だった。
一方、ルイ・マル監督は、マイルス・デイビスと組んで「死刑台のエレベーター」(1957年)を完成させていた。このサスペンス映画で、主人公の心理をスリリングに描きだすために、マイルスは、実際にラッシュの映像を見ながら即興で吹いたというエピソードが残っている。
ジャズとフランスは、相性がよかった。フランスにとって、ジャズ・ミュージックとは洗練の極みであり、ジャズ・メンたちも、演奏家としてはじめから敬意をもってうけとめられた。
「ジャズの芸術性を最初に認めたのは、アメリカではなく、フランスだった」
という皮肉な見方さえある。ブラックもホワイトもない国に高く評価されたことで、この時期実際に多くの黒人ミュージシャンたちがフランスに渡ったといわれている。
その後も、ジャズ・メッセンジャーズと組んだエドゥアール・モリネロ監督の「殺られる」(1959年)などジャズを使った作品が競うように作られるなか、「シネ・ジャズ」という言葉が生まれるほど流行は続いた。
当時最高水準にあってジャズは、映画をヒットさせる「飛び道具」の役割を果たしたのである。
最後に、シネ・ジャズ以前の1955年に作られていた傑出したジャズ映画について、ふれておきたい。
これはフランスではなく、アメリカの作品「黄金の腕」。
監督はオットー・プレミンジャー。フランク・シナトラが、麻薬中毒の賭博師役を名演、アカデミー主演男優賞にノミネートされた作品で、エルマー・バーンスタインを音楽監督に、ショーティ・ロジャース、シェリーマン、ピート・カンドリなどが演奏に参加している。
公開当時、劇場で見る機会に恵まれたのだが、いまだに記憶が去らないのが、タイトル・バック。ショーティ・ロジャースのフリューゲル・ホーンの響きにのってロゴが躍動するタイトル・バック。
記憶に残るタイトル・バックも少なくないが、後のち語り草にまでなった例はめずらしい。当時は知るよしもなかったが、デザインを手掛けたのは、アメリカン・アートを代表するグラフィック・デザイナーのソール・バスだった。