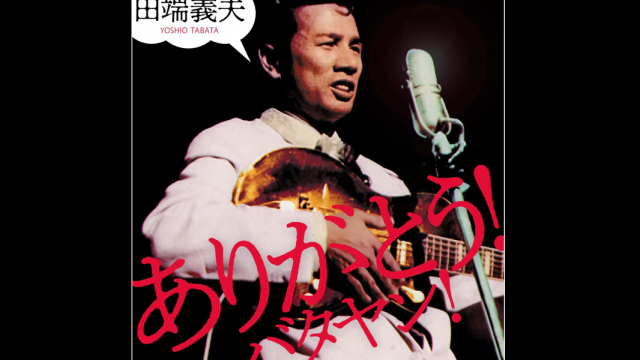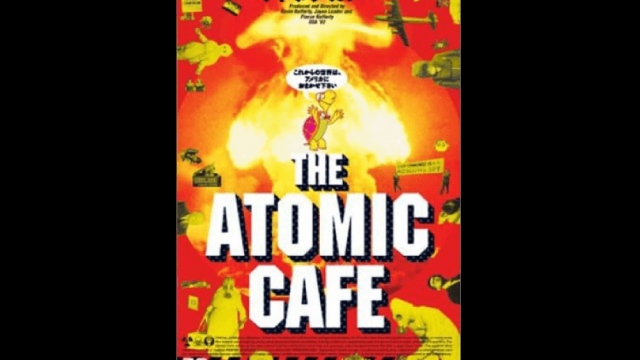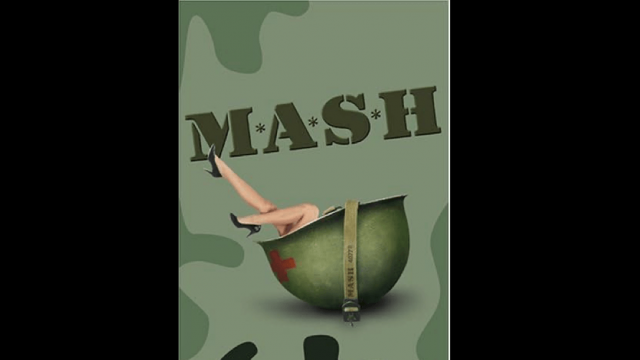Ray-Banの売り場から、「Shooter」というモデルだけが根こそぎに消えた。
日野皓正がさりげなく鼻にのせていたからである。
ジャズ・メンが、ファッション誌に登場することなどこれまでなかった。
贅肉ひとつない引き締まったボディ。軽いフットワーク。身を弓なりにそりかえし、空に向かって一気に吹きあげるパフォーマンス。
日野皓正は最初からスタアとして登場した。
だがその資質は、一夜にして身についたものではない。
1955年頃、米軍キャンプで、「日野ブラザース」という名のタップダンスとトランペットの兄弟バンドが名を上げる。
兄、皓正、弟、元彦。13歳と9歳。ふたりは、父のトラ(エキストラの意)としてステージに立った。
父、日野敏は、かつて日劇で鳴らしたタップ・ダンサーでトランぺッター。
彼が少年たちに課したのは、登下校前30分のレッスン。彼らは忠実にノルマを守った。すでに家計を支えていたからである。
当時、一枚のプリントにおさまった日野は、空き缶にセメントをつめたダンベルで鍛えた見事な逆三角形をしている。
窓を開け放しで吹くものだから苦情が出る。やって来た警察官を、「バカヤロー!こっちは商売でやってんだ!」と、父は追い返した。
「革ベルトで叩かれるんだけど、たまにバックルの方がとんでくる。まるでサーカス団の団長」。日野はそう言って笑った。
遠かったジャズへの道
敗戦の名残りから、ポピュラー音楽一般を「ジャズ」と呼んでいた時代もあったこの日本に、モダン・ジャズが入ってくるのは、1960年代、アート・ブレイキ―とジャズ・メッセンジャーズの来日公演以来のことだった。
熱心なファンが支えた「ジャズ喫茶」でも、50年代には、日本人のジャズは、ターンテーブルに載せられることはなかった。
そんな環境のなかで、日野皓正が出会ったのは、若いながら、日本のジャズを牽引してきたジャズ・ピアニストの菊地雅章。
日野は彼と組んで、「日野=菊地クインテッド」を結成、「日野皓正コンサート」「ハイノロジー」「ライブ」「タローズ・ムード」などのアルバムを発表、なかでも、「ハイノロジー」は3万枚の大ヒットを記録する。
71年には、「ベルリン・ジャズ・フェスティバル」に出演、海外進出へのステップとする。
大手酒造メーカーのCFをきっかけとした「ヒノテル・ブーム」にのって、日野は、これまでジャズ・メンができなかったことに次々挑戦してゆく。
1970年公開の映画「白昼の襲撃」もそのひとつだった。
この映画で日野が組んだのは監督の西村潔。
西村はこれまでに、「野獣死すべし」で黛敏郎。「豹(ジャガー)は走った」では、佐藤允彦。伝説の名作、「ヘアピン・サーカス」では、菊地雅章と組んで映画とジャズを巧みに融合させるなど、東宝で異色のアクション監督の誕生と嘱望されていた。
この作品のために、日野皓正は音楽監督をつとめ、主題歌「スネイク・ヒップ」を書き下す。ブームも手伝って、この作品はめずらしくサントラ盤が発売され、異例の大ヒットを記録する。
「経済的にはひと息ついたが、ぼくはジャズの魂を売っているんだと思った」
1975年、日野は日本での安住を望まず、軸足をアメリカに移す決断を下す。
一家を引き連れ、ニューヨークに移住。
「優秀な黒人がいるのに、なんでイエローなんかを使うんだ?」そんな声も承知の上、毎夜「ジャズ・クラブ」で日銭を稼いで暮らす茨の道を日野は選んだ。
1989年には、日本人として初めて「ブルーノート・レコード」と契約、日本のジャズの水準を立証してみせた。
不屈のスピリットは、少年時代から少しも変わることはない。
(後日談であるが、「白昼の襲撃」を撮った西村潔は、1993年、葉山の海岸で、不慮の死を遂げ、今は幻の天才監督として、名を残すばかりだ)