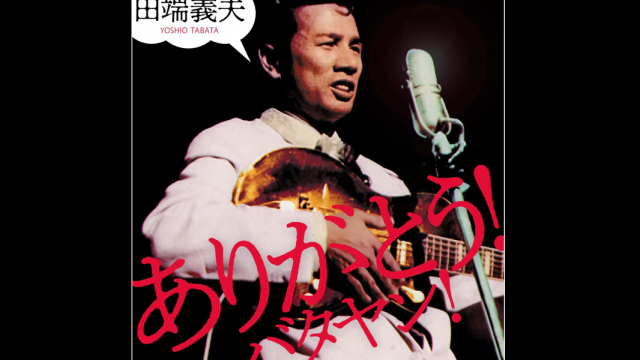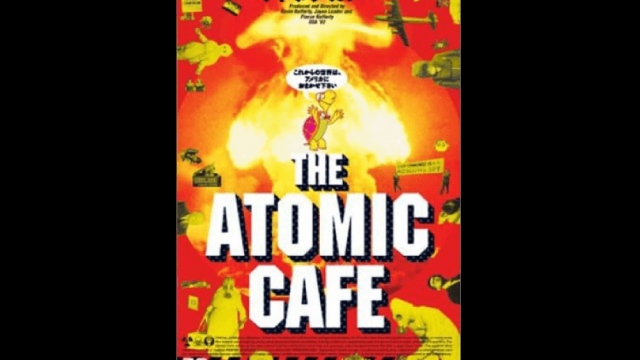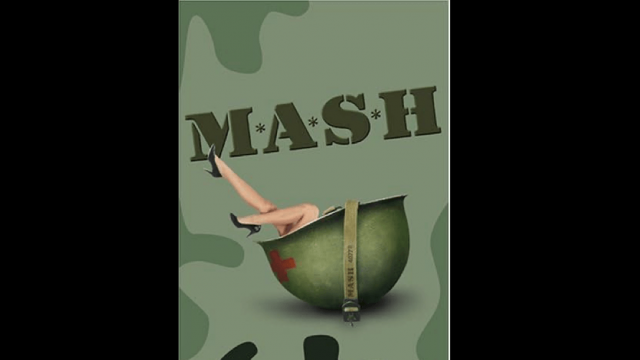「第三の男」は、第二次大戦終結4年後の1949年に制作され、同年カンヌ国際映画祭で、グランプリを獲得。「映画史上最高傑作」と讃えられる英国映画。監督はキャロル・リード、原作は、英国作家のグレアム・グリーンである。
グレアム・グリーンは、この作品は、「読んでもらうためではなく、見てもらうために書いた」と言っているように、まずは映画ありきの作品だった。
ウイーンはオーストリアの首都。650年の長きにわたって、ヨーロッパに君臨したパプスブルグ王朝は、ウイーンを拠点として多くの芸術文化を生み出してきた。しかし、第一次対戦を前後として、王朝は勢いを失い、ついにこの王朝は崩壊した。第2次大戦では、ナチス・ドイツに侵略され、王朝が築きあげた芸術の都、ウイーンは見るかげもなく、瓦礫の山と化し、人々の心はうちひしがれていた。
物語は、アメリカの小説家、ホリー・マーチンス(ジョセフ・コットン)が、旧友ハリー・ライム(オーソン・ウエルズ)から、「ウイーンに来ればうまい話がある」と誘われ、半信半疑でこの地に足を踏み入れるところから始まる。
駅に迎えに来るはずのハリーの姿は、かき消すように消え、待ち受けていたのは、自動車にひかれて死んだハリーの葬式だった。埋葬地に駆けつけたホリーの前に姿を見せる謎の英国の軍人、キャロウエイ少佐・・・。
サスペンス映画の筋立てながら、この作品には、1948年、アメリカ、ソ連、フランス、イギリスによって分割統治され、主権までも奪われていたウイーンの戦争の傷跡を、しっかりとフィルムにおさめるというリアリズムが息づいている。
オーソン・ウエルズの辛辣な皮肉
そのきわめつきが、オーソン・ウエルズ扮するハリー・ライムに語らせた名台詞。
「ボルジア家支配のイタリアでの30年間は、戦争、テロ、殺人、流血に満ちていたが、結局はミケランジェロ、ダヴィンチ、ルネサンスを生んだ。スイスの同胞愛、そして500年の平和と民主主義はいったい何をもたらした?鳩時計だよ」
この辛辣な言葉は、歴史に残る名台詞として語り草となった。
(この台詞は、原作にはなく、オーソン・ウエルズの自作自演であった説というがある)
「第三の男」といえば、「ハリー・ライムのテーマ」として一世を風靡した旋律がある。
それが生まれるまでには秘められたエピソードがあった。
キャロル・リードがアントン・カラスに会ったのは、ウイーンの森近く、グリンツイングの町にある一軒の「ホイリゲ」(ワイン・バー)だった。
カラスは、音楽学校で学ぶかたわら、学費の足しに、その店でチターを弾いていた。
チターは古楽器の趣を残すと特異な形を持ち、歴史は古く、17世紀に遡る。
ホイリゲのほの暗い光のなかで、アントン・カラスが毛布の包みを解くと、見たこともない箱型の楽器が現れる。
左手の指で弦を抑え、右手の人差し指と中指に鉄製の爪をはめると、前ぶれもなく、強くはじいた。
その深みのある金属音の響きに心打たれ、リードはこの音にすべてを賭けてみようと心に決めた。
「ぼくの映画のために曲を書いて欲しい」
思いもよらない申し出に、カラスはとまどうが、残り時間は限られていた。
こうして始まった言葉もまったく通じないふたりの共同作業は困難を極めた。
カラスは、リードの前で、知っている限りのチター曲を弾き、譜面に書き起こし、リードが取捨を決めてゆく。
途方もない作業が連日続くなか、グランド・ピアノの上には白い五線紙の反故(ほご)がうず高く山となり、カラスの指は、固い弦でめくれ、血をにじませていたという。
さらに弾きつづけ、もうこれでだめだと観念した瞬間、あの不滅の数小節がカラスの指先から放たれたのだ。
「それはたった10秒たらずの出来事だった」当時の地元の新聞は書いた。
「この音だ!これが、1949年のウイーンの音だ!」と、リードは声をあげたという。
映画全編にわたってカラスの曲を還流させるというリードの試みはこのように完成を見たのだ。
「映画音楽は足し算じゃない。掛け算だ」
言いえて妙である。これは「七人の侍」など映画音楽の達人と言われた黒澤明にはそんな名言がある。
参考資料:
「第三の男 誕生秘話」内藤敏子著 有限会社マッターホルン出版
「滅びのチター師」軍司貞則著 文芸春秋社