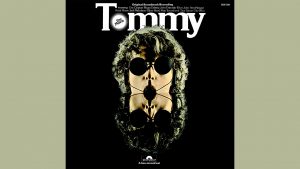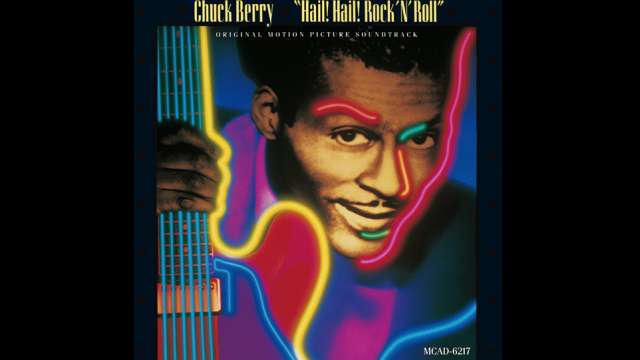「我々の意図は、単に、みんなを圧倒することだった」
ザ・フーのピート・タウンゼントが自伝でそう語ったのは、1970年にリリースしたアルバム『ライヴ・アット・リーズ』についてだ。

1969年、ザ・フーは変革の時期を迎えていた。
5月に発表した4枚目のアルバム『トミー』は、ロック・オペラという新しいコンセプトとともに注目を集め、全英2位、全米4位という彼らにとって過去最大のヒット作となった。
8月にはウッドストックやワイト島フェスティバルに出演し、そのエネルギッシュで過激なパフォーマンスで世界有数のライヴ・バンドとしての地位と名声を獲得する。
しかしライヴが評判になると、市場ではバンドやレコード会社の許可無くライヴを録音したブートレッグ(海賊盤)のレコードが出回り始めた。
この問題をどうにかしたいと考えたレコード会社は、バンド側に何かしらの対策をとるよう命じる。
そこでバンドは古くなった録音機材を秋から始まるアメリカ・ツアーに持っていき、ザ・フーにとって初となるライヴ・アルバムを制作することにした。
12月の終わり、ツアーから一時的に解放されたピートはスタジオを訪れる。
ツアー中に録音された30回分ものライヴからレコードにするテイクを選ぶためだ。
スタジオでは録音を担当したエンジニアのボブ・プリッデンが、全てのライヴを聴き終えたところだった。
ピートはどのライヴがよかったのかボブに訊ねた。ボブがピックアップした中から選ぼうと思っていたからだ。
ところがボブはメモを取っていなかった。
膨大なテープをもう一度聴くだけでも丸5日はかかってしまう。しかし年が明ければすぐにツアーが再開する。
ライヴ・アルバムにふさわしいテイクを探すための時間は残されていなかった。
そこでピートは一から仕切り直し、再度録音することを決める。リーズとハル、その2箇所が選ばれた。
膨大なテープは海賊盤として出回ることのないよう、全て燃やしてしまったという。
1970年2月14日、リーズ大学の食堂に用意された会場には、入りきらないほど大勢の学生が集まった。
開演時間を迎え、メンバーがステージに登場すると、盛大な拍手と歓声が送られた。
ところが演奏が始まるやいなや客席はしんと静まり返る。事前に録音されることを知らされていた学生たちが、余計な音の入らないよう配慮してくれたのだ。
曲が終わるごとに、押さえつけられてた感情を爆発させるかのような歓声が上がった。
静かな、しかし熱気に包まれた会場で、メンバーは渾身のプレイをして応えるのだった。
後日、録音された2つのテープからレコードに入れるテイクを選ぶ作業に取り掛かったのだが、その作業は思いのほか短時間で終わった。
片方のテープにはベースのトラックが入っていなかったからだ。
リーズのほうはバック・ボーカルがちゃんと録れていなかったが、こちらのほうが対処がラクだったし、ライヴならではの熱気も優っていた。
録音からわずか3ヶ月後の5月、リーズの熱気をそのまま封じ込めた『ライヴ・アット・リーズ』がリリースされると、『トミー』に並ぶ大ヒットとなった。
ピートによれば、もともとはレコード会社の「デッカを黙らせてファンを懐柔するための埋め草、つまりは場つなぎ的なレコードだった」のに、それが大きな反響を呼んだことに驚いたという。
とは言っても、その内容には確固たる自信を持っているようだ。
「レコードの終わりに近づくころ聞こえてくる、アドリブでやった激しいリフだとか、〈ヤング・マンズ・ブルース〉のソロだとかは、荒々しいパワーを基本にして音楽を構成する幾千ものエレキ・ギター・バンドに誕生のきっかけをあたえたことだろう」
ピートの作曲家としての才能が開花した『トミー』、そしてバンドのパフォーマンスが充実していることを証明した『ライヴ・アット・リーズ』によって、ザ・フーは新たなステージへと駆け上がるのだった。
ところが、今度はその2枚が高い壁となってそびえ立ち、バンド、そしてピートを苦しめることになるのである。
参考文献:
『ピート・タウンゼント自伝 フー・アイ・アム』ピート・タウンゼント著 森田義信訳(河出書房新社)