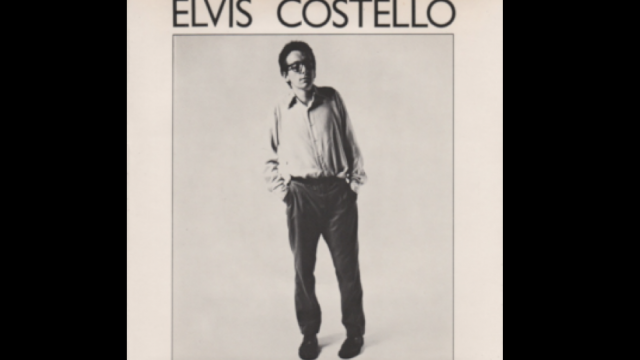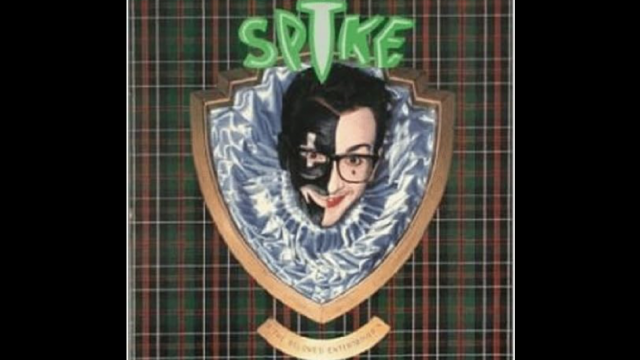♪
やあ、暗闇、僕の昔からの友人よ
また君と話しにやってきたよ
何故って、僕が眠っている間に
ひとつのビジョンがこっそり近づいてきて
種を残していったのさ
そして僕の脳に植えられたそのビジョンは
今もそこにある
静寂の音の中に
♪
サイモン&ガーファンクルの代表曲のひとつである「サウンド・オブ・サイレンス」。
ポール・サイモンがこの曲を書いたのは、彼が大学を卒業して、音楽業界の営業マンとして働いている頃の話である。
ポールの就職先は、音楽出版社だった。出版社が抱える楽曲をレコード会社に営業で売り込み、レコードにしてもらうのが彼に与えられた仕事だった。
「働き始めて半年、結局のところ、僕はただの1曲もレコード化することができなかったのです」と、ポール・サイモンはNPR(ナショナル・パブリック・ラジオ)のインタビューで語っている。
「給料泥棒になりたくないという罪の意識もあり、僕は自分が書いた曲をその音楽出版
社に渡してきました」
ところがある日、ポールは会社とぶつかってしまう。
そしてこう言い放ったのだ。
「わかりました。辞めます。新曲をあなた方には渡しません」
その新曲こそ、「サウンド・オブ・サイレンス」だったのである。
「そういう意味では、言い争いをしたのはラッキーだったことになります。そして僕は、自分でその曲を出版しようと思い立ったわけです」
ポールはコロムビア・レコードと契約し、1964年、サイモン&ガーファンクルとしてデビュー・アルバム『水曜の朝、午前3時』を発表する。「サウンド・オブ・サイレンス」はその中の1曲として収められることになった。アコースティック・ギターの伴奏によるシンプルな演奏だった。
だが、このデビュー作は失敗に終わってしまう。
そんな「サウンド・オブ・サイレンス」を生き返らせたのは、コロムビア・レコードのプロデューサー、トム・ウィルソンだった。
彼は、フォークから転向したばかりだったボブ・ディランの「ライク・ア・ローリング・ストーン」を録音するためスタジオに来ていたミュージシャンたちを使って、「サウンド・オブ・サイレンス」の元音源にエレクトリック・サウンドをかぶせてみたのだ。
その時、デビュー作の失敗で失意のポールは、何も知らず、ロンドンにいた。
翌1965年にシングル発売された新たな装いの「サウンド・オブ・サイレンス」は、年が明けた1966年の元旦、ヒットチャートの1位を飾る。
当然、彼らはボブ・ディランと比較されるようになった。
「ボブ・ディランに何とか影響を受けないように、と僕は大変苦労したものです」と、ポール・サイモンはモジョ誌に語っている。
「僕が『サウンド・オブ・サイレンス』を書いたのは21歳の時ですが、ボブ・ディランの存在なしに、あの歌が書けたとは思いません。ティーンエイジ・ポップにシリアスな歌世界を持ち込んだのは彼ですからね。
だからこそ、彼の物真似はしたくなかったわけです」
その後、「サウンド・オブ・サイレンス」は映画『卒業』で使われたこともあり、世界的なヒット曲となる。
当時、アメリカと冷戦下にあったソ連では、この曲を【資本主義社会における孤独の象徴】だと論評した。
♪「馬鹿者め!」と僕は言った。「君はわかっちゃいないんだ」と
沈黙は、癌が増殖するようにひろがっていくのさ ♪
ポール・サイモンが歌ったのは、社会(都会)とコミュニケイションがうまく取れない主人公だ。
主人公は、裸電球の下で目撃したのだ。
人に語りかけるのではなく、ただ喋っている人たちを。
人の話を理解しようとするのではなく、ただ聞いている人たちを。
喧騒の中の雑踏は、実は虚空のような沈黙そのものだということを。
♪
僕の言うことを聞くがいい
僕の伸ばす腕を取るがいい
だが、僕の言葉は言葉なき雨粒のように
沈黙の井戸の中で木霊した
♪
ポール自身は「この曲は“若者特有の感情”を歌っただけだ」とNPRのインタビューで語っている。
「歌全般に言えることですが、歌詞というよりは、まずメロディが何を語るか、だと思うんですよ。ちゃんとしたメロディがなければ、どんなことを伝えたいにしろ、それは聞く人に届かない、と僕は思っているんです。シンプルなメロディがまず、人の心を開く。だから歌詞を聞いてもらえるわけです」
歌詞を聞いてもらえる=理解してもらえる、ということだろう。
その言葉に少しだけ、ディランと比較されてきたポールの意地を感じる。
「サウンド・オブ・サイレンスは、僕が21歳の時に書いたものです。若い詩です。洗練されてはいませんが、まぁ、その年で書いたものとしては悪くないように思います。誰も僕の話を聞いてくれない、結局誰も人の話なんて聞いてくれないんだ、という思春期の怒りみたいなところから始まっているわけですが、その中に、幾分かの真実があったから世界の人に聞いてもらえたんでしょうね。
でも、一番大きかったのはメロディーだと思っています」
※このコラムは2015年2月12日に公開されたものです