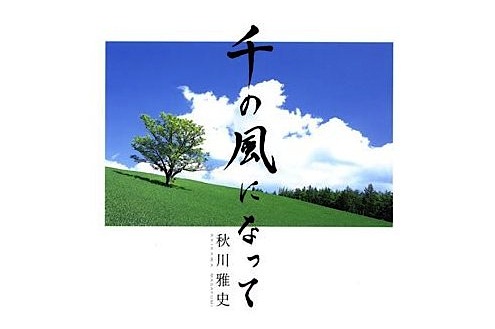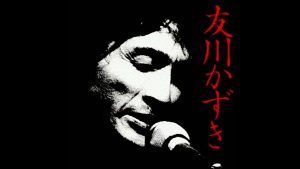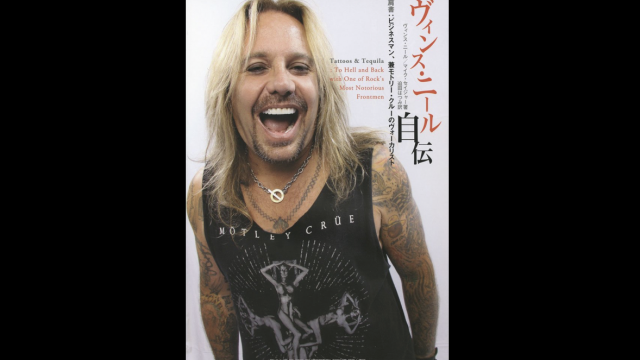この「千の風になって」のクレジットを見ると、作詞者が“不詳”となっており、作曲と日本語詞は、新井満(あらいまん)と記されている。いったい“不詳”とはどういうことなのだろう?
イギリスの日刊紙『タイムズ』によると、原詩となったといわれている「Do not stand at my grave and weep」は、アメリカ人女性メアリー・フライの作品とされている。詩の起源としてはこの説がもっとも有力とされるが、海外においてもまだ論争があり、確実な説というわけではない。
新井満は、単行本版『千の風になって』において、原作者をめぐる複数の説のひとつとして、メアリー・フライの名前を挙げているものの、決定的な説としては紹介しておらず、作者不詳とするのが最も適切だと主張してる。
さて、新井満とは一体どんな人なのだろう?
プロフィールを見ると、「作家」「作詞作曲家」「写真家」「環境映像プロデュ-サー」「長野冬期オリンピック開閉会式イメージ監督」「日本ペンクラブ常務理事」など、多方面で活躍している人物である。略歴を見ると、「1946年新潟市生まれ。上智大学法学部を卒業後、電通に入社。在職中はチーフプロデューサーをつとめた」と書かれている。
小説家としては、1988年『尋ね人の時間』で芥川賞を受賞。2003年に写真詩集『千の風になって』(講談社)を発表。それに曲を付け自ら歌唱したCD『千の風になって』(ポニーキャニオン)を、様々アーティストたちがカバーしはじめる。
そして、2006年紅白で、秋川雅史が歌って一躍“時の歌”となり、2007年の日本レコード大賞作曲賞を受賞する。
作者“不詳”とされている原詩は、90年代の中頃から多くの人々の悲しみを癒し、不思議なチカラを持つ詩として、イギリスやアメリカで大きな反響を呼んできた。
北アイルランドの独立を目指すIRA(アイルランド共和国軍)によるテロで命を落とした24歳の青年が、「私が死んだときに開封して下さい」と、両親に託した手紙の中で引用されていたり、マリリン・モンローの25回忌で朗読されたり、9.11の同時多発テロの追悼式で、父親を亡くした11歳の少女によって読まれたりもした。
新井満が意訳し作曲するに至ったのにも、あるきっかけがあったという。
1996年、彼の幼なじみだった友の妻が癌におかされ、48歳の若さで亡くなった。食生活改善などの市民運動に積極的に取り組んでいた彼女の一周忌には、60名以上の仲間たちによって追悼文集が作られた。その文集に、作者不詳の西洋の詩が紹介されていた。
彼はそれを見て感動し、「この詩を歌にすれば、遺された家族や、彼女の仲間たちの悲しみをほんの少しでも和らげることができるのではないか」と、原詩となる英語詩を探して、曲と歌に合う歌詞をつけようと試みた。
ギターを持ち出しメロディーを紡ごうとしたが、何度やっても上手くいかず、一度は作曲をあきらめた。数年後…ふと思い立って、まずは丁寧に英文の翻訳からやることにした。
比較的かんたんな単語ばかりの文章だが、どうしても上手くまとまらない。そこで英文を朗読した後、まぶたを閉じて、詩のイメージだけを感じ取ろうとした。すると、詩の一節にある「winds(風)」という言葉が心に大きく浮かび上がってきた。
風を見た人っていないですよね? でも、森の中を風が通ると木々が揺れるでしょ? 風の形がわかるんです。風の姿を見たような気がしましたね。『風立ちぬ』という名作があるように、風は“立つ”んです。つまり生まれるんです。
しかし、すぐにやんでしまいます。ところが、しばらくするとまた息を吹き返して吹きはじめます。「そうだ!風というのは息なんだな! 大地の息なんだな! 死んで風になるということは、この地球の大地と一体化することなんだ!」と、理解できたんです。
“死と再生のポエム”こそ作者の言わんとすることだとわかると、新井は自分なりの意訳を一気に進めた。そしてギターを持ち直して曲をつけるのに、5分もかからなかった。
2000年の夏、こうして日本の名曲「千の風になって」は誕生した。

千の風になって

千の風になって
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから