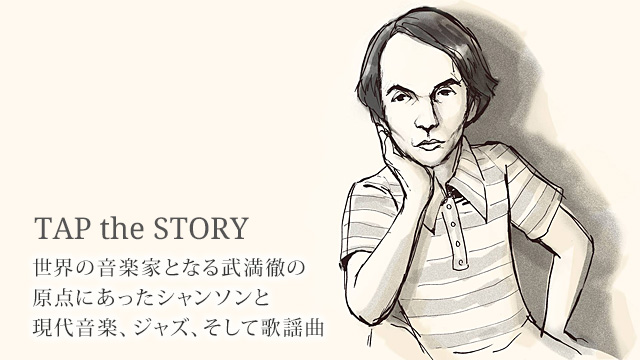西洋音楽の世界で最も有名な日本人作曲家、武満徹が東京の本郷で生まれたのは1930(昭和5)年10月8日のことだ。
生後1ヶ月で保険会社のサラリーマンだった父の勤務先、満州の大連に渡った武満だったが、6年後に内地の小学校に入るため一人で帰国した。
そして東京の叔父の家から小学校に通った。
父はジャズと社交ダンスが好きなだけでなく、玄人はだしで周囲にダンスを教えたりもしていたそうだ。
しかし重い病気にかかって家族で引き揚げてくると、その翌年には郷里の鹿児島で亡くなっている。
太平洋戦争が始まって2年、中学生の武満は軍国主義教育を受けて軍国少年になっていく。
だから予科練の試験を受けたのだったが、華奢な体格ではねられてしまう。
それからは勤労動員にかり出される日々となったが、そこで決定的な体験をして音楽に目覚めた。
ある日、防空壕で若い見習い士官が手回しの蓄音機で聴かせてくれたレコードから、強烈なショックを受けたのである。
その『歌』は、私にとってひとつの決定的な出会いとなりました。
その『歌』に私が感じたものをここに記述するのは、たぶん不可能なことです。
あの時、私(たち)はその『歌』を意志的に聞こうとしたのではなく、『歌』は、ただ静かに大きな流れのように私(たち)の肉体へそそふがれたのです。
私は、大河から分岐(わか)れた支流のように、そそがれる水に身を浸して、世界の全体というものを感じていたのでした。
こっそり聞かせてもらったその歌は敵性音楽として禁じられていたフランスのシャンソン、「パルレ・モア・ダムール(聴かせてよ、愛のことばを)」だった。
それまで音楽に心を揺さぶられたことがなかった武満だが、戦争が終わったら音楽をやろうとその時に心に決めたという。
しかし武満には楽器を習うとか、楽譜を読むとか、音楽的な素養は何ひとつなかった。
何もない。何もわからない。何も弾けない。でも、とにかく音楽をやりたい。
自分は音楽家になるんだという決意は全くゆるぎませんでした。何もできないから作曲家になったのかもしれません。
楽器が何もできない。ピアノを買う金もない。
作曲家なら楽器がなくてもいいだろうから、いちばんお金がかからないんじゃないか、と思ったんですね。
音楽教育を受けられる環境ではなかったにもかかわらず、武満は音楽家になる強い決意のもとで作曲家を目指した。
学校には行かずにニコヨンと呼ばれる日雇い労働をしながら、紙や板に鍵盤を書いてそれを持ち歩いていたという。
日本にもオーケストラ曲を書く作曲家がいることを知って、演奏会に出かけて身震いするほどの感動を受けたのは18歳のときだ。
その直後、街頭で「日米現代音楽祭」の予告ポスターを目にして、武満は切符を買うために訪ねていった東宝交響楽団の事務局で、対応に当たった職員に自分にふさわしい先生を紹介してほしいと訴えた。
その職員から親切に紹介してもらったのが清瀬保二、2週間前の演奏会で聴いたヴァイオリン・ソナタの作曲者だった。
さっそく面会に行った武満は、それをきっかけに出入りを許されることになった。
清瀬の弟子になった武満はその後、黒澤明監督の『酔いどれ天使』『野良犬』『羅生門』といった映画音楽で活躍していた作曲家、早坂文雄の知己を得て師とあおぐことになる。
結核のために体力がない早坂のもとで映画音楽を作る手伝いを始めた武満は、スコアの書き方やオーケストレーションの基礎を覚えていった。
やがて映画や演劇、ラジオドラマなどの仕事に関わるようになり、徐々に頭角を表していくのだ。
しかし師と同じ結核に罹ったことで、1953年には入院せざるを得なくなる。
そこからはいつも死と隣り合わせの日々が続いた。
だがそんな中でもあきらめずに仕事を続けて、1956年に初めて自分の名前がクレジットされた映画を手がけた。
大ヒットを記録した太陽族映画、石原慎太郎原作の『狂った果実』である。
この映画で主演した石原裕次郎が、一気にスターダムを駆け上がった。
当時は単なる風俗映画としか見なされなかった『狂った果実』だが、後にフランスのヌーベルヴァーグにまで影響を与えていたことが明らかになる。
武満はここでジャズを効果的に使っていた。
その翌年、武満は東京交響楽団に委嘱された作品、「弦楽のためのレクイエム」を発表する。
特にその頃は、病気が重くて、自分でもいつ死ぬかわからないと思っていましたから、死ぬ前にどうしても一曲作りたいと思っていました。
ちゃんとした作品を一曲も書かないで終わっては、死んでも死にきれないという思いでした。
「弦楽のためのレクイエム」はアメリカのジャズ・ピアニスト、レニー・トリスターノの「レクイエム」に感動して、自らの死を意識しながら書いたものだ。
トリスターノの「レクイエム」は1955年に急逝した、亡きチャーリー・パーカーに捧げられた作品だった。
テープの回転数を操作してスピードを落とし、普通ではない音色と響きのピアノに、もう一度ピアノを弾いて多重録音した実験的で、前衛的な音楽である。
鎮魂歌らしく詩情にあふれた演奏は、独特の暗さに彩られて武満の音楽にも通じている。
「弦楽のためのレクイエム」を完成させた武満は、自らの意志と力によって初めて音楽人生の中で確かな第一歩を踏み出した。
そして27歳を迎えたころに始まった新薬の投与によって結核が快方へと向かい、音楽家としての人生にわずかながら光がさし始める。
死の淵から逃れて仕事に取り組めるようになると、武満はジャズと歌謡曲で成功していたマナセプロダクションで、鈴木章治とリズム・エースの半分バンドボーイ、半分アレンジャーという仕事をして生活費を稼ぐようになった。
そのときに手がけたアレンジではないかとささやかれているのが、鈴木章治とリズム・エースの「鈴懸の径」だ。
1942年9月に発売された「鈴懸の径」は灰田勝彦の流行歌で、マイナーでゆったりとした3拍子の曲だった。
ところが戦後のジャズブームの中でヒットした鈴木章治とリズム・エースのヴァージョンは、4拍子の軽快なジャズになっていたのだ。
しかもマイナーでもメジャーでもない、半音階で前奏が始まっていたことで実に新鮮な響きとなった。
新しい才能との出会いや仕事の依頼が少しづつ増えたところに、大きな幸運が訪れるのは1959年の春だった。
来日した世界的な巨匠、作曲家のストラヴィンスキーが「弦楽のためのレクイエム」の録音テープを聴いて絶賛したのである。
「この音楽は実に厳(きび)しい、まったく厳(きび)しい。このような厳(きび)しい音楽が、あんな、ひどく小柄な男から生まれるとは!」
そのことによって「TAKEMITSU」の名前は、世界中にまで広まったのだった。
1960年代に入ると武満は現代音楽と映画音楽で、世界でもっとも知られる日本人の作曲家となっていく。

●商品の購入はこちらから
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから