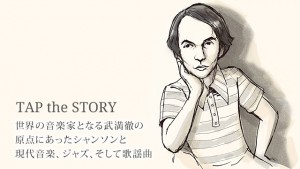ミック・カーン。元ジャパンのベーシストとして活躍した彼は、SUGIZO、土屋昌巳、布袋寅泰、佐久間正英、屋敷豪太など、日本のミュージシャンとの活動も多く、“親日家”としても知られていた。
1982年のジャパン解散後は、ソロ活動をはじめ多くのミュージシャンと組んで作品を残している。元バウハウスのピーター・マーフィーとの“ダリズ・カー”、デヴィッド・トーンとテリー・ボジオと組んだ“ポリタウン”、元ジャパン・メンバーによる“JBK(ジャンセン/バルビエリ/カーン)”など、いくつかのユニットへの参加やセッションミュージシャンとして活躍の場を広げて行ったミック・カーンは、27歳の頃にどんな日々を送っていたのだろう?
1958年、当時イギリス領だったキプロス島で生まれたミックは、3歳の時に家族と共にイギリスへ移住した。7歳でハーモニカ、11歳でバイオリンを習い、既に自分を表現する手段に興味を抱いた。後に学校のオーケストラに加わってバスーン(木管楽器)を担当し、ロンドンスクールシンフォニーオーケストラのメンバーとして選出される。
その後、同じ学校の同級生デビッド・シルビアン(vo)とその弟スティーブ・ジャンセン(d)と出会い、バンドを結成。1974年6月1日に初ライブを行う。この時、ミックはまだ15歳だった。さらに同じ学校に通うリチャード・バルビエリ(key)と出会い、音楽紙”メロデイメーカー”のギタリスト募集の広告を見てロブ・ディーンが加わり、遂にバンド”JAPAN”が誕生する。
1978年(当時20歳)、アリオラ・ハンザ・レコードより1stアルバム『Adolescent Sex(果てしなき反抗)』でデビュー。その頃のイギリスのミュージック・シーンは、パンクからNEW WAVEへと流れており、“ニューロマンティクス”という新たなジャンルも生まれつつあった。
1982年(当時24歳)、5枚目アルバム『Tin Drum(ブリキの太鼓)』を最後にバンドは解散。ミックはJAPAN解散の一年前に、ゲイリー・ニューマンのアルバム『Dance』に参加したことをきっかけに活動の幅が広げつつあった。
その後も土屋昌巳、矢野顕子、ミッジ・ユーロ(ウルトラヴォックス)、ピーター・マーフィー(元バウハウス)、ケイト・ブッシュ等とのセッションを精力的に行い、独自の音楽スタイルと唯一無二のベースプレイに磨きをかけていく。
そんな中、デヴィッド・トーンというアメリカの音楽家・ジャズギタリストに出会い、大きな影響を受けることとなる。デヴィッド・トーンと言えば、ただのギタリストにとどまらず、様々なエフェクト技術・ループ奏法・サンプリングを得意とする前衛的な人物である。当時その才能はジャズの世界にとどまらず、むしろポピュラーミュージックの世界で注目されていた。
「JAPANを解散して様々なセッションに参加したけれど…当時の僕はどこかもう音楽に情熱を持てずに引退も考えていたりしたんだ。自分の音楽を人々の耳に届けるための戦いに疲れ果て、レコード会社からのプレッシャーにうんざりし、ベースという楽器を見るのも嫌になっていた」
ミックは自身がちょうど27歳を迎えた当時のことを自伝の中でこんな風に振り返っている。デヴィッドとの出会いによって、自分のプレイが所詮我流に過ぎないことを気づかされたというのだ。二人のファーストコンタクトはこんな具合だった。
「君がミックか? 意外と小柄なんだね。サウンドは大きいのにね(笑)」
「へぇ…君がデヴィッドか。6フィートはあるブロンドのサーファーってイメージだったんだけどね(笑)」
デヴィッド・トーンとのプロジェクトのリハーサルは、ドイツのドルトムントにあるスタジオで3日間に渡って行われた。ドラムは元イエスやキングクリムゾンで活躍したビル・ブルーフォード。
「彼は高度で実験的なドラマーだった。目まぐるしく変化する彼のリズムテンポに対して、常にベースを合わせることが要求される。普通のドラマーはタイム通りにプレイすることを目指すものなのに、彼のプレイスタイルは本当に風変わりだった」
そしてそのプロジェクトを通じて、もう一人の重要な人物と出会うこととなる。
「マーク・アイシャムのトランペットプレイの美しさについてはどう表現したらいいのだろう? デヴィッドが奏でるノイジーなギターとは対照的に、バンドにアコースティックな側面を加える重要な役割を果たしていた。」
デヴィッド・トーンのプロジェクトで演奏を重ねていく中で、ミックは大切なことを学んだのだ。当時27歳だったミックに対して、ローリング・ストーンズやヴァン・モリソン、ジョニ・ミッチェルのアルバムにも参加してきたトランペット奏者マーク・アイシャムがこんな言葉をかけてきた。
「僕らは多くの時間を費やして音楽を勉強し、譜面を読み、自分のサウンドを見つけるために必死にやってきた。君の場合は、最初から独自のサウンドを持っている。つまり君はラッキーなんだよ。どんなミュージシャンでも自分だけのサウンドを求めて葛藤するんだからね。それは色んな知識を教わったからといって見つけられるものじゃないんだ。君はすでに他人が簡単に手に入れられないものを自分のものにしているんだよ。そうだろ? 2〜3年ベースに情熱を持てなかったことなんて問題じゃないのさ! 弾きたい時にベースを手にすれば、君はたちまち地球上の誰にも真似できないサウンドを出してしまうんだから!」
デヴィッド・トーンとのツアーを振り返って、ミックはこんな感想を自伝に残している。
「ツアーが終わる頃には僕の指先にはひび割れができ、ベースへの愛情が戻っていた。やはりベースは僕と外の世界を繋ぐ最良の手段だったんだ。自信、自己表現、逃避のすべてがその中に詰まっているのさ。このプロジェクトを通じて学べたことがある。インプロビゼーションのイロハを習得できたこと。ドラマーが脱線しても僕のプレイを基準にして戻って来れるように“曲をキープする術”を身につけたこと。自分が慣れ親しんできたロックやポップスとはまったく異なる世界観を持つ音楽を知ったこと。これらすべては彼らと一緒にツアーをして得られたものなんだ」
<引用元・参考文献『ミック・カーン自伝』ミック・カーン(著)中山美樹(翻訳)/リットー・ミュージック>

Adolescent Sex

『Tin Drum(ブリキの太鼓)』
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから