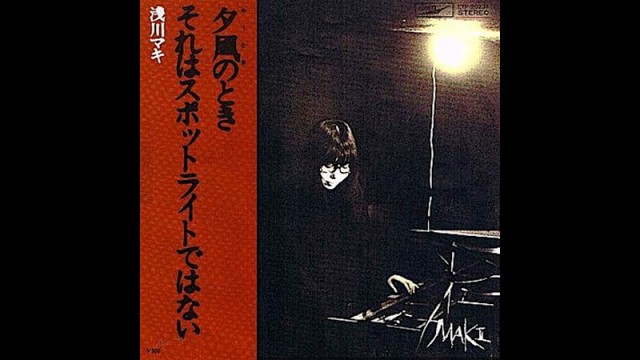日本におけるレコードの“吹き込み”の歴史は1901年(明治34年)にさかのぼる。
当時はイギリスのグラモホン社、アメリカのビクター社、コロムビア社が日本に出張し、音を吹き込んで本国に持ち帰り盤を作っていたという。
日本国内ではまだレコード屋が存在しなかったため、海外で製品化されたレコードは全国の時計屋や自転車屋で販売されていた。
国内で録音した音を海外で製産し再び国内に輸入して販売する…いわゆる逆輸入盤だったのだ。
当時、それらはやすやすと庶民が手にできるような代物ではなかった。
何しろ高価だったのだ。
逆輸入の行程において、日本でもアメリカでも“出国税”と“入国税”のダブルの税金がかかるため、当然値がつり上がってしまうのだ。
加えて関東大震災の影響で、レコードも蓄音機も贅沢品とみなされるようになり…入手困難となっていたという。
そんな事情もあって、レコードの文化はなかなか発展しなかったのだ。
ところがこの時期に、新しい録音技術が日本にも伝わってくる。
それまでラッパのような筒に向かって音を吹き込んでいた方法から、マイクを使用した電気吹き込みが主流となり、ビクターは横浜に、コロムビアは川崎にレコードの製造プレス工場を整備した。
税金がかからない上に、時間もかからない。
さらには大量製産も可能となったのだ。
また、発売されたレコードがラジオにのって全国に流れると、それが抜群の宣伝効果となり、続々とヒット曲が生まれる時代となってゆくのだった。
1927年(昭和2年)9月、米ビクターの全額出資によって“日本ビクター蓄音機株式会社”が創立。
様々なことが起こった時代だった。
リンドバーグの大西洋横断飛行、芥川龍之介の自殺、浅草〜上野間に地下鉄開業、大相撲の実況中継開始、野口英世が西アフリカで病死…などなど。
翌1928年に“日本最初期の商業レコード”が発売される。
曲のタイトルは「波浮の港」。
1923年に野口雨情が発表した詞に、中山晋平が作曲した歌曲である。
日本初の“スター歌手”となった佐藤千夜子が日本ビクターからリリースした2ヶ月後
に、当時世界で活躍していたテナー歌手の藤原義江がアメリカ滞在中に同曲を米国ビクターで録音し“輸入盤”として発売される。
同じビクターでも、国内盤となる佐藤のレコードは黒盤、そして国外盤となる藤原のレコードは赤盤としてレーベルの色が分けられていたという。
同じ楽曲でも佐藤の国内盤は米盤よりも売り上げを大きく上回り、10万枚の大ヒットを記録する。
作詞をした野口雨情は、後にこの曲にまつわるちょっとしたエピソードを語っている。
「そもそもこの曲は一枚の写真を元に作ったのですが、作品が発表されてからあらためて地図を確認したところ…波浮の港からは夕焼けは見えないことがわかったんです。青くなりましたよ。」
昭和初期、この歌の舞台となった伊豆大島は観光とは無縁の離島だった。
島の南東部にある波浮(はぶ)港村は、島の中心部の新島村(1940年に新島村が元村と改称するまで大島にあるのが新島村で、新島にあるのは新島本村だった)からも三原山を挟んで反対側にあるわびしい漁村だったという。
当時は東京からの船便もなく…当時、野口は一枚の写真から受けたイメージだけを膨らませ、現地に足を向けることもなく地図さえも確かめずに詞を書き上げたのだ。
このため、歌詞には“矛盾する風景”がいくつか登場するという。
東を海に面し西側に山を背負って、まったく夕日が見えない波浮港に夕焼けを見せる点や、野口の故郷の磯原にはたくさんいるものの、大島にはまったくいない海鵜が登場する点などなど…。
しかし、そこは“日本最初期の商業レコード”となった記念すべきヒットソングゆえに、矛盾とは言わずに“創造の賜物”として解釈しておきたいものだ。
磯の鵜の鳥ゃ 日暮れにゃ帰る
波浮の港にゃ 夕焼け小焼け
明日の日和は
ヤレホンニサ 凪(なぎ)るやら
<引用元・参考文献『流行歌の歩み〜日本歌謡大全』一般社団法人 日本歌手協会>