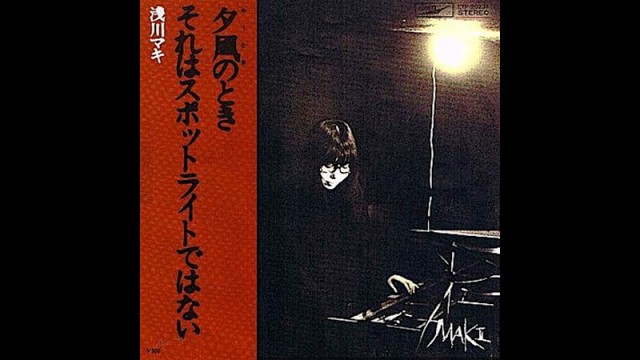「1968年は夫と知床旅情に出会った私の原点。世の中が二つに割れているような当時、ふと思ったのは、人と人の間に裂け目ができても、底でつながる歌を唄いたいということだった。歌い継がれ、心に根を生やして育っていく。知床旅情はそんな歌だから、大切に歌いつづけたいんです。」(加藤登紀子)
それは1960年(昭和35年)の出来事だった。
北海道東部に位置する知床半島の羅臼(らうす)で、東宝映画『地の涯に生きるもの』の長期ロケが行われた。
“知床”という地名は、アイヌ語の「シレトク(siretok)」で“地の涯(はて)”を意味する言葉が由来とされている。
映画の原作は戸川幸夫の小説『オホーツク老人』で、国民的俳優の森繁久弥(当時47歳)が主演を務めたことで話題作となった。
ロケの最終日、森繁は「さらば羅臼よ(別題:オホーツクの舟歌)」という歌を作って羅臼の人達に贈った。
それは知床住民の間で昔から歌われてきた曲を基にした歌だった。
歌詞には冬の厳しさ、春の訪れの喜び、そして望郷の想いが描かれている。
森繁が紡いだその歌は、マスコミ発表を意図としたものではなく、村をあげて大人から子供たちまで撮影に協力してくれた羅臼の人々への感謝の気持ちで作られたものだった。
その時の録音テープが、人から人へと徐々に広まり…1962年(昭和37年)の年末、森繁はNHK紅白歌合戦で「知床旅情」として同曲を歌うこととなる。
それによって、この歌は多くの人びとに知られるようになったが…当時レコードの売り上げはあまり伸びなかったという。
それから10年後、この歌は全国的なヒットとなる。
きっかけに作ったのは、当時27歳の加藤登紀子だった。
彼女は、前年に「ひとり寝の子守唄」をヒットさせたことをきっかけに“シンガーソングライター”として成長を遂げようとしていた時期だった。
加藤登紀子はこの歌との出会いについて、あるインタビューでこんな風に語っている。
「初めて知床旅情を聴いたのは25歳の頃(1968年)でした。学生運動の活動家で、後に私の夫となる藤本敏夫との初デートの時でした。その日の夜の別れ際に藤本が歌ってくれたのが知床旅情でした。夜空の下で堂々と想いを表現する彼の姿に、歌手3年目の私は衝撃を受けました。負けちゃったなあってね。その後、藤本は拘束されて…私は別離の中で「ひとり寝の子守唄」を書きました。知床旅情との出会いが、初めて自分のために作った曲に繋がったんです。衣装を着たシャンソン歌手ではなく、身の丈にあった自分の曲を歌うシンガーソングライター加藤登紀子が生まれた瞬間でした。」
当時彼女は『日本哀歌集』というコンセプトアルバムを作るために、全国各地に伝わる名曲を発掘する作業を行なっていた。
「銀座のすずめ」「琵琶湖周航の歌」「満州里小唄」「西武門哀歌」などと共に探し出されたのがこの「知床旅情」だった。
たまたまこの年、JRの前身である日本国有鉄道が個人旅行客の増加を目的としたキャンペーン“ディスカバージャパン”を展開することとなり、加藤の歌う「知床旅情」がキャンペーンソングとして抜擢される。
楽曲の素晴らしさ、加藤の哀愁漂う歌唱、そして大々的な宣伝効果が相俟ってシングル盤「知床旅情」は140万枚の売り上げを記録するミリオンセラーとなる。
「私が知床旅情をリリースする前年(1969年)の秋頃、森繁さん主催のイベントでひとり寝の子守唄を歌うと、楽屋にいた森繁さんが“誰が歌っているんだ?ツンドラの風の冷たさを知っている声だ”と言って出てこられて、舞台の袖で歌い終えた私を両手を広げて迎えてくれました。私は旧満州(現中国東北部)のハルビン生まれで、森繁さんは旧満州からの引き揚げ者。大陸への想いの共有が、二人の縁を結んだと思っています。そう…知床にも引き揚げ者がたくさんいて、その人たちが今でも“登紀子ちゃん、よく生き延びたね”と可愛がってくれます。森繁さんが晩年になっても“ハルビンに行って、二人で馬車に乗って走ろうよ”と話していたことが忘れられません。その後、私は80年代に中国でコンサートを開いた時に日本人残留孤児の方たちを前に、中国語で知床旅情を唄いました。その時、彼らと一緒に泣いたことが今でも忘れられません。」(加藤登紀子)
<引用元・参考文献『歌がつむぐ日本の地図』帝国書院>
<引用元・参考文献『フォーク名曲事典300曲』/富澤一誠(ヤマハミュージックメディア)>