野坂昭如が歌ったシングル盤の「マリリン・モンロー・ノーリターン」は、1971年にコロムビアからレコード発売された。
しかし、時代のトリックスターのような立場にいた黒メガネの直木賞作家が、歌手としてデビューするという話題がマスコミに派手に取り上げられたものの、それほどヒットしたというわけではなかった。

作家の久世光彦はエッセイの中で、不快感を覚えたという文章を残している。
はじめて聴いて、嫌な歌だと思った。野坂昭如さんが歌っていたからかもしれない。陰気な声だった。始終よろけ気味の歌い方も苛立つ。いやに素っ気ないかと思うと、急に思い入れたり、かと思えば、もうどうでもいいといった風に投げやりになったりする。
聴いていて胸騒ぎがするような歌い方には、どこかに野坂昭如という表現者の怪しさがつきまとっていた。最初の音から危うさをともなう音程が、聴き手の不安感をかきたてたともいえる。
「マリリン・モンロー・ノーリターン」がヒットしなかったのは、その不安感に原因があったのではないか。
ところが、話題性がなくなった後になったのに、レコードは地味な動きではあっても売れ続けた。それはB面に入っていた「黒の舟唄」のおかげだった。
「マリリン・モンロー・ノーリターン」と「黒の舟唄」は、どちらもクレジットに”作詞・能吉利人 作曲・桜井順”と記されている。
能吉利人という謎めいた名前の作詞者がCMソングのヒットメーカーで、作曲家の桜井順と同一人物であることなどは、当時まったく知られていなかった。
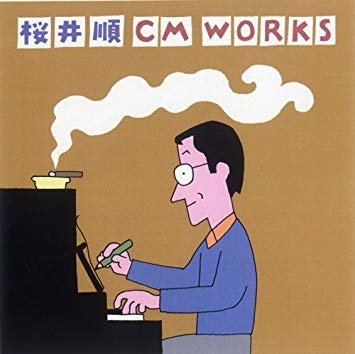
桜井潤/CM Works
そして当然のように、誰もが作詞は野坂が書いていたと思ったのは、小説で描かれる文章のタッチと歌詞のイメージが自然に重なるものだったからだ。
再び久世光彦のエッセイから引用しよう。
「黒の舟唄」の方は、いかにも野坂さんらしい発想である。唄の成立に野坂昭如の<暴力>が感じられる。――ここで私は、ふと考える。嫌な歌だと眉を顰めながら、どうして胸に引っ掛かるのだろう。鈍い痛みに私は小さく呻く。それは深爪のようなものだ。
桜井順はCMで作詞することもあったのだが、その場合には”作詞・作曲 桜井順”と表記していた。ところが、野坂の歌に関してだけ能吉利人の名を使っていたのは、ソングライティングの方法に由来するという。
いつも野坂のそばで言動や行動を見ながら、桜井順は面白そうなものを歌にしていく方法をとっていた。それは野坂の中にあるものを感じて曲を作るということなので、結果としてはひとりで作詞と作曲をしているが、「ふたりでひとりのシンガー・ソングライター」だったという。
僕が最初の頃に作ったものっていうのは、野坂さんの言動を見て感じたことを歌詞にして、それをいきなり歌にしちゃっているのがほとんどだから。書き直したりっていうことがなくて、書いた僕ですら意味が分からなかったのね(笑)
例えば「花ざかりの森に 禿鷹がやって来る 目玉も肉も ズタズタ 屍がひとォつ」なんてイメージだけで書いてるから、あとで「何のことだろう?」って(笑)
でも野坂さんがそれを歌った後で、大菩薩峠で連合赤軍がどうしたこうしたっていう事件が起こったりして、そういうシンクロはちょっと怖かったんだけどね(笑)
出来上がった歌を渡された野坂はつべこべ言うことなく、まるで物でも食らうかのように黙々と歌ったという。作・編曲の桜井順、作詞の能吉利人、それに歌手の野坂昭如とが三位一体になって、はじめて歌が成立していたのである。
その点については野坂自身もこう解説している。
桜井のつくる歌は、特別奇をてらったものではない。時代を嗤い、かつからかい、さらに皮肉の裏返し、力まず焦らず。このゆとり、この術は桜井独自のもの。本人は無意識だろう。
だが実は、真っ向から時代と向き合ってきた。歌手野坂は、さすが本職と関心しつつ、与えられた曲を、練習も訓練もせず、ただ歌うだけ。勘と度胸が頼り。
つくり手と、歌い手。互いに何の相談もせず、注文もつけない。何となく次から次へ生まれた歌は、桜井順という才能が、野坂というフィルターを通して世に出したもの。
やがて多くの人の胸に何かが引っかかった「黒の舟唄」が、盛り場の有線放送などを通じて口コミによって広まっていった。
そして、1年が過ぎて知る人ぞ知る変わった歌というポジションを得たところで、楽曲に新しい生命を注いでくれるシンガーとの出会いが待っていた。
黒いサングラスをかけた盲目のシンガー・ソングライター、長谷川きよしによって力強いギターと共に歌われることによって、「黒の舟唄」は歌詞に描かれていた哀しみや悔いがいっそう深く聴き手の心に届いたのである。
同時代に生きる者たちばかりでなく、後に続く人たちに「黒の舟唄」が歌い継がれたのは、長谷川きよしの果たした功績が大きい。
(【女優の大竹しのぶが泉谷しげると歌った「黒の舟唄」】へと続きます)
<注1>久世光彦氏の文章の引用元は、久世光彦著「ベスト・オブ・マイ・ラスト・ソング」(文春文庫)です。

長谷川きよし/THE OTHER もうあきてしまった

長谷川きよし/卒業
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから












