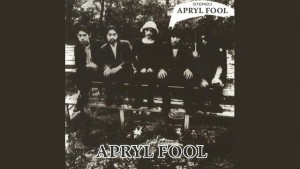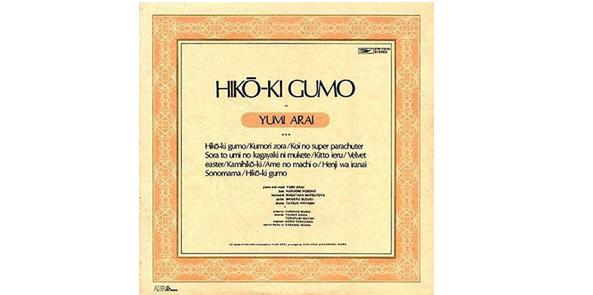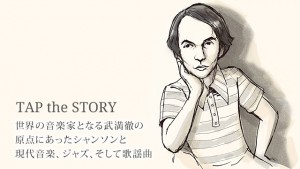松本隆がプロのミュージシャンとして音楽活動を始めたのは1969年の2月、細野晴臣に誘われてグループサウンズの「ザ・フローラル」にドラマーとして加入した時からである。
アマチュア・バンド「バーンズ」のドラマーだった松本はベースがやめた際に、立教大学にベースのうまい人がいると聞いてメンバー補充のために、直に電話をかけて細野に面会を申し込んだ。
細野が20歳の大学生、松本は慶應に通う18歳の高校生、その面会が初対面となった。
<参照>・細野晴臣はジミヘンの「ファイアー」と「紫の煙」を完コピして松本隆のオーデションに臨んだ
慶応大学に進んだ松本が、バーンズのドラマー兼マネージャーとしてディスコのハコバンなどの仕事をしていた時、複数のバンドを掛け持ちしていた細野からフローラルに参加しないかと声がかかった。松本はオーディションを受けて、正式に加入することになった。
そこからフローラルはメンバー・チェンジを経て「エイプリル・フール」へと発展するが、その年の9月にアルバム『Apryi Fool(エイプリル・フール)』を出すと同時に解散してしまう。

●この商品の購入はこちらから
小学生の頃からストラヴィンスキーやラヴェルを聴いていた松本は、中学3年でビートルズに出会って、「こんな面白いものがあるんだ」と直撃をくらったことからバンドを始めた。その一方では宮沢賢治と中原中也に傾倒し、ジャン・コクトーやランボーなどの詩を詠む読書家でもあった。
作詞を始めるきっかけはバーンズ時代のことで、「お前はいつも本を読んでるから詞を書け」と細野に言われたことだった。
それまでは音楽好きな自分と本好きの自分は平行していたらしいが、細野の言葉によって初めて「読書と音楽が交差した」のである。
しかし、エイプリル・フールのアルバムでは「外国にも出ていきたいから英語でやるべきだ」というメンバーの要望で、英語の歌詞がほとんどになってしまった。松本は心のなかで日本語でやりたいと思っていたので、細野に対して「次は日本語でやらせてくれ」と言っていた。
ぼくは自分の内面の何かを引き出すのが歌だと思っていたから、そこに翻訳が媒介すると、ワン・クッション入るわけですから、そこでパワーを失ってしまう。だから英語はなるたけやめたい。学校教育の何年間かでわずかに覚えた言葉よりも生まれたときからしゃべったり聞いたりしてきた日本語のほうが語彙も多いし、使いこなせる。使いこなせる言葉で書いたほうが説得力を持つと主張したんです。
細野と松本はエイプリル・フール解散後、大瀧詠一と鈴木茂の4人で「ヴァレンタイン・ブルー」を結成し、70年の春になってそれを「はっぴいえんど」と改名した。
松本ははっぴいえんど時代について、「“ことば”や“うた”を通して、生や死など人間の本質に関わる問題について答えを出そう」という思いで、作詞に取り組んでいたと語っている。
それまでの歌謡曲やフォークは、恋や青春などのキーワードを並べただけのラブソングが多くて、僕にとっては絵空事だったんです。はっぴいえんどでは、安直なラブソングではなく、身近にある風景や出来事を愛おしく想う気持ちを表現することを心がけました。だから、「夏なんです」や「風をあつめて」は僕にとっての“ラブソング”です。「夏なんです」は、地面との距離が近くて、空は高くて広いという少年の目線で夏休みや入道雲への愛情を素直に表現できたんじゃないかな。
しかし1973年に入ったある日、松本は細野から「解散するって決まった」と言われてしまった。はっぴいえんどは3年間の活動で3枚のアルバムを発表したが、新しい日本語のロックを創りだして音楽シーンに影響を与えてその役目を終えたのである。
初めてバンドの解散を知らされた松本は、サラリーマンになることも考えたというが、生活していくためには作詞家になるほうが早いと思い直した。そこで知り合いのディレクターたちに、「作詞家になる」という宣言をしている。
はっぴいえんどのレコーディング・エンジニアだった吉野金次にも、「コマーシャル・ソングが書きたい」と具体的な相談してみた。
その時に吉野は「わかりました」と答えたが、コマーシャル=商業的な音楽だと勘違いしたらしい。まもなくして香港からやってきたアグネス・チャンの作詞という、はっぴいえんどとはフィールドが違う世界の仕事を紹介してくれた。
アグネス・チャンの作品を書くにあたっては、「とにかくやさしく。誰でもわかるように」と心がけたという。そして1974年3月に発売されたアルバム『アグネスの小さな日記』のために書いた作品から、「ポケットいっぱいの秘密」が高く評価されて、シングルのA面に抜擢されたのである。
それがヒットしたことによって松本には歌謡曲の作詞家という、思わぬ道が急速に開けていくことになった。しかもこの時にスタジオ・ミュージシャンとしてレコーディングを担当したのが、はっぴいえんど解散後に細野がギターの鈴木と結成した「キャラメル・ママ」で、ドラムが林立夫、キーボードが松任谷正隆というメンバーだった。
それはどこかで将来の運命的なつながりを感じさせる出来事でもあった。

●この商品の購入はこちらから
女の子の気持ちを女の子以上に表現できる作詞家として活躍する松本には、生まれつき心臓が弱くて病弱だった妹がいた。松本は小学校に行く時にいつも妹の分まで、ランドセルを肩に担いで一緒に通学していたという。
女の子用の赤いランドセルを持ってると、当然のことだが友達にからかわれることになった。だが病弱の妹をいつも思いやり、ときには妹の気持ちになって考えて、彼女が喜ぶことをしてあげるのは兄として当然のことだった。
「なんで俺はこんなことしてるんだろう」と思うんだけど結局、そういう妹と一緒に育っていくわけですから。普通の人よりも、生と死の境界線みたいなものが、日常の中で畳の目のようにあるわけです。そういうのを感じやすくなっていたんですよね。僕には、妹が持てないランドセルまで持ってあげることが身に染みついているから、歌手のために何かするっていうのも自然なことでしたね。だから、これが天職だったんだと思います。
松本は1975年に太田裕美のために作った「木綿のハンカチーフ」で高い評価を得ると、そこからさらに歌謡曲の世界における作詞に没頭してスキルを磨き、次々に新鮮な作品を発表して成功を収めていく。それが27歳から28歳にかけてのことだった。
さらに1980年代に入ってからはソング・ライティングのパートナーとして、細野や大瀧というかつての盟友たちと組む一方で、松任谷由実などともコンビを組むことが増えて、松田聖子を筆頭とするアイドルやスターたちを輝かせるプロデューサーとしての存在感を増していった。
(注)本コラムは2016年4月2日に初公開されたものの改訂版です。
なお本文中の松本隆氏の発言は「松本隆対談集 風街茶房 1971-2004」(立東舎」からの引用です。

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから