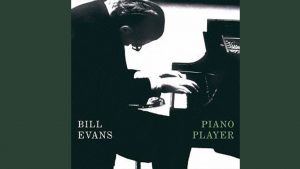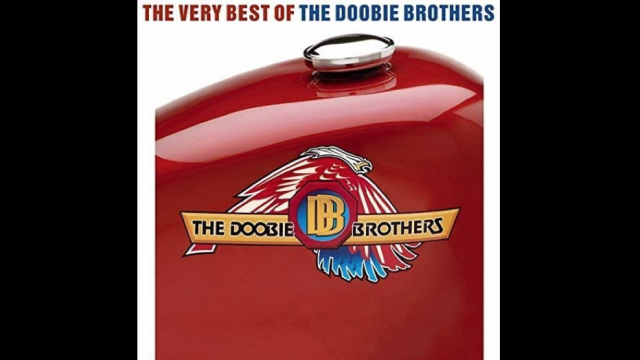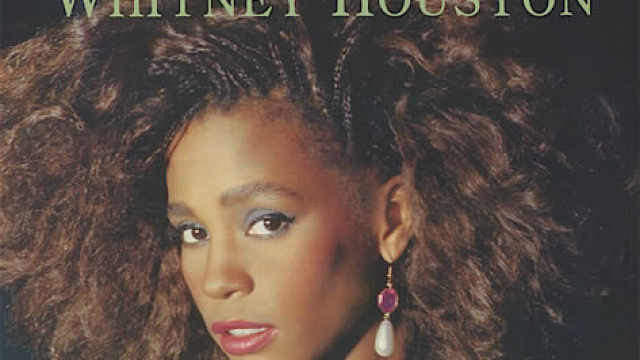2015年の6月11日の朝、従来のジャズの演奏スタイルを覆した“ジャズの革命家”が、ニューヨークのマンハッタンで死去した。家族の代理人によれば、死因は心不全。85歳だった。
その訃報を受けて、ジム・ジャームッシュ監督の『ストレンジャー・ザン・パラダイス』『ダウン・バイ・ロー』、ヴィム・ヴェンダース監督の『パリ、テキサス』、デヴィッド・リンチ監督の『ワイルド・アット・ハート』などへの出演でも知られる、俳優にして音楽家のジョン・ルーリーが自身のFacebookに追悼文を綴った。
まだ私がサックスを吹き始めた頃に、オーネット・コールマンを知ったわけだけど、彼には元気づけられた。こっちなら行けるって道を俺に示してくれたんだ。私はウースターの公共図書館でジャズに関するものならなんでも探しまくって、彼とセシル・テイラーについての本を見つけた。
どういうわけか、オーネットが言ってたこの言葉が俺から離れなかった。
“失敗してもいいんだって分かった時に、だったらやれるって思った”
この言葉が深く刺さったんだ。うん、まったくその通り。自分以外の誰にも分かんなくたって、こんなのただのメチャクチャじゃないかって思われたって、間違ってもいいんなら何ものかには近づける。
自由気ままにアドリブを繰り広げているように思えるジャズにも、実は伴奏とソロの区別や、予め決められたフレーズの長さやコード進行などの“ルール”がちゃんと存在する。
そんな“ジャズの約束事”を無視して、自分の思ったままに演奏し、新しいジャズ=フリージャズを創り出した天才が1950年代末に出現した。
オーネット・コールマン。アメリカ合衆国テキサス州フォートワース生まれのアルトサックス奏者だ。
アルトサックスの他にもトランペットやヴァイオリンもこなし、1960年代〜70年代初頭に黄金期を迎えた“フリージャズの時代”を牽引した人物である。彼のアドリブラインには旋律があり、ハーモニーがあった。
1959年にアルバム『The Shape of Jazz to Come(ジャズ来るべきもの)』を発表し、賛否両論を巻き起こした。
「これはジャズなのか?」「破壊の音楽なのか?」と、当時はオーネット・コールマンの音楽を理解できる人は少数派だったという。1961年にリリースしたアルバム『Free Jazz』では、彼が率いる8人のミュージシャンが2つのグループに別れ、誰彼なく自発的に旋律を奏でたり、合いの手を入れたりと、延々40分間にわたってフリーな演奏を続けたというから驚きだ。
しかしコールマンが無視したのは、いわゆる西洋音楽のルールだけで、自らのアイデンティティ=黒人音楽の内なる声には忠実だった。その演奏には心の底から湧き出すようなメロディーがあり、その何ものにもとらわれない旋律は、音楽的にも社会的にも“自由”を希求するメッセージそのものだった。
1970年代後半からはエレクトリックジャズの領域にも手を染め、“フリーファンク”とも呼ばれるファンキーなアルバムを制作した。この頃に“ハーモロディクス理論”という独自の理論を考案する。
1991年には、ウィリアム・バロウズの長編小説を映画化した『裸のランチ』の音楽にも参加。2001年には、高松宮殿下記念世界文化賞を受賞。(ジャズミュージシャンでこの賞を受賞しているのはオーネット・コールマンとオスカー・ピーターソンのみ)2007年には、ピューリッツァー賞、グラミー功労賞を受賞。
──最後に、作家の村上春樹が綴った印象的な言葉をご紹介します。
昔、ヴェトナム戦争が続いていたころ、煙草の煙がたちこめる新宿あたりのジャズ喫茶では、多くの若者が眉をひそめて息を凝らし、真っ黒なJBLユニットから大音量で叩き出されるオーネット・コールマンの音楽に聴き入っていた。まるでその音符の暗号的洪水の中から、重要なメッセージを摑みとろうとするかのように。当時、オーネット・コールマンを聴くという行為には、大江健三郎を読んだり、パゾリーニの映画を見たりするのと同じような、特殊な肌触りがあった。
<引用元『ポートレイト・イン・ジャズ』(新潮文庫)/村上春樹・和田誠著>

Shape of Jazz to Come

Free Jazz
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから