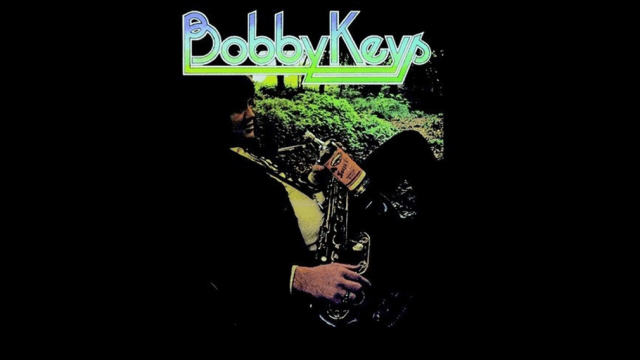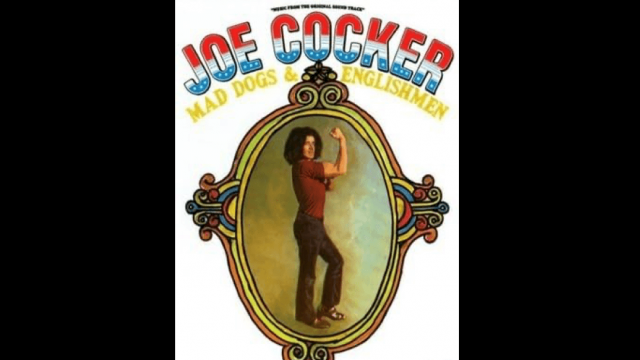1969年は、ローリング・ストーンズにとって一つの大きな転機だった。
6月にはリーダー的存在だったブライアン・ジョーンズが、度重なる問題行動によって解雇され、一ヶ月後の7月3日に27歳で亡くなった。
それと入れ替わるようにして、新たなギタリストのミック・テイラーが加わり、ストーンズは新たなバンドサウンドを確立させつつあった。
この頃にミック・ジャガーとキース・リチャーズが、これからのストーンズに必要だと考えていたのが、ホーン・セクションだ。そんなときにサポートとして加わったのが、テキサス出身のサックス・プレイヤー、ボビー・キーズだった。
ストーンズとボビーの出会いは、1964年に遡る。その年、初のUSツアーで全米各地を回っていたストーンズは、テキサスでボビーと同じステージに立っている。両者が出会う前、ボビーのストーンズに対するイメージは非常に悪かったという。
当時の俺は、「ラバー・ボール」ってヒット曲があったボビー・ヴィーって男と組んでいて、<やつら>が登場するまでプログラムのメインを張ってたんだ。それが、こいつらがメインっていうじゃないか。ここはテキサス州だぞ、ちきしょう。俺のホームグラウンドなのに。
また、この年にストーンズの「ノット・フェイド・アウェイ」がヒットしていたことも、イメージダウンに拍車をかけていた。「ノット・フェイド・アウェイ」のオリジナルは、テキサス出身のバディ・ホリーだったからだ。
ボビーの目には、バディ・ホリーの歌を勝手に自分たちのものにして、アメリカでも金儲けしようとしている侵略者のように映っていた。
しかし、ストーンズの音楽を生で聴いて、印象が一変した。
バディ・ホリーを歌うイギリス野郎たちが縄張り荒らしに来た! ちきしょう! しかし、これが、肌で感じちまった。びりびり感じちまった。知らぬまに顔をほころばせて踊っちまったよ。
ボビーがストーンズの音楽に加わるようになったのは、1969年12月にリリースされた『レット・イット・ブリード』からだ。プロデューサーのジミー・ミラーが、「リヴ・ウィズ・ミー」をレコーディングするときに呼び寄せたのがボビーだった。
その年の12月上旬。ストーンズはUSツアーを終え、さらにマッスル・ショールズ・サウンド・スタジオで「ブラウン・シュガー」「ワイルド・ホーシズ」「ユー・ガッタ・ムーヴ」の3曲をレコーディングして、イギリスへと戻ってきていた。
そんなある日、ミックはボビーとその相棒、トランペットのジム・プライスにナイトクラブで偶然出くわす。2人はエリック・クラプトンやジョージ・ハリスンらとともに、デラニー&ボニーのツアーに同行していて、たまたまイギリスに来ていたのだ。
ミックとキースはすぐさまアプローチをかけ、セッションの約束を取り付ける。日付は12月18日、その日はキースの誕生日であり、ボビーの誕生日でもあった(二人は同じ年の同じ日に生まれている)。
ロンドンのオリンピック・スタジオでは、誕生日パーティーもかねてセッションが行われたのだが、「ブラウン・シュガー」はレコーディングこそ終わっていたものの、間奏部分をどうするかはまだ決まっていなかった。ボビーはちょっと吹かせてくれよと自ら名乗り出ると、素晴らしいサックスソロを披露する。
ボビーが、これからのストーンズの音楽に必要不可欠であることが証明された瞬間だった。キースは自伝でそのときのことをこのように振り返っている。
お前は最高だ。ボビー・キーズ! ボビーが「ブラウン・シュガー」でサックスを吹いた69年12月のセッション。とびきりの楽しい時間だったよ。
1971年1月にリリースされた『スティッキー・フィンガーズ』は、ボビー・キーズとジム・プライスによるホーン・セクションによってサウンドの厚みが増し、イギリスとアメリカをはじめ世界中で大ヒットし、各メディアから高い評価を集めた。
その後、ボビー・キーズはストーンズとのツアー中に、ホテルでバスタブをドンペリで満たすという豪快な問題行動を起こし、一時はサポート・メンバーから外されていたが、1989年に復帰してからは、2014年12月2日に70歳で亡くなるまで、サポート・メンバーとしてストーンズのサウンドを支え続けるのだった。
参考文献:
『キース・リチャーズ自伝 ライフ』キース・リチャーズ著/棚橋志行訳(楓書店)

スティッキー・フィンガーズ

BOBBY KEYS – OFFICIAL RELEASE (2016 REMASTERED)
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから