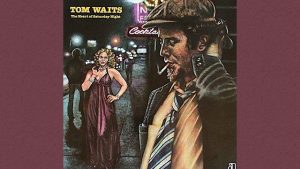この歌は京都出身のシンガーソングライターの尾崎亜美が、17歳で歌手デビューのチャンスを手にした杏里のために書き下ろした楽曲だ。
神奈川県立希望ヶ丘高等学校(定時制)に通っていたの美しい少女のデビューシングル「オリビアを聴きながら」は1978年11月5日にリリースされた。
尾崎と杏里が初めて会ったのは、その年の春だった。
方や当時16歳の人気モデル、方や21歳にして既に“ヒットメーカー”として注目され始めていた実力派ソングライター。
「創作に取りかかる前に彼女と会って打ち解けて話したい。」と、尾崎は担当者にリクエストをだした。
その頃、尾崎は上京以来“間借り”して暮していた街・六本木から白金台にあるマンションに引っ越したばかりだった。
尾崎は杏里を新居に招待し、16歳の少女がリラックスできるように手料理をふるまったという。
「普段はどんな音楽を聴いているの?」
「オリビア・ニュートン・ジョンが好きです。」
趣味の話、恋愛の話、将来の夢の話…二人の会話は弾んだ。
その後、尾崎はすぐに作曲にとりかかる。
年齢よりも大人っぽくみえた杏里が時折見せた年相応のあどけなさと、自然体でやわらない表情。
その印象から尾崎は、ある女性の姿を想像し、歌を作り上げてゆく。
一人暮らす部屋で、オリビアの曲を聴きながら自分を見つめ直す。
少し前に別れたばかりの恋人を強く拒絶している…。
尾崎は作曲当時のことをこんな風に振り返る。
「歌詞のハイライトで使っている“二度とかけてこないで”という強い言葉も、彼女の柔らかい空気感があれば、とんがった印象は残さない。彼女の笑顔が、逆に強い女性を描く勇気を与えてくれたんです。」
女性が男性を“振る”という設定の歌詞自体が珍しかった当時、10代の女性歌手のデビュー曲としては異例の作品となった。
杏里自身も、この歌を受け取った時は少し戸惑ったという。
いわゆる“箱入り娘”だった彼女は、当時帰宅が遅くなると仕事の現場や遊び場まで、わざわざ兄が迎えにきていたという。
歌詞の内容は何となくイメージできるが、深く感情移入してまでは歌えなかったという。
「まだ10代で、ちゃんとした恋愛経験がなかったこともありますが、詞の意味が深くて、どんな風にも解釈できたから難しかった。自分なりに理解できたのはずいぶん後になってからでしたが、今や私の人生における“大切な財産”となってます。」
実は尾崎はこの歌を杏里のために書きながら、同時に“自分へのエール”も込めていたという。
京都出身の尾崎が“心の景色の原点”という東京・六本木。
どうして六本木なのだろう?
あの有名なアマンド前の交差点から芋洗坂を下る。
今は飲食店ばかりが並ぶエリアだが、1977年頃はまだ閑静な住宅街が残っていた。
その年、まだ地元京都にいた尾崎はもともと病弱なのに過労がたたり、40日間の入院静養を経験したという。
この入院を機に、彼女は一念発起し、音楽活動の拠点を東京に移す。
初めての一人暮らし。
「弱い自分とさよならしたくて、相当な覚悟を決めた上での上京でした。だから、一番東京らしく思える騒々しい場所を選んで自分を追い込んだんです。」
知人の持ち家の1階に間借りをした。
7畳の寝室と3畳の台所。
陽当たりはよくないが、緑に囲まれ、静かで古びた感じがどこか京都を思わせた。
彼女にとって、その部屋こそが“自分が自分らしくいれる場所”となった。
だが、一歩外に出ると彼女は都会暮らしの中で日々葛藤していた。
近所の高級スーパーに買物に出かけ、食材を買い物かごに入れるが…会計の前に気持ちがくじけて中身を売り場に戻す。
そんな毎日をくり返していたという。
「京都に帰りたい…」
そんな時期に手掛けたのが、この「オリビアを聴きながら」だった。
歌の主人公が暮らす部屋は、白金台に引っ越す直前まで尾崎が住んでいた芋洗坂の部屋をイメージした。
「本当は弱くて誰かに頼りたくなってしまう…だけど、そんな自分を変えたい。自立した人間になりたい。」
尾崎は、自身のそんな願いを歌詞に登場する女性像に託した。
曲を作りながら自分自身を見つめ直した。
そして彼女は気づいたという。
「自分が自分らしく闘っていくための武器は、音楽しかないんだ。」
<引用元・参考文献『うたの旅人 Ⅱ』/朝日新聞be編集グループ(朝日新聞出版)>