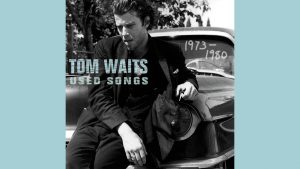1933年2月21日、彼女(出生名:ユニース・キャスリーン・ウェイマン)はノースカロライナ州にあるトライオンという小さな町で生まれた。
時代は大恐慌の真っ只中、貧しい家庭には男4人女4人の兄妹がいて、彼女はその中の6番目の娘だった。
「私が生まれたのは朝の6時だったと聞きました。父はかつての生業から離れて2年も経っていたのに、私の出生届には自分の職業を“床屋”と書いた。母は私を産むその週まで働いていたのに“専業主婦”と書き込んだ。彼らにはまだそんな誇りがあった。父は私が生まれて間もなくコックの仕事をし始めました。」
彼女の母親は熱心なクリスチャンでメソジスト派の牧師も勤めたことがあったという。
そのため、彼女の家では賛美歌を歌うためにピアノやオルガンによる音楽が日常的に演奏されていた。
「私の人生が始まった頃の記憶といえば、母がいつも歌っていたことだ。母が歌っていたのは教会のバイブルクラスで歌われる“I’ll Fly Away”や“If You Pray Right”など。それらが私の幼年期のサウンドトラックだったわ。」
それは彼女がまだ二歳半の時の出来事だった。
彼女がピアノの椅子によじ登ってお気に入りの賛美歌“God Be with You Till We Meet Again”をFのキーで弾いている姿を母親が見て仰天したという。
二歳半の娘が、誰も教えていないピアノを一つのミスもなく弾きこなしていたのだ。
父親はただ微笑みながらうなずいていた。
「神様はこの子に音楽の才能をお授けになったのだ…」
幼い頃の彼女にとって音楽は日常生活の一部で、息をするのと同じくらい自然なことだったという。
母の歌の上手さ誰もが認めるもので、父もまたピアノの他にギターやハーモニカを弾きこなせた。
兄や姉たちもみんなピアノを弾き、地元の聖歌隊やゴスペルグループに加わり、様々なイベントなどで歌を披露していた。
当然ながら彼女も姉らと共にザ・ウェイマン・シスターズというコーラスグループを組み、各地の教会で演奏活動を行うようになる。
「いわば家族全員がミュージシャンだったけど、誰もちゃんとした訓練を受けたわけじゃなかった。幼い子供が歩くことやスプーンで食べることを覚えるのと同じように、私たちにとって音楽は自然に身についたものだった。」
信仰心の強い母親は、宗教的ではない(世俗的な)音楽のことを一種類の呼び方しかしなかった。
母親はその音楽のことを“本当の音楽”と呼んだという。
「私がどこかで耳にした曲を弾いていると“そういう本物の音楽を弾くんじゃありません!”と母によく言われたものでした。ブルースやジャズは母にとって娘に触れて欲しくないものだったのだろう。」
彼女が5歳になった頃、母親は家計を助けるためにミラー夫人という白人の屋敷の家政婦の仕事を始める。
彼女は時々母親について行き、夫人の家で過ごさせてもらうことがあった。
「ミラー夫人は私が生まれて初めて親切に口をきいてくれた白人でした。彼女はいつも優しく、美しく真っ白な髪の毛をしていた。私はその髪が大好きだった。」
ある日、ミラー夫人は町の教会で彼女が聖歌隊の伴奏でピアノを弾いている姿を見かける。
ミラー夫人は彼女の母親に「あれだけ才能があるのに、ちゃんとした音楽の教育を受けさせないのは罪だ」と忠告した。
母親はありがたく言葉を受け止めながらも、我が家にはその教育を受けさせる余裕がないと、ありのままを話した。
それを聞いたミラー夫人は、数秒間だけ考えを巡らせて…すぐに解決策を思いついた。
「私が1年間だけのレッスン費用を工面します。1年経って彼女に見込みがあるのなら、さらにレッスンを継続させる道を何らかの形で探すことにしましょう。」
彼女は8歳から地元のピアノ教師からピアノのレッスンを受け始め、すぐに天才ぶりを発揮するようになる。
ミラー夫人の期待通り才能を開花させた彼女のために、今度はピアノ教師が「ユーニス・ウェイマン基金」を設立する。
彼女はそのおかげで高校を卒業後、ニューヨークの超名門校ジュリアード音楽院に入学してピアノと音楽理論を学ぶ。
その後、紆余曲折を経て、唯一無二のアーティスト“ニーナ・シモン”となって羽ばたいていく…
<引用元・参考文献『ニーナ・シモン自伝―ひとりぼっちの闘い』ニーナ・シモン(著)ステファン・クリアリー(著)鈴木玲子(翻訳)/ 日本テレビ放送網>