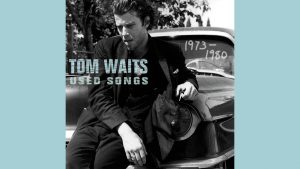越路吹雪は日本の元号が「昭和」になる前、大正13年(1924)に生まれた。戦中から戦後は宝塚男役スターとして活躍し、1951年に宝塚を退団した後は、“日本のシャンソンの女王”と呼ばれるまでとなった稀代の歌手であった。
独身時代は“恋多き女”といわれ、作家・三島由紀夫の恋人として取り沙汰されたこともある。作曲家の内藤法美との結婚後は、内藤がステージの構成や作曲などを手がけ、彼女が亡くなるまで連れ添った。そして1980年11月7日、胃がんのため56歳でこの世を去った。
越路吹雪にはいくつもの浮世離れした逸話が残っており、その“伝説”は今も語り継がれている。今回は伝説の歌姫とシャンソン、そしてエディット・ピアフとの出会いにまつわるストーリーを紹介します。
──フランス留学の経験もあり、声楽家創作オペラ協会会長でもあった佐藤美子は、越路吹雪が歌うシャンソンについてこんな言葉で礼賛している。
「日本人のシャンソン歌手といったら大半が外国人のマネですが、越路さんは“日本のシャンソン”が歌える貴重な人です。」
越路のシャンソンを聴いて、「パリのムードを感じる」と言う人は少ない。それはまさに、日本語で日本人に聴かせるための“越路シャンソン”だった。もっと正確に言うと、フランス産のシャンソンを“越路節”という自己流の歌い方で、日本風にくずして歌った人とも言える。
越路吹雪の盟友であり、マネージャーでもあり、越路が歌うほぼ全てのレパートリーの訳詞・作詞を手掛けた岩谷時子は、1953年に越路(当時28歳)が初めてフランスに一人旅をした際に送ってきた手紙を、ずっと大切に保管していた。
「私は日に二、三回ずつ腹を立て、毎日パリの何かしらに抵抗し、自分の何かしらと闘って過ごしています。このまま長くパリにいてキャバレー歌手になって暮そうかと思うけれど、フランスのシャンソンはフランスだけのもの。そのメロディーは世界で歌われていても、フランス人の歌うシャンソンは彼らの生活から生まれた歌なんだからフランスだけのものよ」
当時、まだ“越路節”も未完成であったと思われるが、この頃からすでに「所詮本物のシャンソンはフランス人にしか歌えないもの」と悟り、自分流のシャンソン、日本のシャンソンを歌ってやろうとしたたかに模索していた。
その後、何度もパリへ足を運んだ越路は、本場のシャンソンに刺激を受けながら、自問自答を繰り返し、歌に磨きをかけていく。そんな姿を一番身近で見ていた岩谷は、当時のことをこう振り返っている。
「彼女が本格的にシャンソンを唄おうとしたのは、1953年にエディット・ピアフの歌を聴いてからです。当時、ピアフはパリで全盛期を迎えていました。ピアフとの出会いが越路吹雪という歌手の人生に重い意味を持たせたと言ってもいいでしょう」
1953年4月9日、たった一人で羽田を出発した越路は、11日パリに到着する。当時、パリにいた評論家の小林秀雄、作家の今日出海(こんひでみ)、東和映画の川喜多長政の三人に出迎えられた。
宝塚から飛び出した越路を預かっていた藤本プロダクションの藤本真澄が、パリにいる小林たちに前もって頼んでいたのだ。
「フランス語のできない奇々怪々なのが行くからよろしく。」
当時、越路は宝塚を出たものの、芸の壁にぶつかり、パリに行けばその壁も打開できると期待していた。到着した翌日、小林たちに連れられて、初めて本場のシャンソンを聴きに行く。越路の日記にはこんな言葉が綴られていた。
「シャンソン歌手の男の人は、ジェスチャーが大きすぎて、私ですらしんどかった。ダメ、パリの良さがわからない。飛行機があまりに早く私をパリに運びすぎたようだ」
4月21日の夜、パリ在住の日本人シャンソン歌手・石井好子とバーでシャンソンを体感した時も、こんな感想を綴っている。
「ピンとこない。歌を喜びとする私がシャンソンを聴いてもピンとこないとは。どれを見てもフィーリングなし」
その翌日(4月22日)、越路は本物を聴くこととなる。
「オーケストラの良さ、彼女の歌う時のジェスチャー、曲のアレンジの素晴らしさに私は悲しむ。パリの良さが少しずつわかってきた!」
2回目にピアフの歌を聴いたのが5月7日の夜だった。この時の日記がショックを物語っている。
「ピアフを二度聴く。語ることなし。私は悲しい。夜、一人泣く。悲しい、淋しい、私には何もない。私は負けた。泣く、初めてパリで」
数日後、日本にいる岩谷宅の郵便箱に、一通の手紙が送られてきた。
「私の歌には内容がない。私は月夜の蟹だ。」
越路はその後、ピアフが歌ったシャンソンの楽譜を片っ端から買い込んだ。他界した後に見つかったその楽譜には、所々に簡単な訳詞や、衣装のデザインが書き込まれていた。当時、パリのホテルで書いたものらしい。こうして越路吹雪は、エディット・ピアフとを体験、吸収していったのだ。
以来、彼パリに行くたびにピアフの舞台を観る。それはピアフが晩年、肉体も声も衰えてしまった時期まで、最後の最後まで客席で見届けたという。
1963年10月11日、ピアフがこの世を去った日も、越路は偶然パリに滞在しており、その訃報をリトル・サボイというホテルの部屋で知った。
──ピアフと越路。この二人は直接会って話したことはない。1971年の11月、日生劇場で初のドラマティックリサイタル『エディット・ピアフの生涯』で、越路がピアフを演じることとなる。
この作品で初めて、演出家・浅利慶太(劇団四季の創設者の一人)と出会う。翌年再演された同公演で、越路はピアフの「愛の讃歌」を歌い、芸術祭優秀賞やゴールデンアロー賞などを受賞する。
その後、何度も再演された『エディット・ピアフの生涯』の主役を演じ終えた日の舞台裏で、浅利は冗談まじりにこんな事をつぶやいた。
「越路ピアフか、それともエディット吹雪か」
地獄耳と言われた越路が聞き逃すわけがない。化粧台の前で知らん顔をしていた彼女は、煙草を吹かしながら横目で浅利をにらみつけた。その目は、こんな風に語っていたという。
「冗談じゃないわ。わたしは私。ピアフはピアフよ。」
(引用元・参考文献:『聞書き 越路吹雪 その愛と歌と死』江森陽弘著・朝日新聞社)

越路吹雪 シャンソンの世界

愛の讃歌‐ピアフを歌う‐
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから