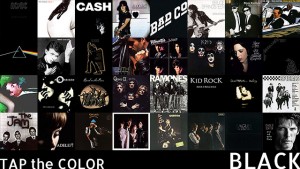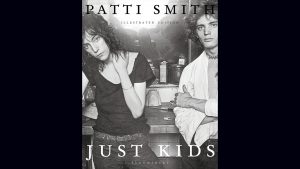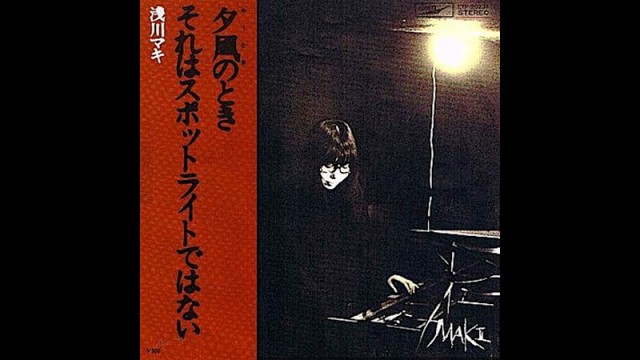レナード・コーエンの代表曲「Bird On The Wire(電線の鳥)」は、こんな一節から始まる。
電線の上の一羽の鳥のように
真夜中の聖歌隊の酔っぱらいのように
俺は自分なりのやり方で自由になろうとした
1967年、33歳で遅咲きのデビューを果たしたコーエンは、1950年代後半から約十年間にわたって、漂泊の日々を過ごしていた。
故郷カナダのモントリオールからニューヨークへと移り住み、ロンドンへと流れ、その後ヨーロッパ各地やキューバ、そしてまたアメリカへと身を移しながら詩を紡ぎ、曲を創り、小説を執筆していた。
デビューの翌年、ナッシュビルでレコーディングされたこの歌は、ボブ・ディラン、ジョニー・キャッシュを手がけたボブ・ジョンストンがプロデュースを担当した。
それから四半世紀の時が流れ、当時61歳を迎えたジョニー・キャッシュがリック・ルービンのプロデュースのもと、この曲をレコーディングした。それはキャッシュがこの世を去るちょうど十年前の1993年の出来事だった。
生前、数多くの曲をカバーし歌ったジョニー・キャッシュだったが、レナード・コーエンの作品を取り上げたのは、後にも先にもこの一曲だけである。なぜこの曲を選んだかについて、キャッシュは多くを語ることなく逝った。
2歳違いだった二人は、それぞれのやり方で自由を求め、それぞれに神を信仰した。厳格なクリスチャンであった父親の影響もあり、キャッシュは生涯を通じて敬虔なキリスト教徒だった。
一方のコーエンはユダヤ系カナダ人であり、父親がユダヤ教の指導者(ラビ)として有名な人物であったことから、厳格なユダヤ教徒というバックグランドを持っている。30代後半から仏教(臨済禅)を学び、62歳の時に僧侶となり現在に至る。
キャッシュは、犯罪者をテーマにしたマーダー・バラッドからゴスペル(宗教音楽)までを歌う、対極性を持った稀少なアーティストでもあった。
コーエンも同じく、“エロティシズムの赤裸々な表現”と“禅の信仰”という、対極した世界観を持った詩人と言われている。
同じ時代を生きながらも、交わる事のなかった二人にとって、唯一の接点となる人物がボブ・ディランだった。彼らは各々にディランと出会い親交を深めた。そのディランがユダヤ教からキリスト教へ改教したことは有名な話で、そこに何らかの因縁を感じずにはいられない。
或る時、一本の電線に二羽の鳥が留まった。
その一羽は“漂泊の詩人”と呼ばれた鳥。
もう一羽は“黒服の男”と呼ばれた鳥。
個人の生き方が問われる今、電線の上から深遠なメロディが聴こえてくる。
“自分なりのやり方”で自由を求めた男達の歌声が聴こえてくる。
<解説>
60年代初頭、レナード・コーエンはガールフレンドのマリアンヌを連れて、ギリシャのイドラ島という小さな島に住み着いた。そこは水道設備すら整っていない不便な島だったが、いつしか作家や画家、詩人たちが住み着き始め、後にはアレン・ギンズバーグやブリジッド・バルドー、ソフィア・ローレン、ついにはケネディー一族までもが訪れることになる有名人たちの隠れ家的存在となった。
いち早く島の魅力に惹かれた彼は、古い家を買って創作の拠点とした。そして彼は、この島で「Bird On The Wire(電線の鳥)」を作った。
20代の後半だった或る日、窓の外を眺めていると、一本の電線に一羽の鳥が留っているのが目に入って思いついたというこの歌は、片思いに苦しむ孤独な男の心情が綴られている。歌詞の一部に「浮浪者が俺に言った、“そんなに多く求めてはいけない”そして美しい女が俺に叫んだ“さあもっと多く求めたらどうなの”」といった対照的な表現があり、レナード自身の奥に潜む難解な人格を垣間見る事ができる。
このような比喩や隠喩の言葉が並ぶ中、何をしても振り向いてもらえない悲しみや切なさが痛々しいほどに伝わってくる一曲だ。そこからは恋愛事情だけではなく、組織や社会に縛られず“自由になりたい”と願う、普遍的なテーマも読み取ることができる。

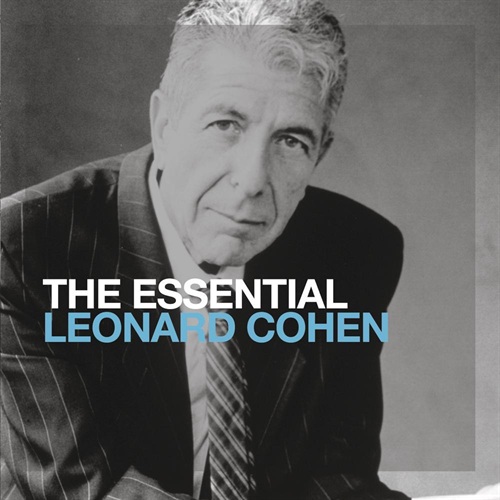

Songs From a Room
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから
執筆者
【佐々木モトアキ プロフィール】
https://ameblo.jp/sasakimotoaki/entry-12648985123.html