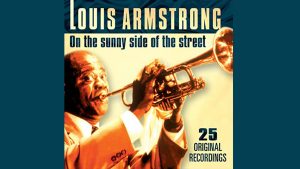1977年6月、27歳になったスティーヴィー・ワンダーはビルボード誌が後援したUCLAでのシンポジウムに出席し、こんな発言している。
「あの曲名は最初から思いついていたけど、曲の中ではいろんなミュージシャンを採り上げようと思っていた。素晴らしい仕事を遺したミュージシャンはたくさんいる。でも、すぐに忘れられがちだ。僕は自分の感謝の気持ちを示したかったんだ。」
その発言の8ヶ月前…スティーヴィーは18作目となるアルバム『Songs in the Key of Life』を発表し、その中に収録した一曲「Sir Duke(愛するデューク)」を亡くなったジャズの巨人デューク・エリントンに捧げている。
スティーヴィーは、それまで受けた数多くのインタヴューで、尊敬するアーティストとしてデューク・エリントンの名を第一に挙げるほどリスペクトをしていたという。
同曲は1977年にシングルカットされ、全米ポップチャート、R&Bチャートともに1位を獲得、さらに全英チャートでも2位を記録する大ヒットとなった。
さらにアルバムは、当時全米アルバムチャート14週1位となる大ヒットになり、グラミー賞の最優秀アルバム賞も受賞した。
当時、彼はこのヒットを受けてこんな言葉を残している。
「(私の曲は)憎しみより愛、戦争より平和、そこに多くの人たちが親近感を抱いてくれるのではないでしょうか。」
偉大なジャズピアニストでありバンドリーダーだったデュークは、1974年5月に75歳で亡くなっている。
それはスティーヴィーが17作目のアルバム『Fulfillingness’ First Finale』(1974年)を発表する直前のことだった。
それからまもなくして、彼は自分の音楽に多大なる影響を及ぼしたデューク・エリントンを讃える曲を作ろうと考えたという。
音楽はそれ自体がひとつの世界で
そこには誰でも理解できる言葉があり
みんなに歌い、踊り、手拍子を取る平等な権利があるんだ
彼が尊敬したデューク・エリントンといえば、ジャズ創成期の時代に作曲家兼バンドリーダー兼ピアニストとして大活躍した偉大なジャズメンである。
生涯3000曲以上の音楽制作に携わった彼のレパートリーの中でも、特に「Take the A Train(A列車で行こう)」は、時代を超えて今もなお世界中で親しまれている一曲と言えるだろう。
彼は白人社会がジャズを“下等な娯楽”と考えていた1940年代に、クラシックの殿堂カーネギーホールにおいて初めてジャズコンサートを実現した人物でもある。
白人ジャズと黒人ジャズの違いを強調し、自分の作品を“黒人音楽”と呼んで区別していた。
「黒人は聴衆を楽しませればいい」という風潮の中で、彼は「我々はアーティストであってエンターテイナーではない」と、毅然と言い放ったというエピソードも残っている。
そんな“姿勢”と類い稀な音楽的才能によって、彼はステーヴィーを始め後世の黒人ミュージシャン達の精神的支柱となってゆく。
彼を心から敬愛していたスティーヴィーは、亡き彼に捧げた曲の歌詞の中にカウント・ベイシー、ルイ・アームストロング、エラ・フィッツジェラルドといった黒人音楽家の名前を登場させ、彼らの才能と功績を讃えた。
唯一白人の音楽家グレン・ミラーを登場させたところも、ステーヴィーなりの平和的メッセージがあってのことだったと推測できる。
「盲目であることが不利だなんて思ったことはない。黒人であることを不利だなんて思ったことはない。僕たちは、自分の子供達が人種差別や偏狭、いかなる偏見をも経験しなくていいように、彼らの将来を守らなければならない。」(スティーヴィー・ワンダー)
音楽は知っているんだ
それが生活に切っても切れないものだと
そしてそこには時間を経ても忘れられない音楽の先駆者たちがいる
カウント・ベイシー、グレン・ミラー、サッチモ
そして全ての王者デューク・エリントン!
<引用元・参考文献『スティーヴィー・ワンダー ある天才の伝説』スティーヴ・ロッダー (著)大田黒泰之(翻訳)/ブルースインターアクションズ>