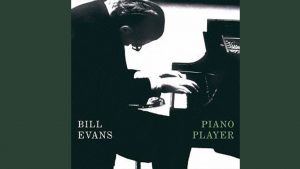作家の村上春樹は著書の中で、デューク・エリントンについてこんな風に綴っている。
天才というのは往々にして短気でせっかちで短命なものだが、彼はその才気溢れた人生を、まことに優雅に、まことにたっぷりと、まことにマイペースで生きた。見事に“生ききった”と言うべきか…。そしてその奇跡的なまでに豊かな音楽的水脈は、広い平野の隅から隅までを、余すことなく潤した。言うまでもなく、ジャズの歴史にとっては慶賀すべきことである。<引用元『ポートレイト・イン・ジャズ』(新潮文庫)/村上春樹・和田誠著>
1974年5月24日、デューク・エリントンはニューヨーク市内にある病院の一室で静かに息を引きとった。享年75。癌に冒され死期が近くなってからも病室で作曲を続けていたという。
印税などで莫大な収入を得ながらも、お金のかかるビックバンドを率いて晩年まで旅を続けていたのは、自分の頭の中にあるサウンドをすぐに実演したかったからだろう。
今日は“公爵(デューク)”の愛称で親しまれ、ジャズ界に偉大な功績を残した彼の足跡をあらためてご紹介します。
デューク・エリントン。ジャズ創成期の時代に、作曲家兼バンドリーダー兼ピアニストとして大活躍した男である。生涯3000曲以上の音楽制作に携わったレパートリーの中でも、特に「Take the A Train(A列車で行こう)」は、時代を超えて今もなお世界中で親しまれている一曲。
「“ジャズ”という言葉も問題の一部だな。この言葉からはニューオリンズの売春宿の連想が完全に消えないんだ。私たちがやっているのは黒人音楽と呼ぶべきなんだ」
「黒人は聴衆を楽しませればいい」という風潮の中で、デュークは「我々はアーティストであってエンターテイナーではない」と、毅然と言い放ったというエピソードも残っている。そんな“姿勢”と類い稀な音楽的才能によって、後世の黒人ジャズメンの精神的支柱となっていくのだ。
1899年4月29日にワシントンD.C.で生まれた。なぜ“公爵(デューク)”という愛称で呼ばれるようになったか? 一説では、父親がホワイトハウスの執事であったからだという。
また、子供の頃から身のこなしが優雅で、きちんとした服装をしていたことからつけられたという説もある。小学生の頃からピアノを習い始め、ハイスクールでは学校行事でピアニストとして抜擢されるほどの腕前だった。この頃に音楽教師から高度な作曲理論を学んだという。
「私の音楽に対する勉強は、G♭とF♯の違いを学んだことからはじまった」
後に彼が残した有名な言葉である。28歳から32歳まで、ハーレムにある『コットンクラブ』の専属バンドとして演奏をする。
30代の後半から錚々たるメンバーを率いて結成したデューク・エリントン・オーケストラは、今なおジャズを演奏する者にとって大きな影響をもつ歴史的なバンドとなった。
その特徴あるサウンドは、作曲法とも関係していると言われている。「A列車で行こう」の作曲者でもありエリントンの右腕でもあったピアニスト、ビリー・ストレイホーンがこんな風に語ったことがある。
「エリントンはピアノも弾くけれど、本当の意味で彼の楽器はバンド全体なんだ。バンドのメンバーの一人ひとりが明確に音色を演じ、彼はそれをぜんぶ混ぜ合わせて独自なスタイルを創る。自分の楽団一人ひとりのために作曲し、めいめい自然に、楽に演奏させ、エリントンはミュージシャンの心の奥の隅々まで探り、本人すら知らなかったようなものまで取り出してみせるんだ」
バンドに在籍しているミュージシャンたちの長所を見抜き、そこを伸ばすように作曲していたというのだ。自らの作曲や音楽制作について、自身が語った言葉も残されている。
「しばらくバンドの仲間に入っていると、その男の力量が聴こえるようになるんだ。一人の人間のサウンドはそのミュージシャンの全人格なんだ。曲を書くときにはそのサウンドが聴こえてくるんだ」
また、デューク・エリントン・オーケストラには楽譜がなかったという。デュークが曲を書き、それを聴いたメンバーがそれぞれハーモニーをつける。そこには音楽的には分析できない独特のサウンドが生まれていた。
自分の音楽を表現してくれているミュージシャンをとても大事にしていた。例えばドラッグをやっているメンバーがいて、周りから指摘を受けるようなことがあっても(注意はしても)、そのメンバーの生き方や人格を否定・非難することはなかったという。それもあってか、彼のオーケストラでは長く在籍したメンバーが多かった。
また、他の多くの黒人ミュージシャンがそうであるように、人種差別問題を生涯に渡って意識し続けていた。公の場での発言では優雅に、軽い内容の話が多かったが、常に音楽では主張していた。バンドに白人ミュージシャンが混じることはあったが、デューク・エリントンの曲は、どんなテーマに基づいて作曲したものであれ、つねに黒人の立場や考え方に寄り添ったものだった。
当時、人種差別が激しいアメリカの中で、黒人として生きるのはどういう事なのか?その音楽を通して訴え続けたのだ。
そんな彼を心から敬愛していたスティーヴィー・ワンダーが、1976年に「Sir Duke」という素晴らしい黒人音楽讃歌を発表する。それは“公爵(デューク)”がこの世を去って2年後の出来事だった。
音楽は知っているんだ
それが生活に切っても切れないものだと
そしてそこには時間を経ても忘れられない音楽の先駆者たちがいる
カウント・ベイシー
グレン・ミラー
サッチモ
そして全ての王者デューク・エリントン!

ザ・デューク・プレイズ・エリントン
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから
執筆者
【佐々木モトアキ プロフィール】
https://ameblo.jp/sasakimotoaki/entry-12648985123.html