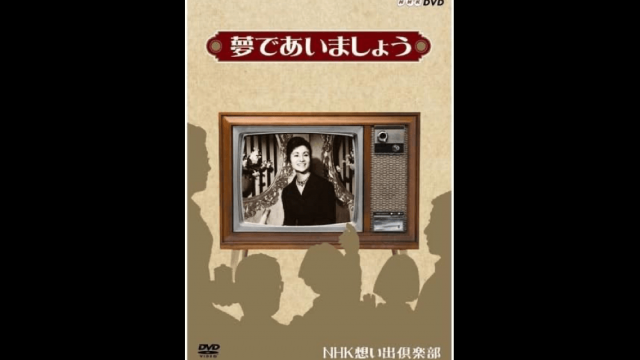黒柳徹子には小学校の時からなりたいものがいろいろあった。バレリーナ、幼稚園の保母さん、従軍看護婦、スパイ、競馬の騎手。だが、香蘭女学校を卒業後にはオペラ歌手になると、きちんと目標をさだめて東洋音楽大学声楽科へ入学した。
東京音楽学校でバイオリンとクラシック音楽を学んだ父の黒柳守綱は、昭和12年から5年間に渡って新交響楽団のコンサートマスターを務めたが、戦争のためにシベリア抑留を余儀なくされた。
しかし、1949年に帰国後はふたたび音楽家として活躍し、東京交響楽団やNHK交響楽団のコンサート・マスターを歴任した。ところが黒柳徹子は、クラシック音楽を教わっても思うように活動ができないと感じていた。
「そうだ、私はそのうち結婚してお母さんになる。その時、料理や洗濯や掃除が上手にできるお母さんはたくさんいるだろうから、私は自分の子どもに絵本を読んだり、人形劇をやってあげられるお母さんになろう」
そう決めたという。そこで、どこに行ったらそういうことを教えてくれるのかと母に訊ねると、「新聞に載っているんじゃない?」と言われたので見てみると、本当にNHKの放送劇団募集の記事があったので応募した。
しかし、筆記試験では25問中5問しかできず、実技の課題だったパントマイムもできなかった。にもかかわらず400倍もの競争を突破して、黒柳徹子は合格してしまったのである。
それは「あまりにもなにもできなかった」ことに可能性を見出した養成所の先生たちが、特別枠で採用したことによるものだった。後に先生のひとりからは、こう教えられたという。
「テレビジョンという新しい世界の俳優には、あなたみたいな何もできない、何も知らない、言い換えると、無色透明な人が向いているかもしれない。一人くらい、そういう合格者がいてもいいだろうと思って、あなたは受かったんです」
ラジオでも舞台でも映画でもない、テレビという新しいメディアのための俳優をつくる養成所に入ったのは1953年の2月1日だった。それはNHK東京テレビジョンが本放送を開始した日のことで、まだラジオが全盛期だった頃である。
始まったばかりのテレビはわずか866台、1台につき5人ずつ観ていたとしても、視聴者が5,000人にも満たないという状態でのスタートだった。
それからおよそ1年後の1954年4月、ラジオの子供番組『ヤン坊 ニン坊 トン坊』に出演した黒柳徹子は、トン坊の声で主役を務めて人気が出て注目される。
続いてテレビでも幼児教育番組『おかあさんといっしょ』のコーナーとして始まった、ぬいぐるみを活用した『ブーフーウー』や、人形劇『チロリン村とくるみの木』といった人気番組で声優として活躍していった。
1960年に入ると日曜日の夜8時から始まった日本初のカラー放送によるバラエティ番組、四人のホスト(フランキー堺、ペギー葉山、越路吹雪、森繁久弥)が週替わりで登場する『パノラマ劇場』で、渥美清とともにレギュラー出演者となって認められた。
黒柳徹子の才能が一気に開花するのは1961年の春からのことで、なんと一挙に毎週3本のレギュラーが決まったのだ。このとき27歳だった黒柳徹子は、ここからの1年が彼女にとっても画期的な年となる。
子供向けの『魔法のじゅうたん』が水曜日の18時、音楽バラエティ『夢で逢いましょう』が土曜日の22時、そして日曜日は20時から生放送のバラエティ・ドラマ『若い季節』だった。やがて『若い季節』の人気が上昇し、半年遅れで『夢で逢いましょう』もまた、一世を風靡する番組へと成長していった。
東京の化粧品会社を舞台にした『若い季節』はバラエティ色の強い連続ドラマで、銀座をタイトルバックにザ・ピーナツの主題歌が流れるオープニングから、全国各地のテレビ視聴者には都会的なセンスを感じさせる魅力的な番組だった。
そのうえ〝人海戦術〟といわれたほど多くの出演者、レギュラーだけでなく準レギュラーがいた。ハナ肇とクレイジー・キャッツ、ダニー飯田とパラダイス・キング、坂本九、ジェリー藤尾、スパーク3人娘(中尾ミエ、伊東ゆかり、園まり)といった歌手たちと、淡路恵子、沢村貞子、有島一郎、三木のり平、森光子、岡田真澄、古今亭志ん朝と、NHKならではの豪華なキャスティングだ。さらに人気俳優からタレント、コメディアン、スポーツ選手までもが、タイミングをみてゲストとして出演していたのである。
なかでも人気が急上昇したのは浅草の軽演劇出身のおかしな役者の渥美清と、頭の回転と舌が一緒に動いて声もよく通って目立つ黒柳徹子だった。
『若い季節』や『夢であいましょう』は生放送でしたから、1時間分の台詞を覚えて、それを生でやるっていうのは出演者やスタッフ、みんなで力を合わせないと無理ですよね。だから本当にみんな仲良しでしたね。
『若い季節』には、エノケンさん(榎本謙一)から渥美清さん、九ちゃん(坂本九)、そしてクレイジーキャッツまで、色んな世代の方が出演していて、本当に賑やかで毎日がお祭りみたいでしたよ。
当日まで台本が出来上がらず、現場に行ってから一気に覚えて、割り勘でご飯食べて(笑)、それから本番。若かったと思いますね。でも、撮り直しが出来ないからこそ「やらなきゃ!」という情熱がありましたね。
黒柳徹子は渥美清とともに、音楽バラエティ『夢であいましょう』にもレギュラー出演した。土曜日の夜に『夢であいましょう』があり、日曜日のゴールデン・タイムには『若い季節』という流れになったので、毎週この二人を観ていれば自然に馴染みになってしまう。
テレビが生んだ新しい時代の人気者として、二人は同時期にコントや詩の朗読で存在感を発揮しくことになる。その頃に浅草で人気が出始めていた伊東四朗が、こう振り返っている。
「私たちコメディアンが当時憧れていたのは『夢であいましょう』。結局出られなかったけれど、出ている人が本当にうらやましかったですね」
「仲間たちの間でオシャレでカッコイイ番組だと評判でした。こういう番組を見ないと時代に置いて行かれると、1、2回見ました。とても優れた番組でショックを受け、自分が意味のない修行をしているんじゃないかと思ったほどでした」と語ったのは、まだ無名の修業時代だった萩本欽一である。
黒柳徹子は『夢であいましょう』(61~66年)にレギュラー出演したまま、最後の1年は司会も引き受けているが、構成を担当した永六輔との間にこんな会話が残っている。
黒柳:テレビが始まったときは、みんながスタートラインに立ったわけだから、言葉は変だけど「戦友」としか言いようのない気分です。仲間意識は強かったです。
永 :番組作りでは、アメリカに学んだ点もあります。米軍の知り合いやアーニー・パイル(東京宝塚劇場を米軍が接収した劇場)がバラエティー、レビューをやっていて楽しさを学びました。「夢で~」には、中村八大という天才的なメロディーメーカーがいましたから、音楽をいかしました。
黒柳:昔のカメラはクローズアップの時、近寄らなければ撮れなかった。これ以上、カメラが寄れないとなると、私の方から寄っていく(笑い)。だから、一心同体にならないと撮れない。生放送ですから俳優は全部せりふを覚えて、助け合いました。
永六輔と中村八大が作る「今月のうた」のコーナーからは「上を向いて歩こう」を筆頭に、「遠くへ行きたい」、「おさななじみ」、「こんにちは赤ちゃん」など、老若男女が口ずさめる口語体の新しい歌が生まれてヒットした。
音楽がぐっと私たちの日常に近づいたと思います。実は、その少し前、昭和33年(1958年)に最年少でNHK紅白歌合戦の司会をしたんですね。その時の出演者には、赤坂小梅さんなど丸髷を結った方もいらっしゃったんです。
『話し上手、聞き上手はいるが、対話の才能では日本で初めての人』と評価される黒柳徹子は、テレビというメディアとのマッチングの良さを抜きにしては語れない。
みんなが手探りの状態にあった黎明期のテレビでは、どうやれば正解なのかを誰もわかっていないという時代だった。しかもほとんどの番組が生放送だったから、ありったけの集中力で真剣勝負のように立ち向かっていくしかなかった。
私達は、手をとりあって、よくわからない〈テレビ〉という暗闇の中を進んでいった。だから、その頃一緒だった人は、みんな、同級生というか、同志のようなものだ。
やがて1964年の東京オリンピックを迎えて、黒柳徹子はテレビの黄金時代が始まると時代の最先端に立っていたのである。
〔注]本コラムは2016年6月4日に初公開されました。
〈参考文献〉黒柳徹子 著「トットチャンネル」新潮社、小林信彦 著「テレビの黄金時代」文春文庫

「トットチャンネル」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから