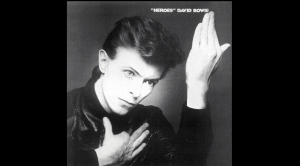それは1980年11月7日の出来事だった。東京・中目黒にある東京共済病院の待合室を、3人の男が慌ただしく駆け抜け、エレベーターの中に消えた。
待合室にいた数名の患者や付き添い人たちが「何ごとか?」と、走り去ってゆく男達の背中に一瞬視線を投げたが、数秒後には再び静かな待合室に戻った。
一時間後、その待合室の様相が一変する。大きなカメラを肩や首にかけた男達や、一目で報道記者とわかる腕章をつけた取材陣が待合室に集まりだしたのだ。
病院の前には、新聞社やテレビ局の旗をつけた車が並び、病院内や周囲にあった公衆電話は、彼らに占領されて殺気だっていた。
ゆっくりと開いたエレベーターのドアから、一時間前に駆け込んでいった男の一人が飛び出してきて、すぐ左側にあった赤電話のダイヤルを慌てて回し、受話器の向こうの相手に小声で伝えた。
「意識が不明で、先生や看護婦がマッサージをしているんですが……はい、時間の問題だと思います。はい!わかりました…すぐ来られた方が…はい!はいっ!」
その隣りで電話をかけていた腕章をまいた記者が、右手で受話器を押さえながら耳をそばだてている。電話をしていた男が受話器を置くと同時に、記者が早口で問いかける。
「越路さんでしょ? 容態はどうなんですか? 時間の問題なんですか?」
数秒後には報道関係者たちが男を取り囲む。
「ええ…」
うつむきかげんに応えて、男は足早にエレベーターに乗り込んでいった。
その頃、3階にある個室301号室では、医師と看護婦たちが7〜8人で、越路吹雪の全身をマッサージしていた。時々少しだけ開く唇からは、何を言おうとしているのか、言葉にならない言葉が溢れていたという。
そのやせ細った手先を、夫の内藤法美が握りしめている。やがて、彼女の身体からは何の反応もなくなった。
「コーちゃん!!」
付き添いの人たちの叫びにも似た呼びかけが病室に響く。最後に、ほんの一瞬だけ、そのノドが微かに動いたという。そこにいた全員が息をのむ。次の瞬間、脈をとり続けていた医師が目をつむった。
午後3時2分、“日本のシャンソンの女王”と呼ばれた稀代の歌手、越路吹雪が56歳でこの世を去った。
その日の夕方、彼女の亡骸は、渋谷区桜丘にあった自宅マンションに帰ってきた。マンションの前には報道関係者たちが群れをなして集まっていた。テレビニュースの速報でも、彼女の訃報が早々に流された。
それを見たファンたちがつめかけ、深紅の布で覆われた棺が車から降ろされると、つんざくような絶叫があちこちからあがった。
「コーちゃん!!」
午後6時過ぎには、越路の友人たちが自宅に駆けつけてきた。平幹二朗、淡路千景、久慈あさみ、ジョージ川口、乙羽信子……次々と姿をあらわす彼らを記者やテレビレポーターたちが取り囲み、無神経なフラッシュを浴びせマイクを向けていた。
涙声を震わせながらコメントする彼らの多くは、彼女のことを“コーちゃん”と呼び、“越路さん”という人はほとんどいなかった。
「コーちゃんが逝くなんて」
後日、彼女の死因は、胃癌から腹膜まで転移した末期癌だったと公表された。医者は本人に宣告をしていなかったという。
当時、越路吹雪は自分が癌に侵されていたことを知っていたのだろうか? とすれば、いつ頃から感づいていたのだろうか?
彼女が他界した後、最愛の夫だった内藤と生涯の親友でもあった岩谷時子は、この疑問を何度も自問自答したという。二人は口をそろえてこう言った。
「きっと知ってましたよ」
何故か? 夫の内藤があるインタビューでこんな言葉を残している。
「彼女は自分に嘘をつかなかったし、他人の嘘も見破る特殊な感覚がありました。第六感というのでしょうか?」
内藤は彼女に感づかれるのが怖かったのだ。彼女は舞台上の堂々としたイメージとは真逆で、とても精神的にもろいところがあった。自分が癌だと知れば、絶望的になるのがわかりきっていた。そうなれば、坂道を転げ落ちるように何もかもが自暴自棄になってしまう。
それが一番怖かったのだ。内藤は、身内としての辛さを押し殺して顔色一つ変えずにこう応えていた。
「たいしたことはない。」
また、彼女と長年連れ添った岩谷も語る。
「怖いほど感のいい人でした。共済病院に入院してから頻繁にお見舞いに来てくださっていた親友の一人に小島春子さん(アイリスメガネ社長夫人)とういう方がいらっしゃいました。ある日、越路は“春子さん、今日は来ないわよ”というんです。私が“どうして?”と訊くと“うん、どうしても”と答えるだけでした。」
あとでわかったことだが、その日、小島夫人は愛車のジャガーで病院へお見舞いに来る途中に、接触事故を起こしていたという。
その他にも「コーちゃんは感がよかった!」という話は山ほどあるという。だから、そんな越路に対して周りがいくら癌を隠しても、気づかぬはずがないというのだ。
その年の夏、7月3日に夫の内藤は、主治医の院長から別室に呼ばれた。
「越路さんの胃痛は総合的な所見から胃癌によるものと思われます。切ってみないとわからないのですが、相当進んでいるようです」
その時の気持ちを内藤は克明に憶えていた。
「頭の中が真っ白になりました。それと同時に彼女には絶対に気づかれぬようにしなければならないと思ったんです。もしも彼女に気づかれたら、あの性格だと死期を早めることになると思い“癌”という言葉を胸に飲み込みました。彼女には何気なく“今度再検査するらしいけど胃潰瘍らしいよ、こじれたら面倒だからいっそ早めに切っちゃおいよ”と、こともなげに言いました」
彼女は、しばらく黙り込んだまま内藤の顔をじっと見つめたという。その表情から何かを読みとろうとしていたのだろう。
翌週の7月8日、彼女は胃の三分の二を切り取る手術を受ける。内藤は再び主治医の部屋に呼ばれる。
「やはり胃癌でした。予想以上に転移が進んでいます。制癌剤を使うしかありません。切らなければあと3ヶ月。ただし、薬の効く人・効かない人がいます。今後の経過しだいでは延命もできるでしょうが、当然のことですが、もう舞台は無理です」
覚悟はしていたものの、内藤にとっては、死刑の宣告に似た言葉だった。「とにかく彼女に気づかせないようにしなければ」と、そのことばかりが頭の中で渦巻いていた。
「悪い病気じゃなかったんでしょ?」
手術後、病院のベッドで目覚めた越路は、開口一番に内藤に訊いた。その横にいた岩谷の顔色も推し量りながら、彼女は病室に入ってきた婦長とこんなやりとりをしたという。
「私、癌ですって!? ようし! それなら今すぐここから飛び降りてやるから!」
と、ベッドから降りるまねをした。内藤と岩谷が、そんな彼女の笑えない冗談に言葉を返せないままでいたところ、機転をきかせた婦長が笑いながらこう応えた。
「どうぞどうぞ、私がうしろから押してさしあげますわ。そんな患者さん、うちの病院ではいりません」
彼女は、ほんの一瞬だけ何とも言えないような目をみせたあと、すぐに笑顔で言い返したという。
「そうよね、そんなわけないわよね」
内藤はこの時のことを婦長に感謝しているという。そんなやりとりがあって、ちょうど4ヶ月後に彼女は同じ部屋のベッドの上で永眠した。
死期を悟って逝くこと。知らぬまま逝くこと。それを伝える人。伝えることなく見送る人。
逝く者にとっても、見送る側にとっても、辛い選択であることには変わりない。だが、たとえ死が彼女の肉体を奪ったとしても、その歌声は変わらぬ輝きを放ちながら、人の心の中で生き続けている…
(引用元・参考文献:『聞書き 越路吹雪 その愛と歌と死』江森陽弘著・朝日新聞社)
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから