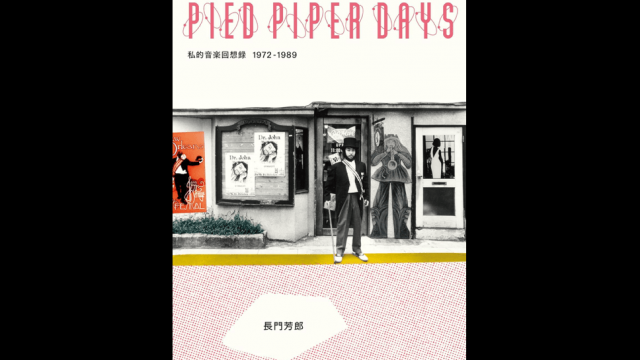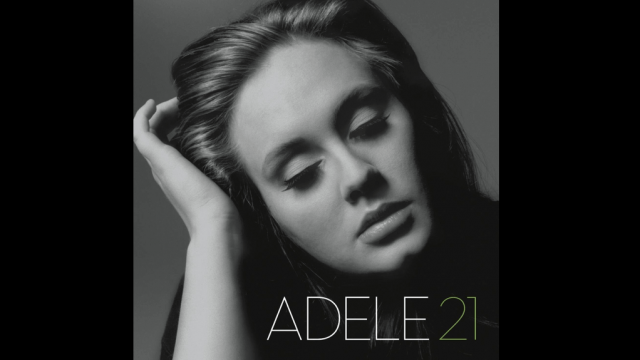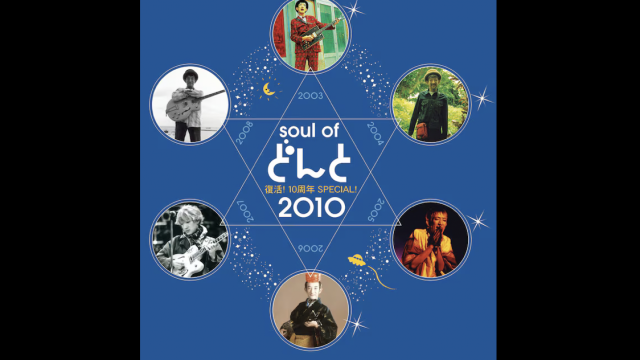南青山にあった伝説のレコード・ショップ「パイド・パイパー・ハウス」は、1975年11月にオープンしてから足かけ14年間の営業で1989年6月に閉店した。
日本では1989年から、レコード会社の発売する新譜が全面的にCDへと切り替わり、アナログ・この古世にはレコードの生産がほぼストップしている。したがって「パイド・パイパー・ハウス」が閉店したのは、レコード文化という一つの時代が終わったことの象徴でもあった。
店名は、グリム童話やロバート・ブラウニングの詩で知られる北ドイツ、ハーメルンに伝わる伝説の笛吹き男から名付けられたものだ。
開店した当時の港区南青山5丁目は、まだのんびりした住宅地の風情が残っていて、246通りから骨董通りを曲がってすぐの一角にあった「パイド・パイパー・ハウス」も、ビートルズで育ったかつての音楽少年たちが店を始める前は乾物屋さんだった。
人通りもさほど多くない場所にできた共同経営のいささか風変わりな店には、ロックの輸入盤を中心にして少数の邦楽のレコードがメインで、現代音楽から民族音楽、輸入小物や雑誌、ミニコミまでこだわりの品々が並んでいた。また、「音楽を中心とした新しい空間を」目指した店の一角には、大きな木の切り株をテーブルにして、ちょっとした喫茶スペースも設けられた。
この店の常連だったらのミュージシャンたち、音楽評論家や雑誌編集者、若きクリエイターなどが顔を合わせて、話に花が咲くことは日常茶飯事だった。閉店後も深夜まで貸切状態で、ビールやワインも飲めたので、酒場の風を呈することもあったという。
当時はコピーライターだった糸井重里が小泉今日子との対談企画で語っているなかに、70年代の「パイド・パイパー・ハウス」が出てくる。
小泉 その頃の原宿って、どんな感じでしたか?
糸井 これはぼくだけの感じ方かもしれないけど、原宿は、なんだか離れ小島のようでした。城塞都市というわけではないんだけど、緑も多いし、ちょっと島っぽいというか。だから、へんな人はここに集まっちゃったほうが楽、みたいなところがあったんです。
小泉 離れ小島。
糸井 スーツ姿の人がほんとに少なかったですよ。セントラルアパートにあった広告会社の営業マンたちも、ほとんどスーツじゃなかったと思う。
<略>
ロンドンブーツが流行れば、みんながロンドンブーツ履いてる。原宿はそういうところで、スーツじゃない人たちの島だった、という気がしますね。ぼくの気分では、なにか、こことロサンゼルスがつながってたんですよ。
小泉 原宿とロサンゼルス。
糸井 そう。青山の骨董通りを少し入ったところの角にパイド・パイパー・ハウスっていうレコード屋があって、そこで輸入盤のレコードを買ってくるやつがいたりしてね。
小泉 うん、うん。
糸井 それから、セントラルアパートに、ブライアン・フェリーが来たりとか。
小泉 へぇえー。
糸井 セントラルアパートって、建物の中心に中庭があって、そこを囲んで吹き抜けになっていたんです。それぞれの部屋の入口が中庭に面していて、「ブライアン・フェリーが来たぞ」っていうと、みんながこう、見に出てくる。
(全文はこちら⇒「ほぼ日刊イトイ新聞2011-03-07」)
「パイド・パイパー・ハウス」は確かに音楽を通して、ロサンゼルスとつながっていたのかもしれない。
他の店ではなかなかお目にかからない珍しい輸入盤のレコードが、LAのショップのように並んでいただけでなく、1枚のレコードをめぐってアーティストやその周辺、ルーツまでを含む情報が伝えられていた。
そうした方向性がさらに充実していくのはシュガーベイブやティン・パン・アレーのマネージャーだった長門芳郎が、1977年12月に同店のスタッフに加わってからである。
アメリカでは廃盤になったレコードや過剰在庫の処分品は、ジャケットの角がカットされて通常の流通を外れた廉価盤となって出回る。
長門は複数のカット盤卸業者から届けられる膨大なリストをチェックして、店の目玉になるようなレコードを選び出しては、それらをオーダーして店に並べた。

『Hoagy Carmichael Sings Hoagy Carmichael』
当時の歴代ベストセラーの中でも特に「パイド・パイパー・ハウス」らしいのは、1975年に英MCAからリリースされた『Hoagy Carmichael Sings Hoagy Carmichael』だった。
これは「スターダスト」「我が心のジョージア」ほか、数多くのスタンダード・ソングを書いたアメリカのソングライター、ホーギー・カーマイケルが自作品を歌った1954年リリースの古いアルバムである。
その地味なレコードが良く売れたのは細野晴臣の「香港ブルース」(1976年)や、ザ・バンドの「我が心のジョージア」(1977年)で、期せずしてカーマイケル作品のカヴァーが発表されていたからだ。廉価盤ということもあって、オリジナルを聴いてみたいという音楽ファンが購入してくれた。
良いレコードであれば洋楽・邦楽を問わず、輸入盤以外でも積極的に扱うという「パイド・パイパー・ハウス」の姿勢は、当時の一般的なレコード店に比較すれば際立っていた。
松本隆がプロデュースした南佳孝のデビュー・アルバム『摩天楼のヒロイン』が、1973年の発売から3年が過ぎて品切れになったままだったのを知り、レコード会社に300枚の再プレスを要望して、この小さな店だけで100枚を売り切ったこともある。

『摩天楼のヒロイン』
1979年から80年にかけて話題を集めたRCサクセションのアルバム『シングルマン』再発運動のときも、「シングル・マン再発売実行委員会」の拠点は、「パイド・パイパー・ハウス」に置かれていたのだ。
一橋大学在学中の1980年に田中康夫が執筆して第17回文藝賞を受賞した小説『なんとなく、クリスタル』にも、この店が登場している。
六本木へ遊びに行く時には、クレージュのスカートかパンタロンに、ラネロッシのスポーツ・シャツといった組み合せ。ディスコ・パーティーがあるのなら、やはりサン・ローランかディオールのワンピース。輸入レコードを買うのなら、青山のパイド・パイパー・ハウスがいい。
もちろん田中康夫は作家となってからも常連となり、3000枚のレコード・コレクションから選び抜いた100枚のレコードを紹介した単行本『たまらなく、アーベイン』(文庫版「ぼくだけの東京ドライブ」)は、「パイド・パイパー・ハウス」詣でがなければ生まれなかっただろう。

『たまらなく、アーベイン』
こうしたユニークな店にはミュージシャンばかりでなく、新しいライフスタイルを求めるクリエイターや若者たちが集まり、ロックからMORまで幅広い音楽ファンが育っていった。
「パイド・パイパー・ハウス」のお客さんでもあったポップス・マニアの若者たちによって結成されたグループには、ピチカート・ファイヴがいる。
デビュー前から、デモ・テープが完成する度に店に届けてくれていたピチカート・ファイヴの音楽センスに惚れ込んだ長門は、彼らのマネージメント・オフィスを作ることになる。
その一方で長門は、海外アーティストのコンサートをプロデュースし、ヴァン・ダイク・パークスやドクター・ジョンを筆頭に、フィービ・スノウ、ジョン・サイモン、ローラ・ニーロ、NRBQ、MFQなど、多くの来日ツアーを手がけた。
パイド・パイパー・ハウス閉店後、長門は海外アーティストのレコード制作とコンサートに携わりながら、数多くの洋楽アルバム/CDのリイシュー企画と監修でも名を馳せている。
<追記>2017年11月1日
2016年7月15日に渋谷タワーレコード5階に6か月の期間限定でオープンした『PIED PIPER HOUSE in TOWER RECORDS SHIBUYA』は、オープン後の好評を受けてさらに営業期間を延長することが決定して営業中です。
*なお本記事は2015年7月31日に初回公開されたものを加筆修正しました。

『PIED PIPER DAYS パイドパイパー・デイズ 私的音楽回想録1972-1989』
【関連特集】
レコード・ストア・デイ 2016──今年も開催!アナログレコード限定発売やTAP the POP企画トークショーも。
http://www.tapthepop.net/special/recordstoreday2016
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから