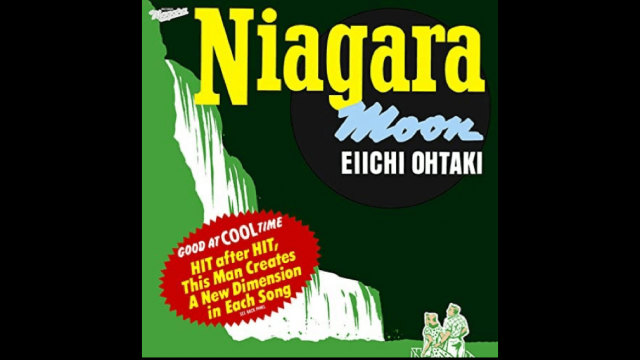小学生の頃から映画が好きだった寺尾次郎は、よく叔母さんに東宝の怪獣映画と青春ものと外国映画の3本立てに連れて行ってもらったそうだ。
音楽活動を始めていた大学時代はベーシストだったが、1975年3月から山下達郎が率いるシュガーベイブに参加し、翌年4月1日の解散ライブまでメンバーとして活躍した。
ただしメンバーに加入したときは、デビュー・アルバム『SONGS』(4月25日発売)が完成した直後だったので、日本の音楽史に残るその記念碑的なアルバムで演奏していたわけではない。
シュガーベイブはアルバムを完成させるとほぼ同時に、バンドとしてのライブ活動を強化するために、山下達郎と大貫妙子、村松邦男というフロントの3人と、ドラムが上原裕(ユカリ)、ギターが伊藤銀次、そしてベースが寺尾次郎という布陣になった。
ドラムとベースはバンドにとって、きわめて重要度の高い裏方仕事である。当時の経緯については伊藤銀次が、著書「伊藤銀次 自伝 MI LIFE,POP LIFE」のなかでこう語っている。
僕とユカリ君が入るとき、ベースの鮫川己久男君がやめて、寺尾次郎君が入ってきて、山下君がそのときに話してたのは、この編成だと曲によってトリプル・ギターで1キーボード。曲によってはツイン・ギターでツイン・キーボードってこともできるし、バリエーションが増えると。
ところがいざ加入してみると、山下達郎が書くような複雑なコード進行の曲をやったことがなかった伊藤銀次は、音楽的に知らないことが多くてついていくのに精一杯だった。
僕はそれまで泥臭い音楽ばっかりやってたもんで、どうもしっくりこない部分がありました。確かにバンドとして迫力ある演奏にはなったんだけど。そうこうしているうちに、山下君の方から「銀次、悪いけど」って話があって、シュガー・ベイブをクビになりました。
その後、1976年の春にシュガー・ベイブが解散。寺尾はその年いっぱいまでは音楽の仕事をしていたが、やがて洋画の配給会社に入社する。そこで音楽から映画の道に進んだのである。
会社ではパブリシティーの仕事を担当していたが、映画祭に関わったことをきっかけにして字幕翻訳家になっていく。だが、本人の弁ではたまたまそうなったのだという。
たまたま映画配給会社に入り、7年目くらいで映画祭の手伝いをしたとき、あまりに好きな作品があったので自分で字幕をつけようと思っただけ。配給会社にいたので字幕制作のやり方や工程は頭に入っていた。
その「あまりに好きな作品」とはデイヴィッド・クローネンバーグ監督が製作した『デッドゾーン』(1983年製作)である。
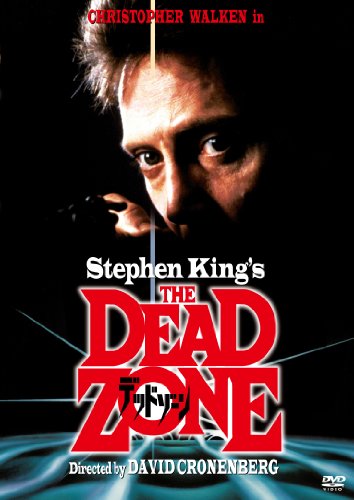
スティーヴン・キングの小説『デッド・ゾーン』を原作とするこの作品は、アメリカをはじめとする各国で高い評価を得ていた。しかし日本では商業的な成功が見込めないとの理由から、2年後の1985年にになってようやく第1回東京国際映画祭のなかで限定上映されている。一般公開はさらにその2年後の1987年だったが、やはりミニシアターでの封切りで地味なものだった。
そうした流れのなかで寺尾次郎は映画の字幕翻訳の仕事をするようになったが、それからは積極的に仕事に取り組んだようだ。おそらくは特殊な能力を必要とされる、地味な裏方仕事が性に合っていたのだろう。
やってみるとパズルのような面白さに取り付かれ、ライバル会社の人にも自分を売り込んで偽名で3年か4年ほど翻訳していた。そして10年目に親会社の都合から退職することになり、食うために始めたのが字幕屋である。
字幕翻訳という世界で頭角を現していったのは、英語だけでなく独学でフランス語を習得したからだった。それについては兄が聴いていたシャンソン歌手、シャルル・アズナヴールが歌うフランス語の”音”に惹かれた影響なのかもしれないと述べている。
だが明確な理由はなくともフランス映画には、どこか惹かれるものがあったのだろう。
翻訳を始めた当初はよくポルノ映画を訳した。一人で試写室に入り、箱書き作業をする。アメリカものが多かったが、時にフランスのものがあると、濡れ場でも話し続けるフランス人たちに笑いを禁じえなかった。(フランシュ革命を題材にしたものが最高に笑った)。いつまでたっても、話すことが好きな国民性。まるで回遊をやめると死ぬといわれるマグロのようだ。
地味な現場から始まった字幕翻訳家の仕事だったが30年後には、「寺尾次郎による渾身の新訳!」ということが話題になるほど、映画ファンにその名を知られる存在になっていた。
〈続く〉
(注)寺尾次郎の発言は、映画翻訳家協会(編)「字幕翻訳者が選ぶオールタイム外国映画ベストテン 」(AC Books)からの引用です。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから