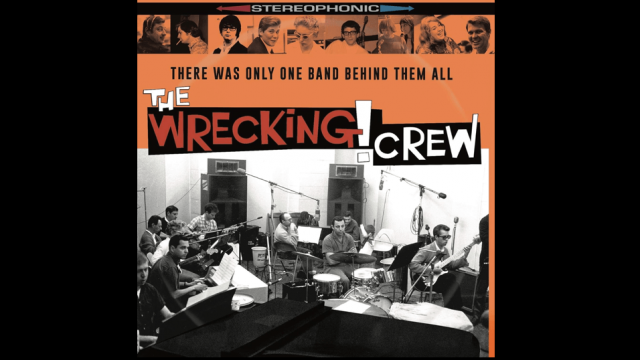カルメンマキ&OZはアメリカに出発する直前に、またしてもメンバーチェンジを行っていた。
そもそも結成当時のメンバーはカルメン・マキと春日博文のほか、鳴瀬喜博(のちにカシオペア)がベース、ドラムスは脱退後にクリエイションに加入する樋口晶之(のちに竜童組)であった。
ところが、レコード制作に入るという段階でカルメン・マキと春日以外、メンバーが入れ替えになったのだ。しかもアルバム録音が始まってから、それ以降のOZをアグレッシブなベースで支える人物、川上茂幸が加わってきた。
川上は70年代の前半に米軍キャンプを回り、元ダイナマイツの瀬川洋のグループでの活動を経て、OZに加入したことでロックシーンの黎明期を切り開いて、ベーシストのパイオニアと呼ばれることになる。
「閉ざされた町」のレコーディングに参加したメンバーは、カルメン・マキ、春日、川上、そしてキーボードが川崎雅文(のちに竜童組)、ドラムが久藤賀一である。
その年の2月21日に解散したイエローのキーボード奏者だった川崎は、前年のワールドロックフェスティバルはじめ、しばしば同じステージに立って仕事していた間柄だった。したがってOZのレパートリーをある程度知っていたので、新メンバーに変わってもすぐにバンドにとけ込めたという。
ロスに到着してからのメンバーたちは1ヵ月間、リハーサル・スタジオに入ってじっくり練習を重ねて曲を仕上げた。 本格的なレコーディングが始まったのは4月からで、夜の8時から朝方の4時までの時間帯でのセッションになった。
ロック・バンドの長時間レコーディングが主流になってきたアメリカの一流スタジオは、日本のように時間単位で営業するのではなく、すでに昼と夜中の2交代制に移行していた。昼の部が10時から18時までの8時間、夜の部が20時から4時までの8時間が基本だ。
しかし、ベーシックなリズム録りまでは順調だったが、ダビングに入ってから手間取ってしまい、後半になってくると時間が足りなくなってしまった。だから最後の仕上げについては、やや悔いが残るものになったらしい。
帰国後に「やれるだけのことはやった」と述べていた春日の発言からは、逆にやりきれない気持ちが伝わってくる。
「ダビングの段階からが大変で、最後のほうは時間が足りなくなってしまった。贅沢なほどに時間を使っていて、それ以上は無理ということになり、エリックを信用して、まかせることになった。だから100%満足とは言い切れないが、やれるだけのことはやった」
ここで話に出てきたエリック・スコットとは、タートルズのオリジナル・メンバーのユニットFlo&Eddieのバックで、ベースを弾いていたスタジオ・ミュージシャンだった。
紹介する人があって楽器の手配などを手助けしているうちに、アレンジなどのアイデアを提供するようになったエリックは、他の仕事をキャンセルしてまで熱心にスタジオに付き合ってくれたことから、最後はプロデューサー的な立場になってしまった。
実はロスにおけるレコーディングで最も苦労したのは、言葉によるコミニケーションの不自由さと、理解不能なことが生じることへの戸惑いであったという。何から何まで恵まれた環境だと見えていても、必ずしもいいことばかりではなかったのである。
カルメン・マキがその点について、このように述べていた。
「言葉が直接に伝わらないし、間接的に伝えるとニュアンスが変わってしまうところもある。私たちの意見と、日本のスタッフの意見、それにエリックと(エンジニア)のディーだから、まとめるのが大変でした。それ以外はもう、ぜいたく三昧で問題ありませんでした」
春日は作曲と編曲を担当していたのだから、サウンドとアレンジの最終責任者として、最後まで音に責任を持ちたかったであろう。時間切れで仕上げに立ち会えなかったのは、さぞかし口惜しかったに違いない。
6月に帰国したカルメンマキ&OZを待っているのは、アルバム発売後に全国33カ所で行われるツアーであった。そのためにファーストというPA会社が設立されて、全国どこでも同じレベルの音響機材でロックを楽しめる準備が進んでいた。
1976年7月10日、ポリドールのキティ・レーベルからセカンド・アルバム『閉ざされた町』が発売された。ファースト・アルバム『カルメンマキ&OZ』は、前年の1月に発売されて以来の累計売り上げは6万枚に達して、日本のロックとしては好セールスを記録していた。(注・1976年のポリドール・マーケティング部調べ)
だが『閉ざされた町』についてはレコード店からの反応がいまひとつで、実際のセールスもなかなか数字が伸びなかった。『カルメンマキ&OZ』はツアーで売れたが、力作で良い楽曲もあったのに『閉ざされた町』は売れなかった。
それは当時の日本の空気感と『閉ざされた町』の間には微妙ではあるが、実は大きなズレがあって、時代の先を行き過ぎていたからだと考えられる。
<参考文献>文中の春日博文氏、カルメン・マキ氏の発言は、「週刊ミュージック・ラボ」(1976年6月28日号)からの引用です。

「閉ざされた町」

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから