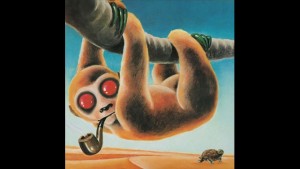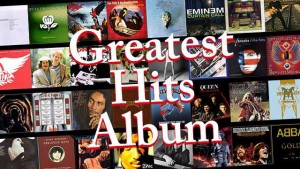日本のロックが黎明期にあった1970年代の初めに、本格的なロックバンドの「カルメン・マキ&OZ」を率いて活躍した春日博文が、64歳にして初のソロ・アルバム『独りの唄』を発表したのは2018年の5月のことだ。
春日はカルメン・マキ&OZが1977年に解散した後に、暗黒時代といわれたRCサクセションにギタリストとして参加し、エレキバンド化を推進するなど重要な役割を果たしたことがある。
その後は次第にプロデューサーの仕事へと活動の主軸を移して、1980年代後半からは韓国のソウルに住むようになり、若い音楽家たちを育ててプロデュースしながら、自らも韓国語で作品を発表してきた。
そんな音楽活動を経て到達したのが、初めて日本語で歌ったアルバム『独りの唄』だった。ウクレレを中心とする軽やかなサウンドにのって、やさしく人なつっこい感じの歌が展開していく内容で、バラエティに富んだオリジナル作品はどれも新鮮だ。
途中に入ってくるジャズやカリプソのインストゥルメンタル曲も、小品だからこそだろうが心地よい。とにかくシンプルで人間味にあふれ、人の温もりを思わせるあたたかに満ちている。
殺伐として息苦しさが漂う2018年の日本で、ここまで心がほっこりするような音楽に出会えるのは、僥倖のように思える。

独りの唄
カヴァー曲のなかで心を打つのが、かつての朋友だった忌野清志郎が書いた作品だ。2曲を取り上げているのだが、どちらもすぐ傍で二人が一緒に歌っているのではないか、そう錯覚しそうになるくらいに、ウクレレの世界とよく馴染んでいた。
そもそもRCサクセション時代にハワイでレコーディングしたとき、忌野清志郎が持ち帰ったウクレレを弾いてみて、春日は初めてウクレレという楽器に魅了されたという。そうした体験があったから、よく馴染むのも当然といえば当然だったのだろう。
なお、1996年に春日がプロデュースを担当したカルメン・マキのソロ・アルバム 『UNISON』に提供した楽曲の「ムーンビーチの砂の上」は、忌野清志郎も後にセルフ・カヴァーしている。
ところであらためて春日の足跡をたどってみると、「カルメン・マキ&OZ」を結成したのが1972年、彼はその年の春に高校を卒業するはずだったが、バンド活動に集中するためにすでに中退していた。判断が早かったし、早熟といえばかなり早熟である。
そこからビアガーデンの営業バンドといった下積み時代を経て、1974年11月にポリドールからシングル「午前一時のスケッチ」でデビューした。日本のロックシーンで頭角を現したこのときが20歳で、そこからプロとして認められていったのだから、ギタリストとしての技量も野心も、生半可なものではなかったのだろう。
もちろん自らの意思でロックという音楽を選んで、なんとしてもバンドで活動していくという強い覚悟を持ったシンガー、カルメン・マキという存在があってこそ、創作への道が開かれていった。

そして1975年1月にファースト・アルバム『カルメン・マキ&OZ』をリリースしたが、これは内容の素晴らしさだけでなく、予想を超える好セールスを記録したことでも音楽業界で注目された。
1974年6月にリリースされた四人囃子の『一触即発』、同じく11月にリリースされたサディスティック・ミカ・バンドの『黒船』に続いて、『カルメン・マキ&OZ』によって日本のロックが本格的に動き始めた感があった。
彼らはその年の5月に行われたグランド・ファンク・レイルロードの来日公演で、オープニング・アクトを務めている。それを宣伝するキャッチコピーひとつにも力が込められているし、当時の熱気が広告から伝わってくるようだ。
1975年は可能な限り、ほとんどのロック・コンサートやイベントに出演して、がむしゃらともいえるくらいにライブを積み重ねていった。その成果が数字にもつながったことで、アルバム『カルメン・マキ&OZ』が異例のロングセラーになったともいえる。
こうして日本で初めてといっていいくらいに、ロックというジャンルが商業的に成立する可能性が見えてきたのだった。やがて彼らは世界のロック・シーンも視野に入れて、4ヶ月もの時間をかけてロサンゼルスに滞在するレコーディングを敢行する。
(春日博文の静かなる復活②に続きます)

カルメン・マキ&OZ
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから