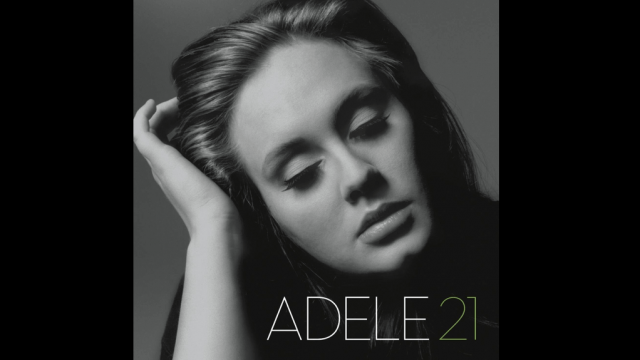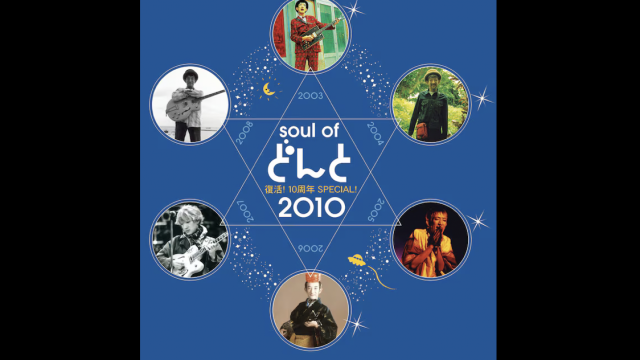ビートルズの最初のアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』から『ラバー・ソウル』までを手がけてきたのは、英国EMIの技術部門に勤務するエンジニアのノーマン・スミスだ。
そしてノーマンが1966年に昇進が決まってレコーディング現場を離れることになった時、後任として白羽の矢が立ったのは、まだ19歳のジェフ・エメリックである。
1962年に16歳でEMIに入社したジェフは、偶然だがその年の秋に行われたビートルズのファースト・レコーディングにアシスタントとして立ち会っていた。
ジェフが所属していた技術部門の管理者は、その後実験的なサウンドに挑んでいたプロデューサーのジョージ・マーティンと飛ぶ鳥を落とす勢いのビートルズのもとへ、まだ豊富な経験はないが鋭い耳を持つジェフを推薦するという、賢明な判断を下す。
そしてジェフは1966年4月に始まったアルバム『リボルバー』のレコーディングから、チーフ・エンジニアとして次々に画期的なサウンド作りに携わっていった。
4月6日に始まったセッションの1曲目は「トゥモロー・ネヴァー・ノウズ」、ヘヴィーなギターとリンゴの刻む重々しいドラムから始まる楽曲だ。
ジェフはしばらくノーマンのアシスタントをしていたので、初めのうちは先輩の前任者がやってきた方法に習っていたが、そのうちどんどん違うことやり始めた。
同僚だったテープ・オペレーターが、当時のことをこう振り返っている。
ジェフは経験の浅い新参者だったが、慣習的なやり方を知らないだけに、いろんなテクニックにトライしたんです。ビートルズはとてもクリエイティブで、とても冒険的だったから何でも試したがった。ジョージとジェフは抜群の相性で、怖いものなしのチームになりましたよ。あれが別のプロデューサーと別のエンジニアだったら、事態はまったく違っていたでしょうね。
EMIでは、どんなマイクでも楽器やアンプなどの近くに立てるのは厳禁で、約60センチ以内にマイクを立てるだけで、社内規定によて始末書を書かないといけなかったという。
なぜならば、コンデンサー型やリボン型のマイクは高価な製品で、奥行きのある繊細な音まで拾える反面、きわめてデリケートで取り扱いが難しいからだ。
特にリボンマイクの場合は、薄さ数ミクロンのアルミ箔でつくられたリボンで音の振動を拾う構造だったので、フッと息を吹きかけた拍子に、リボンが切れてしまったりすることもあった。
ところがジェフはビートルズのメンバーたちから、「もっと明るくてパンチのある音にしたい」と言われると、そうした社内規定を無視して、アンプにマイクをベタ付けで配置した。
今でこそ楽器のすぐ近くにマイクを立てるのは当たり前の光景だが、当時はまったく常識はずれのやり方だった。しかし、そこまでやってみても「モータウンのレコードなんかと比べるとリズム隊にパンチが足りない」と言われてしまう。
そこでドラムの各打楽器ごとに個別のマイクを立てたのに加えて、ジェフはモコモコしてパンチの出ないバスドラムの皮に穴を開けて、中にマイクを突っ込むという暴挙に出た。
ジェフは「ザ・ビートルズ レコーディング・セッションズ完全版」のなかで、その行為についてこのように解説している。
「バス・ドラムのマイクを、それまでよりもずっとドラムに近づけたんだ。それから、ビートルズの初期の写真で、襟が4つあるウールのジャケットを着て写ってるやつがあるだろう。あのジャケットをドラムに詰め、サウンドを鈍らせて、それをフェアチャイルドの660のリミッター/コンプレックサーで処理した。これが『REVOLVER』と『SGT PEPPER』のサウンドになったんだ。あんな音のドラムスは初めてだったよ」
リンゴ・スターをはじめメンバー全員がそのドラム・サウンドを気に入って、若いジェフのチャレンジ精神は素晴らしい結果を出したことで、早くも認められたのである。
「大いに気に言ってたのは間違いないな。全員あのサウンドに満足してた。まさに彼らが求めていたサウンドだったのさ」
これがレコーディングが始まって2日めのことだったから、プロデューサーのジョージ・マーティンもすぐれた協力者が現れたことを、大いに頼もしく思ったであろう。
これをきっかけにしてジェフは、ビートルズの新しいサウンド作りに欠かせないエンジニアとなり、ジョージ・マーティンとビートルズから吸収できるだけのものを吸収しながら、固定観念にとらわれないアイデアで新風を送り込んでいった。
そして『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』の制作にも深く関わり、歴史的な名作の誕生に貢献していくことになる。

「リボルバー」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから