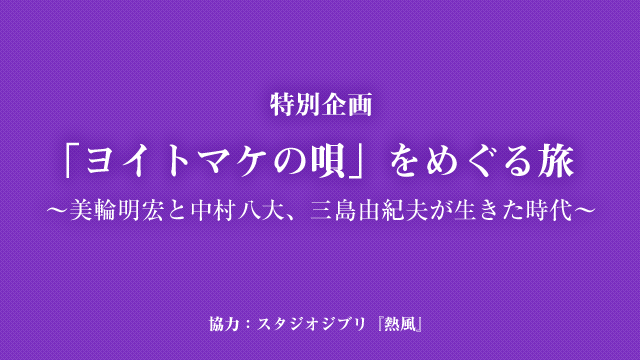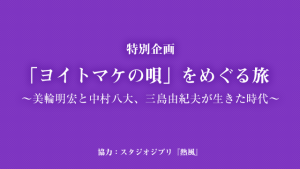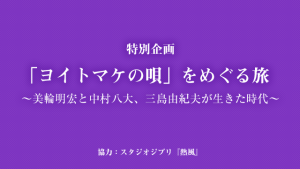シスターボーイという流行語とともに登場した美青年
日本におけるシャンソンの歴史は古く、宝塚少女歌劇団(現・宝塚歌劇団)で最初のレビュー『モン・パリ〜吾が巴里よ〜』が上演された一九二七(昭和二)年から始まった。海外資本によるレコード会社が本格的に事業を始めたのが同じ年のことなので、歌謡曲が誕生した時にはもうシャンソンが入っていたことになる。
やがてフランス映画の『巴里の屋根の下』や『巴里祭』が公開されて、その主題歌や挿入歌が流行して下地ができたところに、SPレコード6枚組『シャンソン・ド・パリ』が一九三八年に発売になり、これが大ヒットして最初のシャンソン・ブームを迎えた。

しかし太平洋戦争が始まってまもなく、敵性音楽が禁止されたことからこの流れはいったん断ち切られてしまう。
日本が戦争に敗れた戦後は、進駐軍の方針もあってアメリカのジャズとポピュラー・ミュージックが圧倒的な人気を博したが、一九五五年から五六年にかけてフランスからダミアやイヴェット・ジローなど、有名歌手が立て続けに来日公演を行ったことから、静かなシャンソン・ブームが始まっていく。
日本のシャンソン歌手では一九五四年にフランスから帰国した石井好子が、第一人者としてシャンソン・ブームを牽引した。石井は東京音楽学校(現・東京藝術大学)で主にドイツ歌曲を学んだ後、進駐軍相手のジャズ歌手として活動していたが、一九五〇年に音楽を勉強するためにアメリカへ留学した。その一年後にはパリへ渡ってレビュー・シアターの歌手となり、日本のシャンソンの先駆者となったのである。
それに続いたのが同じ東京藝術大学出身の二人、音楽教師を経てシャンソン歌手になった芦野宏と、フランス留学を体験した抒情画家・中原淳一を叔父に持つ中原美沙緒だった。そこに留学先のソルボンヌ大学を卒業した高英男が、フランスから帰国して加わったことで層に厚みを増した。
ブルースの女王と呼ばれた淡谷のり子もまた、シャンソンを重要なレパートリーにして活躍した。日本のシャンソンの牙城だった宝塚歌劇団のトップスターだった越路吹雪、戦前からの宝塚スターでベテランの橘薫などの顔ぶれから、シャンソン歌手とは音楽学校出身で、育ちが良くて上品さが身についているのが普通となった。
そうしたブームを底辺で支えていたのが愛好家が集うシャンソン喫茶で、東京都内では「ジロー」「十字架」「銀巴里」「ラ・セーヌ」「サロン日航」などが有名だった。そこから多くの新人歌手が育っていったのだが、なかでもひときわ目立っていたのは銀巴里で断然の人気を誇っていた丸山明宏だ。

敗戦後の復興期にあった一九五一年、銀巴里はデラックス・キャバレーとして、東京の銀座七丁目に開店した。やがてシャンソンがブームになり始めた一九五五年から、昼はシャンソン喫茶として営業するようになった。国立音大付属高校をわずか二学期で退学した丸山明宏(当時は臣吾)は、十六歳で同性愛者たちが集まる銀座のクラブで歌い始めた異端児である。
それから二年後、偶然に前座を務めたことで橘薫に見出された丸山臣吾は、銀巴里に出演していた原孝太郎に師事することになった。彼のコンチネンタル・タンゴの楽団で専属歌手として歌い始めたのは一九五四年で、そこから徐々に頭角を現して知る人ぞ知る存在になっていった。バリトン歌手だった畑中良輔やベルリンに留学して指揮者になる石井真木といった友人たち、米軍キャンプで知り合った中村八大や平岡精二などの人気ジャズメンも頻繁に顔を出した。
熱心に銀巴里へ通っていた大学生のなかにし礼は、シャンソン歌手のため訳詞を手がけるるようになっていくが、銀巴里というところは「丸山明宏という月の大王ないしは女王を中心にして回っている小宇宙だった」と、明快に言い切っている。
歌手たちはみなそれぞれに個性的であったが、申し訳ないが、月の支配下にある夜空の星々とでもいったらいいか。開店の翌年、昭和二七年に十七歳の丸山臣吾が「銀巴里」デビューを果たす。が、その頃の「銀巴里」はまだまだ不入りだった。紫色の髪をした丸山臣吾は数寄屋橋あたりに立ってサンドイッチマンをやり、そのまま店まで客を引き連れて満席にしたという伝説が残っている。
(なかにし礼著「黄昏に歌え」朝日新聞社 P254)
客席を埋めたのは熱心なシャンソン・ファンばかりではない。流行の最先端にある洒落た店で恋人とデートを楽しみたい、そんな若いカップルもたくさん交じっていた。
評判を聞きつけて有名人や文化人もたくさん通ってきた。作家の遠藤周作、柴田錬三郎、三島由紀夫、安岡章太郎、吉行淳之介、画家の岡本太郎、俳優では仲代達矢、西村晃、まだモデルだった頃の菅原文太、松竹歌劇団の九條今日子らダンサーたち常連に混じって、映画や演劇、芸能関係者たちもたびたび顔を出した。

ところが一九五六年に新宿の音楽ビル「ラ・セーヌ」が出来ると、銀巴里から原孝太郎が引きぬかれるという事態が発生した。人気と実力のあるバンマスが楽団ごと移籍してしまったことから、主だった歌手も行動を共にしたので銀巴里は常連客が一気に減った。それからしばらくの間は、閑古鳥が鳴くことになったのである。
丸山臣吾はそのとき師匠から一本立ちする時期だと判断し、迷いながらも銀巴里に残る道を選んだ。そして店の宣伝のためにと、なるべく目立つような工夫をするようになり、ユニセックス的なファッションを身にまとって歌い始める。もちろん店の宣伝だけでなく、観客にアピールすることを心がけてのことであった。
芸名を臣吾から明宏に改めた一九五六年の秋になると、三々五々と集まっていた客が日を追って増えて、入り口の外に行列ができるまでになった。当時のプロフィールには、身長が五尺四寸五分(百六十五センチ)、体重が十二貫(四五キロ)、ウェスト二十インチ(五一センチ)とある。男性にしては小柄で、かなりやせた体型だった。
この青年の名前が都会の最新風俗として「シスターボーイ」という新語とともに、マスコミを賑わせるのは一九五七年の年が明けからのことだ。その陰には映画の宣伝でマスコミを操作する、仕事のできる仕掛人が隠れていた。(続く)

*ノンフィクション『「ヨイトマケの唄」をめぐる旅 〜美輪明宏と中村八大、三島由紀夫が生きた時代〜』の連載が、スタジオジブリの小冊子『熱風』で3月から始まりました。
編集部のご厚意のもとにその冒頭部分のテキストを、毎月TAP THE POPでも公開しています。
4月10日に発行された『熱風』には、この続きが掲載されています。
ご一読いただいて興味を持たれたら『熱風』を手にとっていただければ幸いです。
なお『熱風』はフリーペーパーですが、配布数に限りがあるので定期購読をおすすめいたします。
(佐藤剛)
*このコラムは2016年4月に公開されました。
・スタジオジブリの小冊子『熱風』
・ジブリ関連書常設店の一覧
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから