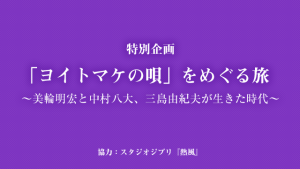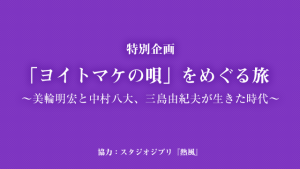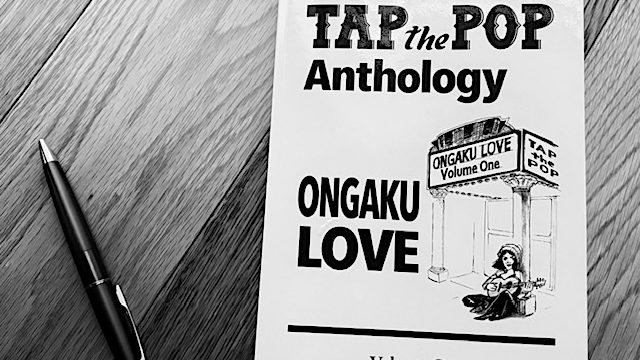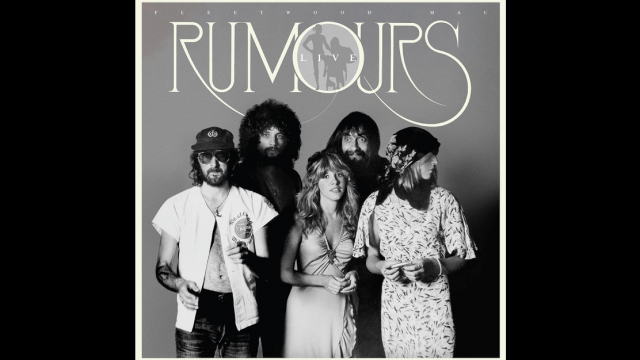敗戦後の復興期にあった1951年、東京・銀座に開店したデラックス・キャバレーの『銀巴里』は、当時としては眩(まばゆ)いほどに豪華な内装のダンスホールだった。
美輪明宏が1955年にシャンソン喫茶へと衣替えした『銀巴里』で、専属歌手として歌うようになったのは開店から二年目、その当時は21歳で丸山明宏(以前は丸山臣吾)と名乗っていた。
ユニセックス的なファッションを身にまとった美しい青年は、まもなく店で最も人気を集める存在になった。シャンソンのファンばかりでなく、アンテナ感度の鋭い若者や文化人、芸能関係者がいつも客席に顔を見せた。
中村八大や平岡精二といった人気ジャズ・ミュージシャン、有名作家の三島由紀夫、安岡章太郎、吉行淳之介、遠藤周作、柴田錬三郎、俳優の仲代達矢や西村晃などが通って来た。
やがて男でもなく女でもなく、妖しいまでの魅力を振りまきながら歌う丸山明宏は、創刊ラッシュが続いた週刊誌のコラムや新聞記事にも取り上げられた。”シスターボーイ”という新語とともにマスコミを賑わせて、スターになっていくのは1957年の年明けからである。
丸山明宏はシャンソンからエルヴィス・プレスリーまで歌っていたが、人気に火がついてヒットしたのは港町の娼婦を歌った「メケ・メケ」だ。
長崎から上京して国立音大付属高校に入った丸山明宏はわずか二学期で退学、同性愛者の集まる銀座の喫茶・クラブでアルバイトしながら、シャンソンを歌い始めた異端児だった。自らの手で日本語に訳して歌詞を付けた「メケ・メケ」には、その尋常ではない才能が早くも表出している。
船乗りと港の女に起きた別れの修羅場を題材にしたシャンソンの原詩は、「男が悲しむ娘の姿を知り、海に飛び込んで恋人の元に引き返す」というハッピーエンドの物語だった。しかし、丸山明宏は大胆な解釈で、アンハッピーエンドに変えて歌っていた。
しかも歌詞からは”クロンボ”や”バカヤロー”といった、日本の”お上品”なシャンソンにはあるまじき言葉が飛び出してきた。それまでのかしこまった文語調や、品のある詩的な歌詞とは異質な、庶民の生活に根ざした口語体の日本語だった。
そこには綺麗事ではないリアリティと、言葉が生み出すビートと躍動感があった。あちらこちらに散りばめられた「チチ」「メケメケ」「イヤイヤ」「トトー」といった言葉。
「く」の音韻を繰り返す「くだまいてる クロンボ」、その響きに対応する「ブロンドの髪」と「情なしのケチンボ」。
「かわいい わかってるだろ」の繰り返し、「ときはすぎてきてきがなる」「 くるときがきました」と、「き」の音韻を多用する歌詞には、笠置シヅ子の「東京ブギウギ」以来の日本語によるビート感覚は新鮮だった。
日本にロックンロールが上陸してロカビリー・ブームが巻き起こり、口語体による日本語の歌詞をビートに乗せた最初のオリジナル・ソング、水原弘が歌った「黒い花びら」が誕生するのは1959年の夏のことだ。
丸山明宏の「メケ・メケ」はそれに、二年も先行していたのである。

●この商品の購入はこちらから
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから