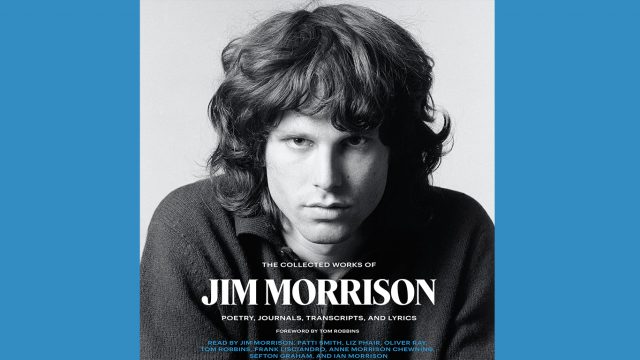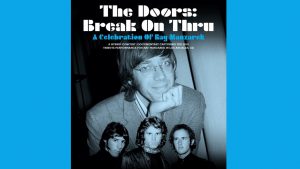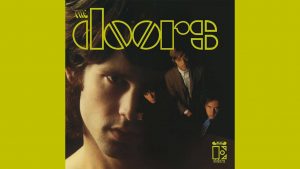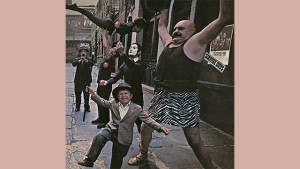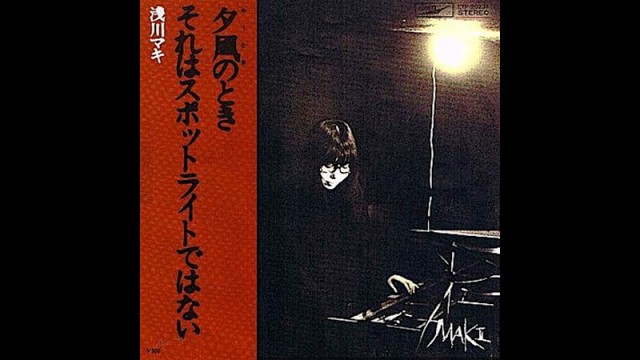ロックの歴史において“孤高の詩人”として多くのアーティストに影響を与え続けてきたジム・モリソン。彼はどんなきっかけで詩を書き始め、バンドを始めることとなったのか? “First Step(はじめの一歩)”とも言える時代のエピソードをご紹介します。
「耳鳴りのように内側から音楽が聴こえてきて、俺はそのメロディーに合わせて詩を作る。音が聴こえてきても俺はそれを譜面にする方法なんて知らない。覚えておくためには、詩を書きとめておくしかないんだ。だから多くの場合は詩だけ残ってメロディーは忘れてしまうんだ」
ジムは14歳の時に、とても夢中になった本があったという。それはジャック・ケルアックが放浪体験を元に書き上げた小説『On the Road(路上)』だった。
「あれは1957年の冬だったよ。ビートジェネレーションを題材にした内容だった。」
また、高校時代の英語教師が読書家だったジムとの間で、こんなエピソードがあった。教師はその時のことをこんな風に語っている。
「彼が16世紀や17世紀の悪魔学に関する本のことをレポートに書いてきた時に“、本当にそんな本があるのか?”と疑ったことがありました。ちょうどアメリカ議会図書館に行くことになっていた別の教師がいたので、たのんで確認してもらったところ、確かにその本は存在していました。彼はおそらくアメリカ議会図書館でしか読めないような本も読んでいたんだと思います。私はそのレポートをもう一度読み返して感銘を受けました。」
その頃からジムは作家を志すようになる。ランボーに関する逸話や、ボードレールやアレン・ギンズバーグ、ディラン・トーマスなど、苦悩の中に自己主張を押し通した芸術家たちの作品が彼の心を捉えて離さなくなっていた。
新聞の切り抜きを集めたり、雑誌の広告、会話の断片などを大学ノートに書き留めることが日常となっていく。高校2年になってからは、詩の量が増えていった。その大学ノートは、自分の心を映す鏡でもあった。ドアーズの初期の楽曲「Horse Latitudes(放牧地帯)」などは、そのノートから生まれたものだった。
高校卒業後、フロリダ州立大学に入学。同級のルームメイトたちとシェアハウスで暮らしながら、キャンパスライフを謳歌していたジムは、いつも酒に酔い、仲間たちとドンチャン騒ぎをして、毎夜エルヴィス・プレスリーのレコードをフルボリュームで聴いていた。
そんな乱れた生活を繰り返す中で、ある時期から哲学にのめり込んでいくようになり、1964年の1月、家族の反対を押し切ってUCLA(カリフォルニア大学ロス校)の映画学科に編入した。
「映画科で学び、自分の考えや思いつきをスクリーンの上に再現してみたくなったんだ。それが当時の夢だった。」
後にドアーズの楽曲「The End」を映画『地獄の黙示録』(1979年)の挿入歌として使用したフランシス・F・コッポラ監督は、彼と同じ教室で学んだ同窓生でもある。
世界中のロックファンを魅了したドアーズの伝説は、その大学にいたレイ・マンザレク(オルガン・ピアノ)との出会いから幕を開けることとなる。
「俺はレイの存在を知っていたよ。レイは自分が撮った自主制作の映画にガールフレンドが全裸でシャワーを浴びるシーンを使い、教授陣がそれを“カットしなさい!”と要求してきても断固として応じなかった男だ。密かに尊敬していたよ。それにレイはもうその当時からバンドをやっていて、当時ヒッピー達が集まっていたカリフォルニアのクラブなんかで演奏していた彼らを何度か観に行ったりもしていたよ。俺はレイの音楽にも惹かれていた。」
1965年6月の出来事だった。レイは、ある高校の卒業ダンスパーティーでソニー&シェール(60年代中期に活躍した夫婦デュオ)のバックバンドを務めることになる。
ちょうどバンドのメンバーが脱退したばかりで、事前に出演契約していた6人メンバーが5人に減ることを制作側に知らせたところ「それではギャラは払えない」という返事が返ってきたという。レイは以前から顔見知りになっていたジムにキャンパスで声をかけた。
「よお、ジム。俺たちと一緒にステージに立ってみる気はないか?」
「レイ、冗談だろ? 悪いけど俺は楽器なんか今までいじったこともなんだぜ」
「かまやしないさ!ただエレキギターをぶら下げてステージに突っ立ってるだけでいいんだ。シールドはアンプから抜いておくから適当に弾いてるふりをしててくれ」
ジムにとって、それが人生初のステージとなった。そのこときっかけに二人は急速に仲良くなり、1965年の夏、彼らはバンドを結成することとなる。
「レイ、俺は歌うぜ!自分の考えや思いつきを詩にして、それを音楽と共に表現するんだ。」
「バンドの名前はなんにする?」
「ザ・ドアーズだ!既知の世界と未知の世界の境目に“その扉”があるんだ。俺たちはその扉になるんだ」
当時、ジムは19世紀のフランスの詩人アルチュール・ランボーに多大な影響を受けていた。
「あらゆる感覚の理知的な錯乱によって、未知なるものを実現すること」
そんなランボーの理念を、彼は忠実にバンドに注ぎ込もうとしたのだ。そしてランボーの他にもう一人、このバンドの誕生を語る上で忘れてはいけない人物がいた。
If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it truly is, infinite.
知覚の扉が浄化されるならば、万物は人間にとって“真の無限”として立ち現れる
幻視者であり、画家でもあった18世紀の詩人ウィリアム・ブレイク(1757年―1827年)の書『知覚の扉(the doors of perception)』の中には、こんな一節が綴られている。
また、イギリスの作家オルダス・ハクスレー(1894年―1963年)は、このブレイクの詩に影響され、自らのメスカリン体験を綴った著作を『知覚の扉』と題した。
ジムは、これら二つの作品に共感を覚え、「扉(Doors)」という名前を提案した。
<引用元・参考文献『ジム・モリスン 知覚の扉の彼方へ』ジェリー ホプキンス(著)ダニエル シュガーマン(著)野間けい子(翻訳)/シンコーミュージック>
【佐々木モトアキ プロフィール】
https://ameblo.jp/sasakimotoaki/entry-12648985123.html