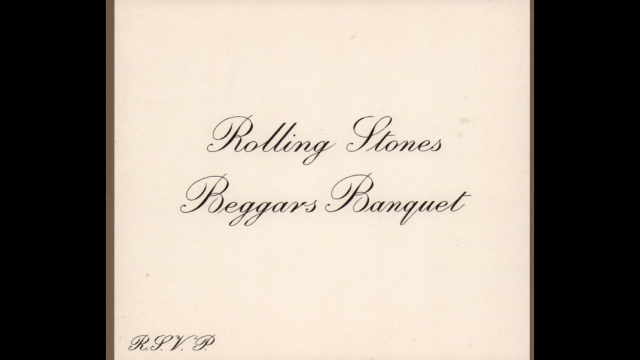(前編からの続き)
あの時代、ミックは他のどんなアーティストよりも快楽主義的なセックスやドラッグ、そしてロックンロールの精神を体現していた人物だ。まさに反体制の象徴であり、品位の欠片もない存在だった。それはステージ上の“単なるパフォーマンス”ではなく、それまでの私生活に目を向けてもうなずけることだった。
2003年までに、4人の女性に7人の子供を産ませていた。性的関係を持った女性(時には男性)は数知れず。何度もドラッグで逮捕され、2度は有罪、短期間ながら1度は収監すらされている。
「悪魔を憐れむ歌」ではサタンを讃美し、アメリカで起きた“オルタモントの悲劇”では殺人事件を引き起こす結果となった。ミックは昔から王族を愚弄し、特に女王のことを“魔女の親玉”と呼んでいたこともあった。(当たり前ではるが)女王は、ミックのそうした姿勢や大袈裟に物事を誇張するパフォーマンスを決して許すことができなかった。
──午前11時ちょうど、バッキンガム宮殿内にある式典場のバルコニー席に待機していた楽団が演奏を始める。英国衛士の精鋭部隊が中央道路を行進していく。
「ご着席を」
チャールズ皇太子が群衆にそう言うと、側にいる侍従が叙勲者のプロフィールを耳打ちする。王室長官が、最初の叙勲者の名前を読み上げるためにマイクの前に立つ。
ミックはガムを噛み、ポケットの小銭をいじりながら、立ったまま控え室のドアの前でそわそわしていた。やがて英国海軍少将に「叙勲者の列に加わるように」と告げられると、あわててガムを処分し、前列の僧侶と養羊業の貢献により叙勲される初老の男性の後ろについた。その日叙勲を受ける数名の中で、勲爵士(ナイト)位を叙されるのはミックだけだった。
「マイケル・フィリップ・ジャガー」
王室長官がその名を読み上げる。そして、こう続けた。
「ポップミュージックへの貢献を称えて」
ミックは笑顔で一歩前に出ると、チャールズ皇太子の前で会釈し、そのままひざまずいて頭を垂れた。
「我、汝にナイト位を授けん」
皇太子が剣を手渡しながら、ミックの左肩と右肩を順にやさしく叩いて言った。
「サー・マイケル・ジャガーよ」
この日の様子を関係者から聞いたキース・リチャーズは、こう言い放った。
「俺達を刑務所にぶち込み、全力で破滅させようとしてきた体制から勲章をもらうなんてどう考えても馬鹿げているぜ! くそ忌々しい冠をかぶって気障(きざ)なアーミンの白い毛皮を羽織った野郎なんかと、一緒のステージには立ちたくないね!」
ミックの元恋人マリアンヌ・フェイスフルはもっと寛容だった。
「ミックってもの凄く見栄っ張りなのよ。いつもあれを死ぬほど欲しがっていたわ。だからなんとなく同情しちゃうのよね」
そして、ミック本人はこんな感想を口にした。
「おそらく俺達の知っている体制は今はもう存在しないんだ。あまり深刻に考えなければ、勲章をもらうってのはいいもんさ。軽い気持ちでぶら下げておけばいい。調子に乗って自分も偉くなったもんだなんて思うのは愚の骨頂だよ」
キースの批判について訊かれると、ミックは明らかに不機嫌になったという。
「アイスをもらえなくてわんわん泣いているガキと同じさ!」
その頃、キースはコネチカット州郊外の邸宅からチャーリー・ワッツに一本の電話をしていた。
「まったくこいつはどういう茶番なんだ!?」
チャーリーは冷静な口調で一言。
「けど、あいつは昔からナイト位を欲しがっていたじゃないか」
キースは、自分と一緒に育ってきた“誰よりも理解している”と思っていたはずの男、ミックのことを思い出しながらこうつぶやいた。
「畜生、どうだったかな。よく憶えてねぇや」

<引用元・参考文献『ミック・ジャガー ワイルド・ライフ』クリストファー・アンダーセン(著)/岩木貴子、小川公貴(翻訳)/株式会社ヤマハミュージックメディア>