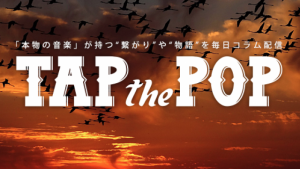日本のロックの原点を築いたジャックスの早川義夫は、こんな言葉を残している。
歌は悲しいから歌うのだと思っている。寂しいから歌うのだ。人とは、違うから歌うのだ。何かが、欠けているから歌うのだ。
中学時代に日劇ウエスタンカーニバルを観てロックンロールに目覚めた早川は、高校入学後に仲間たちとバンド活動を始めると、和光大学へ進学してからジャックスを結成した。
そして1967年にヤマハが主催した第1回「ライト・ミュージック・コンテスト」の全国大会で、フォーク部門の第2位に入賞した。
1968年3月には日本のジャズを扱うマイナーレーベルだったタクト・レコードから、シングル盤の「からっぽの世界」を発売している。
メンバー4人の個性から生まれるジャズとロックとポップスの要素がまじりあった、オルタナティブとしか言いようがない独自のサウンドにのせて、生々しいまでの息づかいや気配をともなって、言葉を超えて伝わってくる早川義夫の世界は圧巻だった。
「からっぽの世界」で注目を集めたジャックスは、1968年9月10日にメジャーの東芝EMIからファースト・アルバム『ジャックスの世界』を発売する。
ところが後に名盤との評価を受けるこのアルバムが、当時は期待されたほどには売れなかった。
一世を風靡していたGS(グループ・サウンズ)のカテゴリーには入らないし、学生たちの間で流行していたカレッジ・フォークでもなく、ジャズやロックの定義でもない音楽は収まりどころがなかった。
しかも追い打ちをかけるように「からっぽの世界」の歌詞で、「おし」が差別用語だとして放送禁止になった。
こうしてジャックスはわずか2年余りの活動期間で、バンド解散を余儀なくされることになる、解散の理由は「売れないから食べていけない」という、なんともシンプルかつ身も蓋もないものだった。
ドアーズやヴェルヴェット・アンダーグラウンドにも通じる時代の先駆者だったとの声が高まり、日本の音楽史に残る伝説的なロック・アルバムと再評価されるのは、解散から20数年後のことである。
代表作となった「ラブ・ジェネレーション」の詞から浮かび上がってくるのは、正直すぎるほど素直に自分をさらけ出す若者の、鋭さと脆さをあわせ持っている純粋でナイーブな心根である。
そこには、いつのどんな時代にあっても、これだけは不変だと言い切れるだけの切実な願いが込められていた。
そうした願いはマスコミやファンから「フォークの神様」と持ち上げられることを拒絶し、あらためて歌と向き合おうとしていた岡林信康のカヴァーによる「ラブ・ゼネレーション」へと受け継がれていく。
ジャックスの解散から20数年後に音楽活動を再開した早川義夫は、自著「たましいの場所」のなかにこんな言葉を記している。
音楽を手段としてではなく、音楽を目的としている人だけが、悲しみを表現できる。悲しみは作り出せない。悲しみは張り付いてしまったものだ。染み付いてしまったものだ。隠すことも、ごまかすことも出来ない。にじみ出てしまうのである。
(注)本コラムは2014年7月11日に公開されたものを加筆修正しました。早川義夫氏の言葉は晶文社より発行された「たましいの場所」からの引用です。

「ジャックスの世界」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから
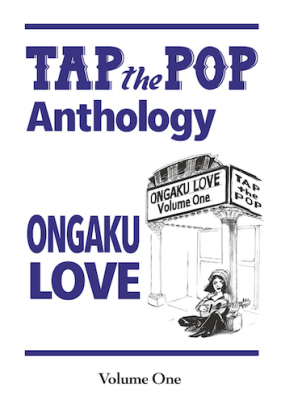
- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから