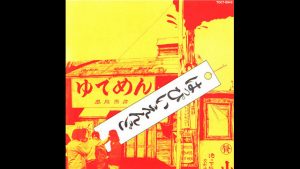立教の学生だった細野晴臣の家に、慶應に通う松本隆が来て、ロックに日本語は乗るのだろうかと、アルバム『ジャックスの世界』などを参考にしながら、勉強会に取り組んでいたのは1968年の秋のことだ。
1960年代末期から70年代の初頭にかけて、日本語のロックが生まれて来た背景には、欧米のロックに刺激を受けて始まったグループ・サウンズへの反発と失望があった。
スパイダースやブルーコメッツ、ワイルドワンズ、タイガース、テンプターズ、そしてゴールデン・カップスなどのバンドが群雄割拠したグループ・サウンズは、ビートルズが来日した1966年の夏を境に動きが活発化し、翌年から一大ブームの様相を呈していた。
しかし、レコード会社や芸能プロダクションが主導していたために、ブームが過熱するにつれて数が限られたプロの作家が提供する作品ばかりがヒットし、人気が出たまでは良かったが、楽曲がパターン化してしまい、売れ筋の歌謡曲と差がほとんどなくなった。そのために飽きられてしまったバンドは淘汰されて、3年と持たないでGSブームは終焉に向かうことになった。
そこで注目されたのがニューロックだった。
当時の音楽シーンは、格好だけロックっぽくて中身は歌謡曲だったグループ・サウンズが流行った後、クラプトンやストーンズの即興フレーズを本人達よりも正確に弾くようなコピーバンドが主流でした。そうした風潮に反発して結成したのが、“はっぴいえんど”です。(松本隆)
細野と松本がひとつの指標にしていたのは、アメリカのバッファロー・スプリングフィールドだった。
スティーヴン・スティルス、ニール・ヤング、リッチー・フューレイという、3人の才能あるヴォーカリストを擁するバンドの音楽は、フォークソングとハードロック、異なるふたつの要素で成り立っていた。さらにはカントリーやブルース、ラテン、R&Bの要素まで含まれていたのだ。
ほどよくカントリーで、ほどよく都会的で洗練されてて、サウンドのなかで”都市”と”田舎”が、自然に融合していバッファローの音楽はどこか整然としたところがあった。
はっぴいえんどをはじめるにあたって、松本は日本という場でやるんだからと、日本語の歌詞にこだわった。それまでの歌謡曲にはなかった日本語の新しい表現、そこに到達するにはどうすればいいのかを考えたのだ。
そして音楽的にもロックとカントリーの接点、すなわち都市と田舎の接点を見つけたいと思ったという。そこで自分なりの答えを出そうと取り組んだ松本は、生まれ育った東京という都市を”風街”に見立てて、舗道のあたりからときどきぽっかりと露出している”田舎”を発見する手法を見出していく。
”風街”は記憶の中にある街で、本来は時間的なイメージだったが、それを空間的なイメージで言葉に落とし込んだ。
”はっぴいえんど”では、安直なラブソングではなく、身近にある風景や出来事を愛おしく想う気持ちを表現することを心がけました。だから、「夏なんです」や「風をあつめて」は僕にとっての“ラブソング”です。(松本隆)
日本語のロックが完成したと高く評価されるアルバム『風街ろまん』は、1971年11月に発売された。

日本人にとっての夏は、亡くなった先祖たちの霊が一年に一度だけ、子孫の家に戻ってくる「お盆」の季節。夏のあぜ道に埃を立てる風、生い茂る木々や植物の生命力、太陽の強い光と入道雲、見えない昆虫たちの声を写しとった歌詞には、生きるものたちと死者の魂が共存する日本の夏があった。
たゆたうグルーヴ感の向こう側からは、死者たちの声までも聞こえてくるようだった。
(注)本稿は2014年8月1日に公開したコラム『はっぴいえんどの「夏なんです」からは、死者たちの声までも聞こえる』を改訂、改題したものです。
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

TAP the POPメンバーも協力する最強の昭和歌謡コラム『オトナの歌謡曲』はこちらから。