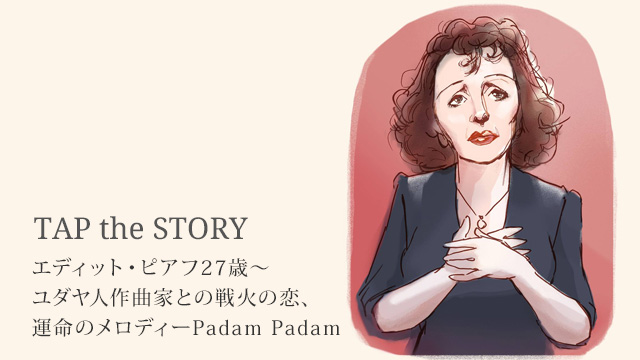稀代のシャンソン歌手、エディット・ピアフ。本名はエディット・ジョヴァンナ・ガシオン。1915年12月19日、彼女はパリ20区の貧しい地区ベルヴィル街で生まれた。
父親は大道芸人で、母親はカフェや酒場などで歌う歌手だった。幼少期は孤独で、親戚から親戚へと転々とし、祖母の経営する売春宿で育てられた時期もあった。幼い頃から“唄うこと”が大好きで、13歳で親戚の家での肩身の狭い生活を離れ、パリの道端で歌う仕事を選択する。
パリのあまり裕福でない地区ピゲールの路上で、観光客や住人相手に歌い続け、聴き入る人たちに使い古しの帽子をまわして生活費を得る暮らしを、何年もの間続けていた。その小さな体で歌う姿から“ラ・モム・ピアフ(小さなスズメ)”と呼ばれたことをきっかけに、ピアフ(スズメ)という芸名がつけられた。
──第一次世界大戦の真っ只中に生まれたピアフが、やっと独り立ちをしちようとしていた頃。ヨーロッパには“次の戦争”の足音が忍び寄っていた。いよいよ歌姫となって飛躍を遂げようとしていた1940年(当時24歳)といえば、パリがナチスドイツの占領下に置かれるという最悪の状況だった。
自由な言論の一切が禁じられることとなった戦火の下で、ピアフはウクライナ(当時オーストリア=ハンガリー帝国領)生まれの作曲家ノルベルト・グランツベルクと出会う。生後すぐにヴュルツブルク(ドイツ連邦共和国バイエルン州ウンターフランケン行政管区の郡独立都市)に移り住んで育ったという彼は、ピアフよりも5つ歳上のユダヤ人だった。
ドイツの大手映画会社UFA専属の作曲家・ピアニストとして活躍していたグランツベルクは、ゲシュタポの手から逃れてパリに移り住んでいた。パリでは亡命者への労働許可書はなく、危険でいかがわしい街の一角で、鉛筆や消しゴムを売りながら日々をしのいでいた。
着の身着のままで逃亡してきたグランツベルクは、数ヶ月後にやっとの思いでアコーディオンを手に入れて、路上で演奏したり、ダンス音楽の伴奏をしたり、小さなオーケストラと共演しながら作曲を買い取ってもらったりしながら、徐々に音楽で生計を立てていく。
場末の小さな楽団の固定メンバーとして、ピアノを弾いていた時に出会ったのがピアフだった。歌い終わると、ブリキの皿をもって客席を回り、僅かばかりのチップを集めていた。
「バルコニーで休憩していると、小柄で猫背の小娘がやってきて、さほど大きい声ではなかったけれど、彼女は瞳に異様な光をためて僕の前で歌ってみせたんだ」
長引く戦火に堪えながら、パリでは芸術家たちがどこかで「芸術で生き抜こう!」とし、そのことがまた新たな出会いを生み、新たな創造へ繋がった。
その後、グランツベルクは、出生地がポーランドだったということで、ポーランド軍の兵士として召集されてしまう。前線に向かう途中でドイツ軍の低空爆撃を受け、マルセイユの赤十字難民収容所に入ることによって兵役から解放された。
当時、マルセイユの街には、パリから避難してきた音楽家や俳優が多くいた。グランツベルクは、そこで“売れっ子”になっていたピアフに再会する。
その頃、フランスではね親独政権がユダヤ人を差別するための法律改正を押し進めようとしていた。ピアフはそれを知りながら、ピアニストとしてグランツベルクと契約し、南仏を演奏して回った。
「当時彼女は押しも押されもせぬ大スターとなっていました。最初に会った時とは声量も比較にならず、表現力も別人のようだった。ユダヤ人への差別政策が進む中、彼女は僕を選んでくれた。大所帯だった彼女の楽団にいるのは、どこよりも安全に思えました。彼女の素晴らしいコンサートの中にいる限り、音楽から生きる希望と言い知れぬチカラをもらっていました」
グランツベルクはある日、思わぬ告白を受ける。“恋多き女”として知られていたピアフは、グランツベルクに愛を打ち明けたのだ。
ちょうどその頃、アメリカに渡って成功していたグランツベルクの叔父が、亡命生活を送る彼をアメリカに呼び寄せようと、ほとんど入手不可能とされていたアメリカビザを同封して、渡米の通知を送ってきた。
ピアフは、その書類が本人の目に触れる前に横取りして隠していた。当時、ユダヤ人と一緒にいることがどんな事態を招くのか、彼女には覚悟の上だった。
1942年、27歳を迎える年に、ピアフはさらに大きなコンサートツアーに出る契約を交わす。パリから来たシンフォニーオーケストラがバックにつき、グランツベルクとしばらくの間、離れることとなる。
旅先から毎日のように、グランツベルクに手紙を書き、時には一日に3通も送る日もあった。ユダヤ人の置かれた状況、そこに関わる者に降り掛かる事態を誰よりも知るグランツベルクは、ピアフの愛に対して積極的に応えようとはしなかった。しかし、情熱的なピアフの気持ちに押され、グランツベルクはこのリスクを伴う恋を運命のような思いで受け入れていった。
翌1943年、ピアフが27歳を迎えた年、グランツベルクは一曲のドラマチックなメロディーを紡ぎ出す。そのメロディーにピアフが「パダム、パダム…」と口ずさむのを聴いて、当時の音楽ブレーンでもあったアンリ・コンテが歌詞をのせ、「Padam Padam」という歌を完成させる。
この“パダムパダム”とは、運命のメロディーを意味した。当時、この曲をめぐって“シャンソンの父”とも呼ばれた音楽家シャルル・トレネによる盗作行為が発覚する。ユダヤ人であるがゆえに、当時出版権を主張することすら困難だったグランツベルクは泣き寝入りするところだった。
ところが、これに激怒したピアフはトレネに直談判し、盗作を認めさせ、グランツベルクと出版社との間に正式な契約を結ばせたのだ。「作者/グランツベルク」として登録されることとなったこのメロディーの契約書には、異例の“但し書き”が添えられていた。
この楽曲は、ただ1人、エディット・ピアフのための作品である。
ピアフがこの歌を発表したのは8年後(1951年・当時36歳)。強い想いを込めて発表し、晩年に渡るまで大切に歌ったという。
<引用元・参考文献『愛の讃歌 エディット・ピアフの生きた時代』加藤登紀子著/徳間書店>

The Platinum Collection
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから