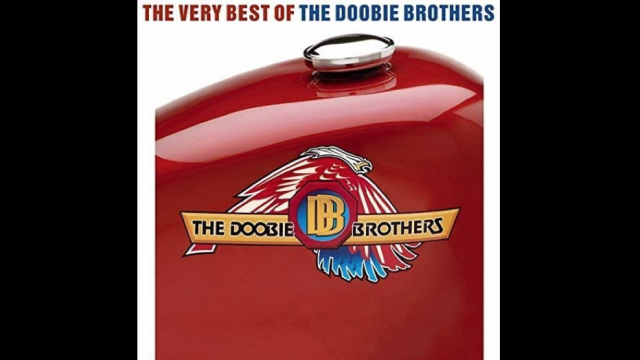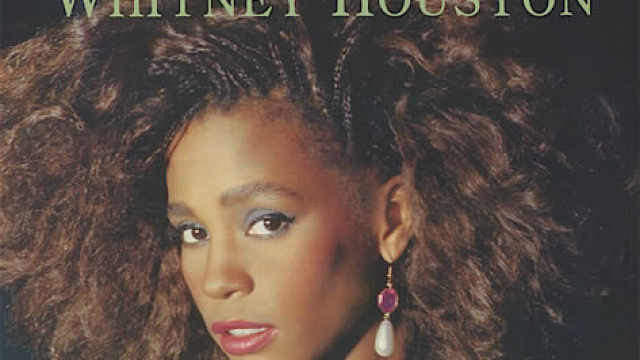「プロデュース業というのは儲かる仕事だけど、それにはそれなりの理由があるんだ。作品が完成するまではアーティストのためにほぼ24時間働かないといけないんだけど、僕にはもうそれができないよ。今の僕は自分のことの方に興味があるからね。それにプロデュースしたアルバムが大成功を納めたとしても、その栄誉にあやかれるのはアーティストであって、その逆にアルバムが失敗したときに責めを負うのはプロデューサーなんだからね!(笑)」
──パンクロック、ハードロック、グラムロック、プログレッシブロックなどなど多岐に渡る“ロックジャンル”の中に、「パブロック」と呼ばれるジャンルがある。1970年代前半からイギリスで巻き起こったムーブメントの一つだ。
ニック・ロウが在籍していたブリンズリー・シュウォーツは、“パブロックの礎”ともいえる伝説的なグループだった。
1975年、ブリンズリー・シュウォーツの解散後、ニックはグラハム・パーカー&ルーモアの名盤『Howlin’ Wind』をプロデュースし評価を得る。以降、プロデューサーとしての活動を本格的にスタートさせる。
1976年、ブリンズリー・シュウォーツ時代のマネージャーだったデイヴ・ロビンソンと、デイヴ・エドモンズのマネージャーだったジェイク・リヴィエラがスティッフ・レーベルを設立。
関係の深かったニックも、このレーベルからソロ名義でシングル「So It Goes」を発表。このレーベルはパンク、ニュー・ウェイヴ系のアーティストと次々に契約して当時の英国ロックシーンを大いに盛り上げる新進レーベルとなる。
スティッフから、自らがプロデュースしたダムド、エルヴィス・コステロを次々にデビューさせ、プロデューサーとして一躍注目を浴びる存在となる。
翌1977年にはエルヴィス・コステロと共にスティッフを離れることとなるが、この時期ドクター・フィールグッド、プリテンダーズ、カーレン・カーター(ジョニー・キャッシュの養女)など多くのアーティストのプロデュースを手がけて、当時の音楽シーンにおいて最重要人物の一人となった。
ニック・ロウは、90年代に受けたあるインタビューでこんな発言をしている。
「今でもたまにプロデュースの依頼はあるけど、僕はもうレコーディングの新たな方法についていけないんだよ。最近ではテクノロジーが目白押しだろ? それに今の音楽業界はスーツを着てパソコンをかかえた人間たちが動かしている。彼らは失敗を許さない。スタジオ代があまりに高いんで、使用するからには完璧でないとならなんだ。“今日はうまくいかなかったから明日またやってみます!”なんて言い訳は通用しないんだ。」
また、彼はあるインタビューで「素晴らしいと思うプロデューサー、あるいはプロデュースの仕事をするにあたって最も影響を受けた人を教えて下さい」という質問に対して、こんなことを語っている。
「僕が好きなプロデューサーというのは、誰がプロデュースをしたかわからないようなアルバムを作る人達なんだ。自分の経験上、それにはちょっとしたコツがあるんだよ。みんなが僕に依頼してくる理由はそのコツに秘密があるんだ。僕の好きなプロデューサーはアーメット・アーティガン(アトランティック・レコードの創設者)とビリー・シェリル(CBS/エピックで活躍したカントリー系の大御所制作者)の二人だけだ。他には誰も思いつかないね」
そのコツとは一体どんな技なのだろう? プロデューステクニック=コツをこんな風に語っている。
「例えばアーサー・アレキサンダーやオーティス・レディング、ジョージ・ジョーンズ、マール・ハガードといった人達のアルバムを聴くと、まるでストリートから曲がそのままマイクを通じて流れてきて、それが素晴らしいレコードになっているような感覚があるんだ。最近のアーティストの作品は音をいじくりまわして、そこいらに変なエフェクトをかけたりしている。そんな作業をすることを“プロデュース”なんて言っているけど、偉大なアーティストにはそんなことする必要はないんだ。本当は曲が良くてミュージシャンが上手ければプロデューサーなんて必要ないんだよ。僕は70年代から80年代にかけて色々なレコードプロデュースをしてきたんだけど…その頃はスタジオへ行って、いい日もあれば悪い日もあった。でもアーティストがうまくやれるように励ましていたよ。僕がやったことはただそれだけなんだ」
<引用元・参考文献『1995クロスビート増刊号ロックンロール』シンコーミュージック>