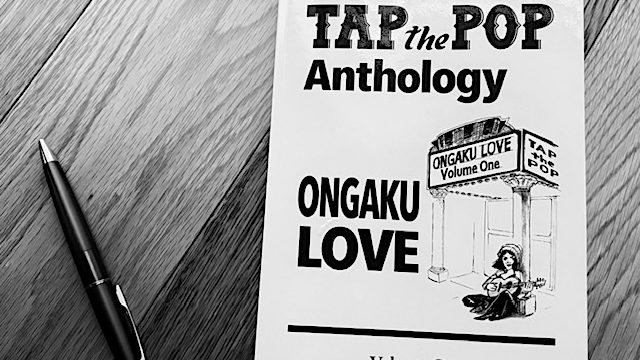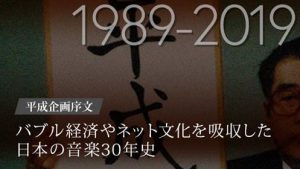流行都市TOKYOに鳴り響いたバブル80’sというパーティ(後編)
バブル──今から想えば、それはとてつもなく華やかで眩しくて、余りにもワイルドで切なかったパーティのような時代。「平成の序章」とでもいうべきあの頃に戻ろうとする時、一体どんな歌が聴こえてくるのだろう?
だが、カタログのように並べて振り返るだけでは、この時代の音楽は決して鳴り響いてくれない。大切なのは、都市部の街を舞台に心象を描いてきた若い世代の動向を捉えること。当時、人口的にもピークを迎えつつあった若者の視点に立つことによって、ポップカルチャーとしてのバブルの本質が見えてくる。音楽が聴こえてくる。
日本中が踊り狂った“バブル”。そしてそんな時代に刻まれたサウンドトラックとは? ポップカルチャー研究家でもある中野充浩が描き出す。
──第3章 J-POPとミリオンセラーの量産
昭和と平成の境目、1989年。多くのメディアが「さよなら80年代」特集を組む中(同年に昭和歌謡の象徴・美空ひばりが死去)、制御不能なバブル経済はさらに膨らみ続け、日経平均株価は年末には3万8915円の最高値を記録した。しかし、パーティを繰り広げる世代には1989年も1990年も別に変わりはなかった。時代は決して十年単位で区切れない。
音楽業界が数年間の歳月を掛けて浸透させていくことになる「J-POP」を掲げ始めたのも、ちょうどこの頃だ。CDの売り上げがアナログ盤を上回ったのは1986年。そして1989年にはアナログ盤の生産がストップして時代は完全にCDへ。
音楽を取り巻く環境にも変化が起こり、大型店舗(タワーレコード、HMV、ヴァージン・メガストアズなど)の出店、カラオケボックスの登場、レンタル店やコンサート施設の拡大、安価なCDラジカセの販売といった影響もCD普及と市場活性に一役買っていた。
歌が自分たちのライフスタイルを彩ってくれるという感覚は、CDというパッケージを得ることでより強まった。TOKYOにおいて音楽は、消費と流行に明け暮れるための“気分作り”であり、パーティを共有するための“マストアイテム”だった。若い世代はCDを毎月何枚も買うことが当たり前になった。1983年以来途絶えていたミリオンセラーが1990年以降になって量産されるのは、こうした経緯があったからだ。
きっと君は来ない
一人きりのクリスマス・イブ
Silent Night
Holly NIght
1989年から数年間、クリスマスシーズンになると必ず話題に上がる曲があった。山下達郎の「クリスマス・イブ」(1983年)だ。JR東海のCM『クリスマス・エクスプレス』の影響から始まった現象だったが、これは“遊ばなきゃ願望”の強い若者たちにとって「クリスマスこそが一大イベント」という心理を巧みについて仕掛けられたヒットだった。
この頃の人気雑誌『ポパイ』のクリスマス完全準備号のコピー「クリスマスはもう怖くない」が代弁しているように、男たちにとってこの日「プレゼントは何を買うべきか」「何を着ていくべきか」「どのレストランを予約すべきか」「どのホテルに泊まるべきか」が、一種の強迫観念のようにつきまとっていた頃。
トレンディドラマもこの空気を見逃すわけがなく、「クリスマス・イブまであと○日」と危機感を募るようにエンディングで流していた『クリスマス・イブ』からは、辛島美登里の「サイレント・イヴ」(1990年)のようなヒットも出た。
さらに夏のビーチや冬のゲレンデといったシーズンデート(ホイチョイ・プロダクションズが映画化)にも、歌は大活躍。車に乗せて連れて行くのは、何もステディな彼女や口説きたい女の子だけではない。
サザンオールスターズや松任谷由実、ドリームズ・カム・トゥルーや久保田利伸の音源はダッシュボードの中に必ず搭載された。シングルではなくアルバムニーズだったのは、会話ばかりで埋められない長いドライブにも、こうしたアーティストたちのコンセプトがカップルを退屈させずに十分に演出してくれたからだろう。


──第4章 バブル崩壊。僕が僕らしくあるために
パーティの歓声に混じって、ため息という存在に気づき始めたのは1990年の後半くらいのことだっただろうか。華やかな生活の中で自分だけが幸せになりたがったり、毎日新しい刺激があって新しい話相手がいるような光だけを追求する姿勢は、一歩間違えると時代のエアポケットの中で溺れてしまう。
クールにパーティの波に乗っかっていた者のすぐそばで、そうやって沈んで行く者もやけに目立つようになった。“遊ばなきゃ願望”の強い若者たちは、あらゆる種類の欲望を満たすことに関しては抜群のA評価だったが、デカダンスへの防衛講義には誰も参加していなかったのだ。そろそろパーティの潮時だった。
対して大人たちはどうだったのか? 海外ではベルリンの壁崩壊をはじめとする革命の嵐が吹き荒れる中、ジャパンマネーは相変わらず企業や土地買収を続けていたし、権力者たちは金とのロマンスにどっぷりと浸かったままだった。
そして遂に、ハイになり過ぎて高騰し続けていたTOKYOの地価が冷え込む時が来た。株価も下落し始め、1990年10月には3年7ヶ月ぶりに2万円台を割り込む。不動産業者の倒産、金融機関の巨額損失……1991年春、バブル経済は完全に弾けた。
一方でレコード会社にとって1991年は、記念すべきバブルの幕開けだったかもしれない。この年、ミリオンセラーはTVやCMのタイアップ効力も手伝って7作も生まれたが、特に純愛路線にシフトチェンジしたトレンディドラマの主題歌2曲=『東京ラブストーリー』から小田和正の「ラブストーリーは突然に」と『101回目のプロポーズ』からCHAGE&ASKAの「SAY YES」は、200万枚以上という記録的な売り上げだった。
しかし、ミリオンという点では、二人の無名のピアノマンの大ブレイクにこそ意味があった。一人はパーティとは無縁であるかのようなストレートな歌詞が印象的だったKANの「愛は勝つ」。
もう一人は、大学4年生のラストシーズンを描いた映画『就職戦線異状なし』(1991年初夏公開)の主題歌を歌った槙原敬之。このほぼ無名の22歳の若者は1969年生まれで、自分たちと同じ時代の空気を吸い込んでいた世代の歌い手だった。
どんなときも どんなときも
僕が僕らしくあるために
「好きなものは好き!」と
言える気持ち抱きしめていたい
どんなときも どんなときも
迷い探し続ける日々が
答えになることを僕は知ってるから
狂乱の光景の中で、自分を見失わずにいることを人知れず胸に隠しながらも、長い間浮かれ騒いだ“遊ばなきゃ願望”の強い若者たちにとって、この歌詞に含まれる「僕が僕らしくあるために」は、宴のあとの救いの言葉としてどれほどの強い力を秘めていたことだろう。
歴史上一番リッチだった青春のサウンドトラックの締めくくりとして、「どんなときも。」ほどぴったりな歌は他にない。
前編(第1〜2章)はこちらから。
平成の日本音楽シーンについてはこちらの本がオススメ

『うたのチカラ JASRACリアルカウントと日本の音楽の未来』
日本の歌と歴史を時代別/テーマ別に綴った書籍。TAP the POPのメンバーも執筆。「流行都市TOKYOに鳴り響いたバブル80’sというパーティ」「コギャルの時代に奏でられたティーンエイジ・シンフォニー」などを収録。1982〜2013年の音楽利用ランキングデータは資料性が高い。
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから
*このコラムは『うたのチカラ JASRACリアルカウントと日本の音楽の未来』収録の「流行都市TOKYOに鳴り響いたバブル80’sというパーティ」(中野充浩著)を再構築し、一部加筆しました。
*東京ポップカルチャー研究家/都市生活コラムニスト・中野充浩によるこちらのコラムもぜひお読みください(note/外部サイト)
Tokyo Pop Culture Story〜東京に描かれた時代と世代の物語1970-2020
【執筆者の紹介】
■中野充浩のプロフィール
https://www.wildflowers.jp/profile/
http://www.tapthepop.net/author/nakano
■仕事の依頼・相談、取材・出演に関するお問い合わせ
https://www.wildflowers.jp/contact/
TAP the POP協力・スペシャルイベントのご案内
【オトナの歌謡曲ソングブックコンサート in YOKOHAMA】開催

1917年に開館した横浜の歴史的建造物「横浜市開港記念会館」(ジャックの塔)で、昭和の名曲を愛する一流のアーティストが集ってコンサートを開催!
昭和に憧れる若い人からリアルタイムで昭和歌謡に慣れ親しんだ人まで、幅広い世代が一緒に楽しめるコンサートです! “国の重要文化財”という、いつもと違う空間が醸し出す特別なひとときを、感動と共にお過ごしください!!
▼日時/2025年6月7日(土曜) 開場17時/開演18時
▼場所/横浜市開港記念会館講堂(ジャックの塔)
▼出演
浜田真理子 with Marino(サックス)
畠山美由紀 with 高木大丈夫(ギター)
奇妙礼太郎 with 近藤康平(ライブペインティング)
タブレット純(司会と歌)
佐藤利明(司会と構成)
▼「チケットぴあ」にて4月5日(土曜)午前10時より販売開始 *先着順・なくなり次第終了
SS席 9,500円 (1・2階最前列)
S席 8,000円
A席 6,500円
「チケットぴあ」販売ページはこちらから
▼詳しい情報は公式サイトで
「オトナの歌謡曲ソングブックコンサート in YOKOHAMA」公式ページ