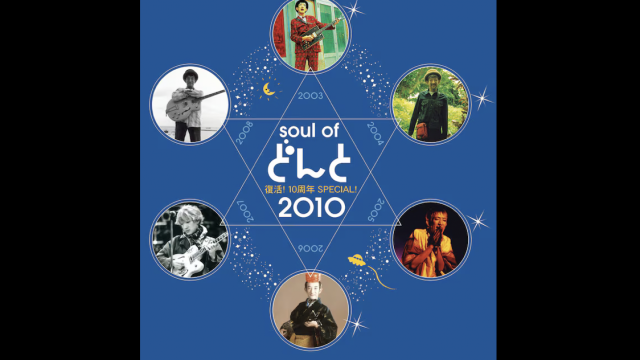作詞家の喜多條忠が、初めて浅川マキの歌に出会ったのは1968年、銀座にあったシャンソン喫茶『銀巴里』でのことだ。まだ学生だった喜多條が『銀巴里』に入ったのはまったくの偶然だが、それが人生のターニング・ポイントになった。
1968年といえば、「劇団・天井桟敷」を起ちあげた寺山修司が、シャンソン歌手だった丸山明宏を主演に迎えて、『青森県のせむし男』と『毛皮のマリー』という、二つのアングラ芝居を上演した年にあたる。それが大評判を呼んで女優、女形として、丸山明宏は脚光を浴び始めていた。
当時付き合っていた彼女と銀座に行った時、たまたま<銀巴里>の前を通りかかったんです。その日は、丸山明宏(現・美輪明宏)が出ている日で、彼女が観てみたいというので、なけなしの金で入ったんですが、その時、前座で歌っていたのが浅川マキだったんです。
丸山明宏を観るつもりが、その前座の浅川マキという歌手に魅入られてしまって、その後、一人で銀巴里に聴きに行くようになったんです。当時から「奇妙な果実」はうたってましたね。
その頃の浅川マキは、前年に「東京挽歌」でデビューしたものの、レコードがまったく売れず、キャバレーまわりや営業の仕事にもなじめず、銀巴里で月に一回くらい、ビリー・ホリデイの「奇妙な果実」や自作の「夜が明けたら」などを歌っていた。
前座が出る時間帯は客席も空いていたので、喜多條は昼から夜まで半日ぐらい銀巴里で過ごしたという。1960年代の大学生はまだ世間では尊重されていて、寛大に見られるところがあった。
喜多條は浅川マキの歌を聴きながら、ノートを広げて詩などの書きものをしていた。歌手がうたっているのに顔もあげないで、ノートに何かを書いている客がいることに気づいて、浅川マキは客席まで降りていって「何書いてるの?」と聞いた。
「マキさんの歌を聴いていると、いろいろと言葉が浮かんでくるんです」って言って書いたものを見せると、あの口調で「やるわね、学生さん」って言われまして。
それがきっかけで喜多條は、浅川マキに寺本幸司を紹介される。才能と才能はこんなふうに、何かに導かれるように出会っていくのだろう。
プロデューサーだった寺本は、六本木のミカドビルにあった事務所で、毎月一回ぐらい詩や音楽の勉強会を開いていた。
そこには、浅川マキと中島みゆきの写真で有名になるカメラマンの田村仁や、ジャックスの早川義夫、早川とともに歌を書いていた相沢靖子、フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」が大ヒットしたデザイナーの松山猛、シンガー・ソングライターの南正人などが集っていた。
その集まりに参加するようになった喜多條は、浅川マキのアルバム『MAKIⅡ』(1971年9月5日)で、「雪の海」という曲を作詞することになる。
しかし、浅川マキに詞を提供する前、1970年には最初のレコードが出ていた。大学を中退して文化放送の番組で台本を書いていた時に、南こうせつから頼まれて、初めて歌詞を書いた「ピラニアのために」である。
これが第一期・かぐや姫によって、「マキシーのために」というタイトルでシングル盤になったのだ。
この歌に出てくる主人公マキシー(原詩ではピラニア)は、実在した喜多條忠の友人だった。学生運動が盛んだった頃によく知られていた女性活動家で、喰らいついたら離れないので“ピラニア”と呼ばれていた。
浅川マキに「やるわね、学生さん」と言われた大学生は、やがてかぐや姫に提供した「神田川」の大ヒットによって、作詞家としての成功を掴むことになる。
注・喜多條忠の発言は「ロング・グッドバイ 浅川マキの世界」(白夜書房)からの引用です。

「レッツ・ゴー! かぐや姫」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから