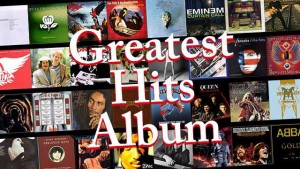音楽ファンに衝撃をもたらした「ギブソン経営破綻か」というニュースをめぐって、朝日新聞の「耕論」というページに3人の識者による見解が取り上げられたのは、2018年5月15日のことだった。
高級エレキギターで知られる米ギブソンが経営破綻した。若者のロック離れが言われるなか、エレキが音楽シーンにおいて「永遠の詩」だった時代は終わるのか。
そのなかで「楽譜には書けぬ情動がある」という見出しで、椎名林檎の発言をまとめた記事が、エレキギターの本質のみならず、ロックもしくは音楽の本質までもわかりやすく伝えていた。
椎名林檎は、幼いころから「型」が決まっているピアノやクラシックバレエを習っていたので、「型」を学べば学ぶほど、「型破り」の尊さや難しさを思い知ったという。
だから「型」になる以前の「初期衝動」を、エレキギターが具体的な音として鳴らすことができる点において、時代が移り変わっても廃れないと述べていた。
掛け持ちでいくつものバンドをやっていた高校生のころから、椎名林檎はエレキギターに担ってほしい役割を決めていたそうだ。
それは「いらだち」「怒り」「憎しみ」「やり場のない悲しみ」‥‥、そういった「負の感情」の表現をすることであり、そこにはノイズをともなうエレキギターならではの歪んだ音色が必須だった。
エレキのプレーは音符に表した途端に面白みを失います。音色一発の魅力ありきだから。実際にはあらゆるタイミングが合致して、授かりもののような音が生まれます。そこにこそエレキの本質が宿ると思います。生々しいボーカルと、エレキギターのプレーだけは、今後もコンピューターでは再現できないでしょう。(朝日新聞からの引用)
エレキギターの美点は音符に書けない表現ができることだが、それを実際にかたちにしてみせるには、音楽を生みだすための「初期衝動」が不可欠だ。
「ロックしたい!」という「初期衝動」さえあれば可能性は生まれるが、逆にそれがなければカタチにはならない。
椎名林檎は、2000年1月26日に発表した「ギブス」で、ニルヴァーナのカート・コバーンと奥さんのコートニー・ラヴを歌詞に登場させている。
ノイジーなギター・サウンドでグランジ・ブームを起こし、ロックの流れを変えたといわれたニルヴァーナには、パンクに通じる「初期衝動」があった。
その一方で、カートは大ヒットしたニルヴァーナのアルバム『Nevermind』で、実際に起こった婦女暴行事件を題材にしたシンプルな弾き語りに近いスタイルで、「Polly」を歌っている。
それを聴いてボブ・ディランは一言、「彼にはハートはあるね」と口にしたという。
フォークシンガーとして注目を集めていた若き日のディランは、ギターの弾き語りというスタイルで音楽シーンに登場した。
だが、1965年にアルバム『Bringing It All Back Home』を発表し、そこからは急速にロックへ接近していった。
そして7月25日、ニューポート・フォーク・フェスティヴァルの最終日にはロックバンドとともに、自らもエレキギターを持ってステージに現れた。それに対して観客からは激しいブーイングを浴びせられ、ステージから降りるという事件が起こった。
当時は、ロックやエレキギターが商業主義に直結していると思われて、フォークソングのファンから反感を買ったのである。
しかし、ディランは言葉でメッセージを伝えるフォークの弾き語りスタイルに限界を感じて、サウンドによる表現が可能なロックという新しいスタイルを選んだ。それによって自らの音楽の初期衝動を、あらためてカタチにして見せたのである。
その年の12月、ディランは『追憶のハイウェイ61(Highway 61 Revisited)』を発表する。そこに収められた「ライク・ア・ローリング・ストーン(Like a Rolling Stone)」は、ロック史上に輝く名曲となって世界中に広まっていった。

椎名林檎「勝訴ストリップ」

ニルヴァーナ「Nevermind」

ボブ・ディラン「Highway 61 Revisited」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから