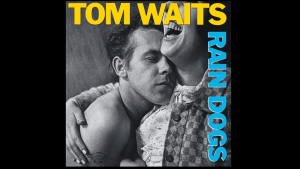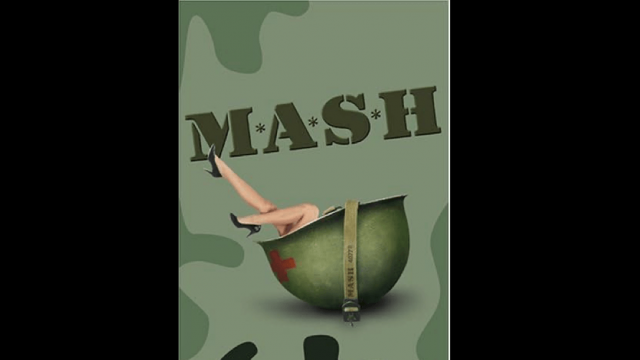オーストラリア、第二の国歌
唇の動きを読まれてまで歌わせられる国歌を持つ国民より、歌うなと言われても、つい口ずさんでしまう愛唱歌がたまたま国歌だったという国民の方が、どんなに気楽なことだろう?
オーストラリアは、国歌の選択を国民に委ねましました。1977年に行われた国民投票で第2位に選ばれたのが「Waltzing Matilda」。公式の場では1位に選ばれた国歌が使われていますが、国民の大多数は納得せず、「Waltzing Matilda」は「第2の国歌」(Second Anthem)」という尊称で親しまれています。
広大な大地に恵まれたオーストラリア(日本の20倍)は「眠れる大陸」と呼ばれていました。1828年に全土が英国領になりましたが、放牧や紡績業でのんびりやってきた国を眠りから覚まさせたのは、1850年、ヴィクトリア州での金鉱発見でした。
ゴールド・ラッシュで世界中から押し寄せた人々の土地争いのせいで、先住民族たちや彼らとともに平和に暮らして貧しい人々たちも、住みついたブッシュ(灌木地帯)から追いたてられます。国は豊かになったのですが、徴税も警察権力も厳しくなり、大らかな気風が失われてしまった。そんな頃、この歌は書かれました。
マチルダとは、どんな美人か?
「Waltzing Matilda」の詞を書いたのはアンドルー・バートン・パターソンという人物で、1895年のことです(作曲は女性)。彼は弁護士やジャーナリスト、従軍記者など多彩な経歴を持つ地方の名士でしたが、バンジョーという雅号でオーストラリアの民話などを描いたバラードを発表。詩人として人気を博していました。彼自身は都市生活者でしたが、その昔、貧しいけれど反骨の男たちが生きていた土地に郷愁を覚えていたといわれます。
マチルダとはいったいどんな女性なのか? マチルダとは金鉱堀りたちが旅の道具を担いで運ぶ「ズダ袋」のようなもの。ひとり寝の寂しさをせめて紛らわせようとつけた女の愛称。美女も出てこないし、ワルツも踊らない。詩をよく読むと、えばりくさって駆けつける警官がサラブレッドに乗っていたりとか、ちょっぴり皮肉もきかせたひとくち噺なっています。
ひとりの陽気な放浪者 沼のそばで野宿してた
ユーカリの木陰で歌ってた お湯の沸くのを待ちながら
誰と一緒に旅に出ようか?
マチルダ担いで放浪の旅 誰と一緒に旅に出ようか
お湯が沸くのを待ちながら 誰と一緒に旅に出ようか
羊が沼地にやってきた 大喜びで捕まえて 羊を袋に詰め込んだ
「お前と一緒に旅に出よう」
馬で主人が駆けつけた
後から警官やってきた
「誰の羊を袋に入れた」
沼に飛び込む放浪者
「生きてお前らには捕まらねえよ」
彼の幽霊見かけるかもね
「誰と一緒に旅に出ようか?」
(訳「世界の民謡・童謡」より)
『渚にて』で世界的な歌に
怒涛のような波しぶきをあげ、メルボルンの港に浮上する巨大な原子力潜水艦。緊急信号の警笛が港いっぱいに響きわたっても反応はなく、港湾に人影はおろか、生活反応が消えている。
スタンリー・クレイマー監督の『渚にて』(1959年)はそんなシーンから始まります。第三次世界大戦が勃発。高性能核爆弾の応酬の果て、戦争は終わったものの、世界中は既に致死量の放射性物質におおわれ、北半球の諸国はすでに壊滅。生き残った潜水艦が、最後に残された南半球にまで下ってきたという設定です。
そのシーンから「Waltzing Matilda」のメロディがかすかににかぶります。映画『渚にて』は、まるでこの一曲のために奉げられたかのように、重要な場面で役割を果たします。
これが人類最後の鱒釣りとなることを知っていながら、メルボルンの市民は、解禁日をくりあげることを決め、人々は川のほとりに集まってきます。なりふりかまわず、釣りに興じる男女のなかから、誰かれなくわき上がる「Waltzing Matilda」。男性コーラスが、夜通し途絶えることなく響き渡ります。
生きていることの素晴らしさ。パンドラの匣(はこ)、核戦争の蓋をあけてしまった人の愚かさ。立ちすくみながらも、みんなで声をかぎりに歌う。この作品のクライマックスであり、カタストロフです。
T・S・エリオットの予言
死者一人みせることなく核戦争の恐怖を描ききった『渚にて』の反響は大きく、封切りの次の年、1960年に「Waltzing Matilda」は、ビルボードチャートに41位に登場。フォーク・ソングと紹介されています。
この『渚にて』には原作があります。SF作家ネヴィル・シュートによって、1957年に書かれた同名の作品の巻頭には、イギリスの詩人、T・S・エリオット(1888~1965)の詩が引用されています。人類の終末とは緩慢なもので、静けさに満ちたものだろうと、エリオットは予言していたのです。
このいやはての集いの場所に
我ら ともどもに手探りつつ
言葉もなくて
この潮満る渚に集う
かくて世の終わりきたりぬ
かくて世の終わりきたりぬ
地軸くずれるとどろきもなく
ただひそやかに
(井上勇訳)
トム・ウェイツ VS ロッド・スチュワート
1976年、トム・ウェイツは、アルバム『Small Change』を発表しますが、その冒頭におかれたのが、「Tom Traubert’s Blues」でした。この作品は、トム・ウェイツが惚れ込んだ「Waltzing Matilda」の一節を生かし、巧みに蘇らせた作品でした。
ウェイツの作品としては初めてアルバムチャート100位に入り、ウェイツの最高傑作とまでいわれた「Tom Traubert’s Blues」でしたが、1992年には、ロッド・スチュワートが、シングルA面で挑戦し、このシングルは全英チャートで6位となり、5週連続トップ10にランキングされています。

(このコラムは2014年3月30日に公開されたものに加筆修正を施したものです)