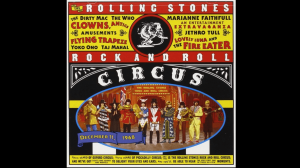ジャズは時代の流れとともに大きく変化してきたが、その中で常に先頭に立ち、時に自ら変革をもたらしたのがマイルス・デイヴィスだ。
1949年頃に録音された『クールの誕生』では、当時全盛だったチャーリー・パーカーらの火を吹くような激しいアドリブとは相反する、誰でも気軽に聴ける落ち着いたスタイルを打ち出し、のちにクール・ジャズと呼ばれるようになった。
1959年に発表した『カインド・オブ・ブルー』では、譜面からコード進行という概念を取り払ったモード・ジャズを確立させる。
60年代後半頃から、マイルスの音楽はそれまでジャズと呼ばれていたものからどんどん離れていった。
常に成長と変化を求め、次の音を模索し続けるマイルスが取り入れたのが電子楽器であり、ロックだった。
マイルスの作品の中でも1つの頂点に数えられる『ビッチェズ・ブリュー』(1969年)ではジャズともロックとも言い切れない、マイルス独自の世界が描かれている。
この作品の成功によって白人のロックファンを獲得してロックフェスにも呼ばれるようになったマイルスだが、それまでのジャズ・ファンを失ったのはもちろん、黒人からの支持も減りつつあった。
そこで今度は若い黒人に向けてファンクと現代音楽の旗手、シュトックハウゼンの空間音楽理論を融合させた『オン・ザ・コーナー』を発表する。
バンドから生粋のジャズメンは減っていき、代わりにスティーヴィー・ワンダーのもとで弾いていたベーシストのマイケル・ヘンダーソン、ジミ・ヘンドリックスのようなリズム・ギターが弾けるピート・コージー、アフリカンなリズムを叩けるパーカッショニストのエムトゥーメといったメンバーが加入した。
もし全員がそのまま続けていたら、もっともっとすばらしいバンドになったことは間違いない。
だが、そうはうまくいかなかった。オレの健康状態ががたがたになったからだ。
マイルスが交通事故を起こしたのは1972年10月のことだった。
睡眠薬を飲んで寝ようとしたが眠れそうになかったので、車でハーレムに向かっていたところを分離帯に突っ込んでしまったのだ。
幸い命に別状はなかったものの、両足を骨折したうえにお尻も痛めてしまい、後遺症となってその後のマイルスを悩ませ続けることとなる。
1974年には公演先のブラジルでコカインやマリファナなどを併用して急に体調が悪くなり、緊急入院するというトラブルも起きた。
これがきっかけでマイルスは音楽をやめることを真剣に考えはじめたという。
翌1975年1月、マイルスは3度目となる来日を果たす。
22日の東京公演を皮切りに2週間かけて名古屋、京都、札幌、小倉、大阪、宮城と全国を回り、2月8日の東京がツアー・ファイナルとなった。
マイルスの身体は満身創痍といってもいいほど不調だったが、一方でバンドの状態は最高だった。
ドラムとベースが強靭なリズムを生み出し、その空間を埋めるようにギターがリズムを刻み、パーカッションが鳴り響く。それらがマイルスの意思で一体となり、ダイナミックに展開していく。
ロック、ブルース、ファンク、現代音楽などを取り込み自身の音楽を追求し続けてきたマイルスが辿り着いた1つの完成形ともいうべき内容だった。
ツアーを終えたマイルスはトランペットを置き、それから5年間表舞台から姿を消すこととなる。
体調不良はもちろん、精神的にも限界がきていたという。
オレは本当に長い間、音楽だけに生きてきた。
芸術的にすべてを出し切った気がして、音楽的にも、もうこれ以上何も言うことがないような気がしていた。
日本公演の一部はCBSソニーが日本独自の企画としてリリースするために録音、その中から2月1日の大阪公演で演奏された昼の部が『アガルタ』、夜の部が『パンゲア』としてリリースされた。
結果として1975年の来日公演を収録した2枚のアルバムは、およそ30年に渡って走り続けたマイルスが隠居前に残した最後のアルバムとなった。
アルバムジャケットそれぞれ横尾忠則、そして田島照久が手がけており、ライナーノーツには注釈としてこう書かれている。
このレコードは住宅事情の許すかぎりボリュームを上げて、お聴きください。
引用元:『マイルス・デイビス自叙伝Ⅱ』マイルス・デイビス、クインシー・トループ著 中山康樹訳(宝島社文庫)
(このコラムは2016年5月10日に公開されたものです)