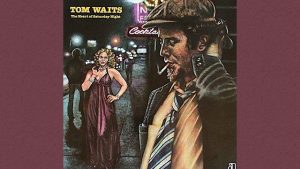50年近くにもおよぶ音楽キャリアを誇る泉谷しげるがこれまでリリースしてきたアルバムの中で最高傑作と言う人も多い『’80のバラッド』(1978年10月25日発売)。
泉谷の代表曲「春夏秋冬」(1972年)のプロデュースを手掛けたことでも知られる加藤和彦とのタッグによる作品で、アレンジを含めレコーディングテクニックの細部に渡って、洗練されたセンスが光る作品である。
1977年、フォーライフを退職した泉谷しげるは、1978年にワーナー・パイオニア(現ワーナーミュージック・ジャパン)の洋楽部門レーベル“アサイラム(Asylum)”に移籍をした。
吉田建、島村英二、柴山和彦、中西康晴などの腕利きプレイヤーを招いて生まれたロックサウンドは、当時の洋楽ファンをも唸らせたという。
グアムでレコーディングされたそのアルバムのライナーノーツには詩人・中山容の筆によってこんな言葉が綴られていた。
「あのたくましく、しかしさびしげな肉声は変わっていない。むしろはるかに強く自信に満ちている。以前のやや破壊的でせっかちな焦燥感がなくなり、声そのものに一層深いエロチシズムを感じた。」
当時、フォーライフ設立からの激動期を過ごし…心身共に疲れきっていた泉谷は、同アルバムのために「裸の街」という歌を書き下ろした。
「この曲は最初“肉弾列車と赤いバラ”っていうとんでもないタイトルがついていたんだ(笑)歌詞もこんなのではなくて、ベトナムは出てくるわ、世界の亀裂は始まるわ、四次元の世界は出てくるわで、実際ひどいもんだった(笑)で、あまりにもとっ散らかり過ぎてたんで“こりゃまずい!”ってんで書き直したってわけ。」
当時、歌詞を書き下ろす際に、泉谷にはある“やり方”があったという。
まず最初に物語を書く。
それは一曲分で原稿用紙に10枚にも及ぶという。
そしてそれをビリビリに破る…。
破った紙を一緒くたにして、ジグソーパズルのように並び替えたり羅列してみる。
「意味が通じるところと通じないところが出てくるわけよ。それで言葉とかセンテンスの決まりを合わせていくって感じかな。だから俺の場合、直接性と抽象性のバランスのスレスレのところにいるってわけ。どっちかに転んじゃうとダメで、結構難しいんだよよ、これが。」
こうして泉谷が選んだ“言葉の変化”は、音と同時進行で進んでいったという。
泉谷は「裸の街」の歌詞の世界観から“埃っぽい音”を加藤に要求した。
「凄く視覚的な曲なんだよ。特に“ブルーランプの下で…”ってフレーズの所にくると一つの絵が出て浮び上がるんだ。その辺りが好きだなぁ。音だけだとどうしてもきれいになりがちだろ。ある近未来のイメージみたいなものを求めちゃうからね。だからこの曲は“そうでないもの”を描くために、色んなものを捨てていった。加藤さんにアレンジ面でずいぶんと苦労かけたのを憶えている。だけど、この曲と“翼なき野郎ども”の2曲が完成したら、後は凄く楽だったよね。その2曲がアルバムの核で、他は枝って感じだったからな。」
<引用元・参考文献『わが奔走—IT’S MY LIFE』泉谷しげる著(ロックキング・オン)>
<引用元・参考文献『永遠のザ・フォーク・クルセダーズ ~若い加藤和彦のように』田家秀樹(ヤマハミュージックメディア)>