1968年生まれの小沢健二はドイツ文学者の父、心理学者の母をもち、クラシックのレコードと並んでビートルズのボックスがある、そんな音楽環境の家庭に育った。
父親の仕事の都合で日本からドイツに引っ越したのは、生まれてまもなくのことだった。
だから家ではクリスマスやイースターになると、ドイツ語のキリスト教音楽のレコードが流れていた。
ドイツで数年間を過ごした幼少期を経て、日本に戻ってきてからも両親はそれらのレコードを、ときおり家でかけていた。
それを聴くと小沢健二はいつも、不思議な気持ちになったという。
そのことを大学時代のゼミの恩師である翻訳家、柴田元幸氏の質問に答える形の対話で、2011年にこう述べている。
小学生の僕はそれを聴くと、不思議な気持ちがやってきて、全然違う場所の空気が匂ってくるような気がするものでした。「なんでこの音楽を聴くと、どこか違う時と場所にいるような気持ちになるんだろう?」と、まあ、そんな風に言葉にはならないのですが、そんな驚きを繰り返し経験したのをよく憶えています。
今考えると、アナログ・レコードは大きいし、紙のジャケットの匂いも強いから、それも関係しているかもしれません。どこの国のレコードジャケットも、その国の匂いがする気がしませんか?
(柴田元幸編『モンキービジネス 2011 Summer vol.14 いま必要なもの号 「音楽と生活 小沢健二』ヴィレッジプレス)
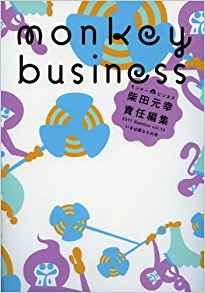
アナログ・レコードで育った人なら体験した人も多いだろうが、アメリカやイギリスから輸入されたレコードからは日本製には感じられない、独特の匂いがほのかに漂ってきたものだ。
それはインクや紙、コーティング剤の入り混じった匂いだったのだろう。
しかもどういうわけかレコードの匂いは、郷愁を誘うものであった。
海外から輸入されてきたレコードの匂いが、どうして知らない土地の郷愁を感じさせたのか?
確かにそれは、不思議なことだった。
どこかで音楽というものがもっている力、あるいは音楽だけが起こせるマジックにつながっているのかもしれない。
そう考えていくと日本のレコードも、日本ならではの匂いをきっと持っていたのだろう。
日本にいたのでは決して気がつくことのない匂いについて、小沢健二はニューヨークに住んでいた自分の体験を話している。
今は国外で暮しているので、日本製のレコードジャケットの匂いに気がつきます。その匂いは日本いると、ちょうど自分の家の匂いに気がつかないように、気がつかない気がします。
日本製のレコードジャケットの匂いは、やはり和紙っぽい匂いがします。
音楽がデジタル化されて手軽で便利になった分だけ、失われたものもが確かにあることがわかってくる。
CDはレコードに比べると紙が小さいからか、アナログほどは匂わないという。
アフリカで買ったCDなどをニューヨークに帰ってきて開封すると、しぶとくアフリカの匂いが漂ってくる気がします。
日本のCDも、清潔な駅ビルのような匂いがほのかにするかもしれません。
当たり前ですが、匂いはないですよね、ダウンロードすると。
アナログ・レコードならではの大きなジャケットという魅力には、目に見える情報量や手に取った質感だけでなく、使われている紙やインクの匂いまでも含んでいた。
音楽は耳で聴くだけではないという事実を、あらためて気づかされる。
柴田元幸氏との一問一答のなかで印象的だったのは、「音楽を聴いていない/演奏していないときでも、頭のなかで音楽が鳴っていますか」という質問に対する答えである。
例えば曲を聴くと、その曲にまつわる記憶が甦ったりします。頭の中で、音ではないのかもしれないけれど、何かが鳴る。
過去の記憶だけではなくて、未来も鳴っていることがあります。例えば、アーティストが素晴らしい新曲を演奏しているのを聴いて、その曲の未来の絵が見えて高揚する、という経験をしたことのある人はきっといるともいます。
〈略〉
だから、頭の中で鳴っている音楽というのは、証明のしようがないのに、僕らは確かにその存在を知っている、幽霊みたいなものかもしれませんし、もっと言うと、音楽そのものなのかもしれません。
たしかに音楽を受けとめる人の頭の中では、いつだってその人の音楽が現在形で鳴っている。
そして小沢健二は恩師の「音楽の力とか、文学(文章)の力というものはあると思われますか? あるとしたら、それはいったいどんなものでしょうか」という質問にも、こう明言していた。
あると思います。念力のように、何かを動かす力だと思います。
代表曲の「愛し愛されて生きるのさ」で、そのことを確かめてみてはいかがだろうか?
(注)文中の発言はいずれも、(柴田元幸編『モンキービジネス 2011 Summer vol.14 いま必要なもの号 「音楽と生活 小沢健二』ヴィレッジプレス)からの引用です。













