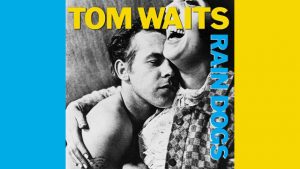1964年、21歳だった荒木とよひさは日本大学芸術学部に在学していた時にスキーの事故で下半身を複雑骨折して2年半に及ぶ長期入院を余儀なくされた。
長い長い治療生活を送る中“死ぬほど退屈だった”という理由から、とくに作曲の経験もないまま自作の歌を紡いで世話になった看護師たちにプレゼントしたという。
その歌はたちまち病院内で評判となり、看護師たちが地域のボランティアの催しなどで唄うことで、徐々に広がっていったという。
彼自身、入院中の暇つぶしに作ってみた曲が、後に国民的人気を博す歌になろうとは夢にも思ってなかった。
少しの時が流れ…1972年、29歳となった彼は数年前に自作した一曲の歌によって人生の大きな転機を迎えることとなる。
偶然、同時期にその歌を耳にした二つのレコード会社のディレクターが、いぬいゆみ、片山知子の二人の歌手にそれぞれ歌わせてレコード化する。
そのすぐ後に人気男性ボーカルグループのダークダックスが歌ったバージョンもリリースされたが…当時はいずれもあまり話題にはならなかったという。
そしてまた少しの歳月が流れ…1976年の6月、今度はニッポン放送の人気ラジオ生番組『あおぞらワイド』に、横浜の主婦から一本のリクエスト電話がかかってきた。
「四季の歌を聴きたい。」
しかし、当時番組の司会をしていた歌手・立川清登(すみと)は、その歌を知らなかった。
「どんな歌なのですか?」
受話器越しに聞き返すと、その主婦は電話口でいきなり“四季の歌”を歌い出したのである。
それを聴いた立川は感動し、番組の中で絶賛したという。
今度はその放送を聴いたリスナーが騒ぎ出し、歌は反響を呼ぶこととなった。
その反響の大きさに驚いたレコード会社6社が“競作”という形で「四季の歌」を次々とレコード化した。
ラジオ番組で絶賛した立川清登をはじめ、菅原保徳など10人にも及ぶ当時の叙情歌手たちがこぞってその歌をレパートリーにした。
その顔ぶれの中には、当時テレビやラジオの番組でレギュラーを何本も務めながら全国展開でコンサート活動も行っていた芹洋子(せりようこ)もいた。
芹は5年前に“四季の歌”と出会い、ことあるごとに「私のテーマソングです。」と言ってステージで歌い続けてきたという。
この年の11月には自身のアルバム『四季の抒情』に収録して発表。
芹の歌った“四季の歌”は翌年にミリオンセラーを記録する。
清楚で叙情的な芹の歌声に加え、誰もが口ずさめる8小節のシンプルなメロディーのくり返し、そして老若男女が素直に歌える覚えやすい歌詞がヒットの理由だった。
3番の歌詞に出てくる“愛を語るハイネのような”という洒落た表現も、当時の人々には新鮮に響いたと言われている。
作詞家・荒木とよひさはその後、テレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」「つぐない」「愛人」、森昌子の「哀しみ本線日本海」、人気テレビ番組『欽どこ』から生まれたグループ・わらべの「めだかの兄弟」など次々とヒット作を手掛けてゆく。
演歌からポップスまで、その作品は幅広いジャンルに渡り、現在までの作品数は2000曲以上に及ぶという。
そして…1981年には、芹洋子が中国の北京で初めての“国賓女性歌手”としてコンサートを行い「四季の歌」を披露した。
その後大反響を呼び、中国語でも歌われるようになったという。
スキーで骨折をして入院生活をしていた青年が“死ぬほど退屈だった”という理由から書いた歌は、国境を越えて愛される叙情歌に育っていった…。
<引用元・参考文献『私の心の歌〜雪の降る街を〜』(学習研究社)>