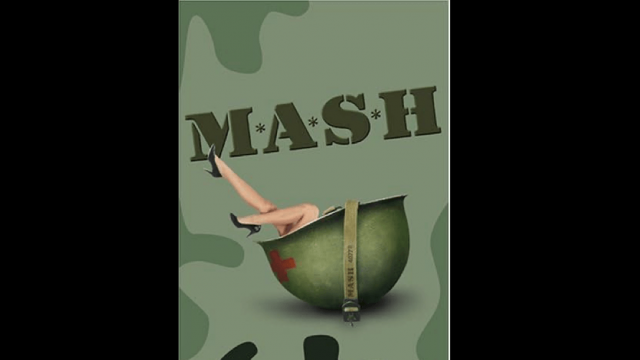「本牧メルヘン」
歌っている鹿内孝は、ウエスタン・カーニバル出身のロカビリーの人気スター。曲を描いたのは、鹿内のバンド・ボーイからほどなく「ブルー・コメッツ」を率いて、GSの頂点に立つことになる井上忠夫。
「本牧メルヘン」は、ロカビリーからグループ・サウンズへというポップスの流れの中に位置していた。情緒的な語感からもそれが感じられる
本牧で死んだ子は鴎になったよ
あざやかなワンフレーズは、やはり阿久悠だった。
「当時ぼくは、歌から感じられる景色が、無国籍になるように心掛けていた。この歌は横浜の本牧を舞台にして書いているが、吹く風や匂いは無国籍である。
1972年に書いたものだが、1970年代の初めの頃は、寂しさと言うのが、死ぬ価値があったような時代である。僕の詞にも理由なき厭世感的な気分の詞がかなりある。あのころ、誰を恨むでも責めるでもなく、さびしさを時代の象徴のように少年たちや少女たちは胸に抱え込んでいた」
阿久はそう書いている。
阿久悠は、翌年、「ジョニィへの伝言」(1973年3月)、「五番街のマリーへ」(1973年10月)を出すが、このときすでに「本牧メルヘン」の中に、ジョニーはスミスとともに登場していたのである。
五番街とは、けして、「フィフス・アベニュー」などではないだろう。
この世にあってない、どことなく懐かしい異郷の街が眼に浮かんでくる。
「カスバの女」
この曲が世に出るまでには、いきさつがあった。
1954年のこと。韓国の作曲家、孫牧人(ソン・モギン)が、ギターを片手に大高ひさを訪ね、書きあげたばかりの曲を聴いてもらう。テイチク・レコードで、長年にわたって、流行歌を書いてきたベテランの作詞家だった大高は、力強いメロディに圧倒されるが、孫の言うように、「歌詞が弱い」と感じた。「このまま日本の演歌にしてしまったら、ものまねに終わってしまう」
このとき、ひらめいたのが、大高が戦時中くりかえし見ていた一本の映画、1937年に公開されたジャン・ギャバンの名作、『望郷 ペペルモコ』だった。
アルジェリアの無法地帯カスバに逃げ込んだお尋ね者、ジャン・ギャバンがカスバの路地裏をさまようという設定を、酒場女がひとり、砂漠の果てまで流れてきたわが身を呪う・・というシーンに置き変えた歌詞が浮かんだ。
この曲は、エト邦枝という歌手で、1955年に発表されるが、鳴かず飛ばず。
映画の主題歌にという話もあったが、映画が製作中止となり、エト邦枝も、歌の世界から身を引くことになる。
ところが、それから12年して、奇跡が訪れる。
緑川アコのカバーをかわきりに、竹腰ひろ子、沢たまき、扇ひろ子らがこぞってカバー。この年だけでなんと、13人の歌手がこの曲を歌った。カバーは、たえることなく続き、青江美奈,藤圭子、八代亜紀、ちあきなおみ、さらには、美空ひばりにも、愛唱された。
実力のある歌手にとって、つまり聴かせどころを知っている歌手にとって、これほど歌い映えする歌はなかったのだ。
「今時代は閉塞感に満ちている。息苦しい。出口もないし風穴さえあかない。しかし、ぼくらは、この時代の中で呼吸をして生きなければならない。かつて、日本の歌は風穴をあけるほどの力を持っていた。風穴をあけたいと思って僕らは歌を作った」
阿久悠はそう書き残している。
「参考資料」
「なぜか売れなかったが、愛しい歌」阿久悠著 河出書房新社刊
緑川アコ「カスバの女」
藤圭子「カスバの女」
ちあきなおみ「カスバの女」