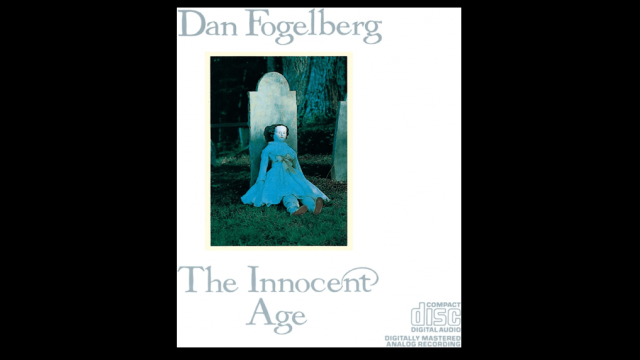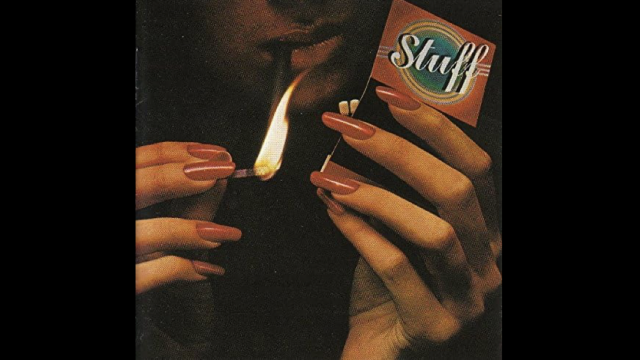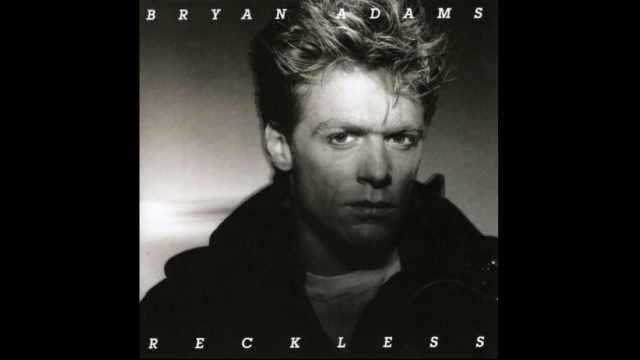クリスマス・イヴにコンサートがブッキングされていないことは、ひとつの奇跡だった。
少なくとも、レコード・デビューして以来、イヴやクリスマスの日には、いつもどこかの街のステージに立ってきた。だが、その年は何故か、ぽっかりとスケジュールが空いていたのだ。彼は生まれ育った故郷で、ひとり静かに過ごすことにした。
その日は朝から雪が舞っていた。静かな、聖なる冬の日を祝うため、彼は食料品ストアに出かけた。雪の中、ひとり車を運転しながら、彼は夢を見ているような、不思議な気分にとらわれていた。それほど、目の前にある現実が彼の日々とかけ離れていたからである。
その感覚は、ストアに着いてからも変わらなかった。だからだろう、そこにかつての恋人の姿を見つけた時も、彼はそれほど驚かなかった。冷凍食品売場のかげに隠れ、彼は彼女が近づいてくるのを待った。そして彼女が通り過ぎようとすると、彼女の袖を引っ張った。
驚いたような表情。何が起こったのか、彼女には最初、わからないようだった。だが次の瞬間、その目を大きく見開き、彼を抱きしめようとした。その結果、彼女は持っていた財布の中身をフロアに撒き散らすことになった。ふたりは笑った。いつまでも笑った。そして彼女の笑い声はいつしか、涙声に変わっていった。
ふたりは彼女の買った食料品をレジに運んだ。値段が打ち込まれ、食料品がバッグに詰め込まれていく。だが、支払いを済ませた後でも、ふたりの会話は終わらなかった。ちょっと飲んでいこうか、ということになったが、近くに空いているバーはなかった。結局、ふたりは酒屋で6パック入りのビールを買い、彼女の車で飲むことにした。
純粋な心に。そして今この時に。ふたりは乾杯をした。
空白の時間を埋めようと、彼も彼女も思ったが、ふたりともどうすればいいのかは、わからなかった。仕方なく、彼女は「それから」を語り始めた。彼女は建築家と結婚していた。暖かく、安心して暮らせていると彼女は言った。だが、彼のことを愛している、とは彼女は言わなかった。
元気そうで何よりだ、と彼は言った。そして彼女の瞳が昔と同じブルーであることを称えた。その時、彼女の瞳の中がかすかに揺れた。彼にはそれが、疑いなのか、感謝を意味するのかわからなかった。
レコード店でみかけるから、元気にやっているんだろうと思っていた、と彼女は言った。ああ、観衆は素晴らしいけど、ツアーは地獄だよ、と彼は言った。
ビールを飲み終える頃には、ふたりとも話し疲れているようだったし、もうそれほど話すことも残っていなかった。そして彼女は彼に口づけ、彼は車から降りると、彼女が走り去っていくのを眺めていた。
学生時代に戻ったような、懐かしい心の痛みを抱えながら、彼は自分の車に戻り、家へと向かった。気がつくと、雪は雨に変わっていた。
“Same Old Lang Syne”
(このコラムは2016年12月29日に公開されたものです)

Innocent Age
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから