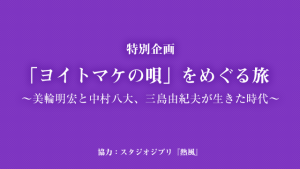立教大学の学生だった中西禮三(後の なかにし礼)はシャンソン喫茶でアルバイトするようになり、美輪明宏がホームグラウンドにしていたことで知られるシャンソン喫茶「銀巴里」へも、1950年代の後半から熱心に通うようになっていた。
そしていつしかシャンソン歌手のために訳詞を手がけるようになり、次々に仕事を頼まれていったのだが、それは生活のためのアルバイトであった。
なかにし礼が歌謡曲の作詞家になったのは、学生のまま結婚した2年後。1963年に伊豆へあらためて新婚旅行に行ったときに、下田国際東急ホテルで石原裕次郎から声をかけられたのがきっかけだった。
自身が興した石原プロモーションが製作する映画の第1作『太平洋ひとりぼっち』のロケで、石原裕次郎は伊豆に滞在していた。
ホテルの入り口に「石原裕次郎ご一行様」と書いてあったので、ホテル内には大スターがいるという緊張がみなぎっていたという。
なかにし礼と新妻が夕食を終えてザワザワしているロビーに出て来ると、奥にあるバーのカウンターに座っていた石原裕次郎と目が合った。
すると、指で招かれているように思えたので、自分の胸を指さして「僕ですか」という身振りをすると、石原裕次郎が頷いた。
大スターの前に呼ばれた二人に向かって、石原裕次郎は「お二人さんが1等賞、いっぱい飲もう」と気さくに声をかけてきた。
撮影が終わって事務所の専務・中井景と飲んでいた石原裕次郎は、退屈しのぎに客の大半を占めていた新婚カップルの品定めをやっていたという。
会話をしているうちにシャンソンの訳詞で生活している大学生だという話になったとき、石原裕次郎がはっきりとした口調でこう言った。
「日本人なら日本の歌謡曲を書けよ。作詞家になってガーンとヒットする歌をさ」
そしていい歌が書けたら、いつでも自分のところに持って来いとも付け加えたのだ。
それから1年以上が過ぎて、なかにし礼は手応えのある歌謡曲の歌詞が出来たので、自分でギターを弾いて曲をつけるとテープに歌を吹き込んだ。
石原プロに持っていくと中井と担当スタッフがテープを聴いてくれて、「いちおうお預かりしておきましょう」と受け取ったが、それっきりなしのつぶてだった。
なかにし礼は1965年の春に大学を卒業する予定で、そろそろどこかに就職しないとやっていけないと思い始めた。
そんな時に、レコード会社から電話をもらった。面識のなかったポリドール・レコードの女性ディレクター、松村慶子から頼まれた仕事は、タンゴ歌手の菅原洋一に歌わせるシャンソンの「恋心」と、B面に入れる「たそがれのワルツ」の日本語詞だった。
カントリーのスタンダード・ソングだった「I really don’t want to know」は、すでに日本語の歌詞がついて「たそがれのワルツ」と呼ばれていた。
しかし、なかにし礼はその原曲を聴いていて、自分のなかで初めて「ひらめき」を感じたので、新たに「知りたくないの」という日本語詞を書き上げた。最初の2行の言葉が生まれた瞬間、それまで体験したことのなかった感覚になったという。
千曲の訳詞をやっていて一度も感じたことのない歴然たるひらめき――――それは私にとって一千分の一の歓喜としか表現できない戦慄すべき出来事でした。
その意味では作詞家として、手応えのある自信作だった。
しかし、「恋心」のB面だったこともあって、レコードが発売になってもさほど注目されることはなかった。ただ菅原洋一がレギュラーで出演していたホテル高輪のラウンジでは、毎晩かならずレパートリーとして歌っていたことで、徐々に客席の女性からリクエストが増えてきた。
夜の巷で静かに「知りたくないの」が動き始めていたころ、男性コーラス・グループのロス・インディオスのための曲を探していた松村から、なかにし礼は渋谷のバーで「なにかいい歌ないの?」と聞かれた。
そこで1年以上も石原プロに預けたままのテープのことを話して、その場で壁にかかっていたギターを借りて自分で歌ってみせた。すると、松村がその歌を気に入ってくれただけでなく、たまたま石原プロから預かっていた新人歌手とのデュエットというアイデアを思いついたのである。
こうして処女作のテープがついに日の目を見ることになった。裕圭子とロス・インディオス名義で1966年に発売された「涙と雨にぬれて」は、レコードの売れ行きはまずまず合格点といったところだった。
ところが曲の良さに気づいたビクター・レコードが、「愛して愛して愛しちゃったのよ」の大ヒットで脚光を浴びていたシャンソン歌手出身の田代美代子と、和田弘とマヒナスターズとデュエットでカヴァーしたことで状況が変わった。
最も脂が乗っていた時期のマヒナスターズだったから、こちらは順調にヒット曲となって、作詞家・なかにし礼の時代が幕を開けることになったのだ。
ちょうどその頃、銀座のバーやクラブのホステスたちの間では、菅原洋一の「知りたくないの」が評判になり始めていた。有線放送の普及とともに赤坂や新宿などのネオン街にも広がって、静かなブームになってきたのである。
それに気づいたポリドールがA面とB面を入れ替えて発売したことで、1966年の後半から1967年にかけて大ヒットを記録した。
私はそのとき、自分が二年前に感じたひらめきが間違いではなかったことを確信しました。あのひらめきがなかったら、歌は絶対にヒットしない、逆に言えば、そういうひらめきがあったならば、その歌は絶対にヒットする。
「知りたくないの」がブレイクしたことを皮切りに、1967年になると時代の要請であったかのように、なかにし礼のもとに仕事が舞い込み始めた。
石原プロの所属で再デビューを果たす黛ジュンのために「恋のハレルヤ」を書いたところ、爆発的な大ヒットになって、「乙女の祈り」「霧の彼方に」と続いた。
更にはブームを巻き起こしていたグループサウンズでも、タイガーズの「花の首飾り」とテンプターズの「エメラルドの伝説」という、ライバル同士の2大バンドを手がける一方で、ゴールデンカップスには「愛する君に」「本牧ブルース」を提供するなど、なかにし礼の書く歌はヒットが途切れなく続いていった。
なかにし礼は、当時を振り返ってこのように述べている。
「あれらの歌は果たして、本当に私が書いたものなのだろうか」と。筆を執って走らせていたのはたしかに私ではありましたが、私は何か別の存在から指令を受けて書いたのではないか―――。
1964(昭和39)年から昭和が終わるまでのおよそ25年間で、作詞が約3000曲、先行する5年間の訳詞1000曲を合わせると合計で4000曲の歌詞を書き、ミリオンセラーは30曲にものぼった。
(注)本コラムは2017年5月5日に公開されています。なお なかにし礼氏の発言は、「NHK知る楽 探究 この世界 2009年8-9月 不滅の歌謡曲 なかにし礼」からの引用です。

「なかにし礼と75人の名歌手たち」
●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから
●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』
TAP the POPが初書籍を出版しました!
「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?
この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる
今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。
「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。
▼Amazonで絶賛発売中!!
『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから